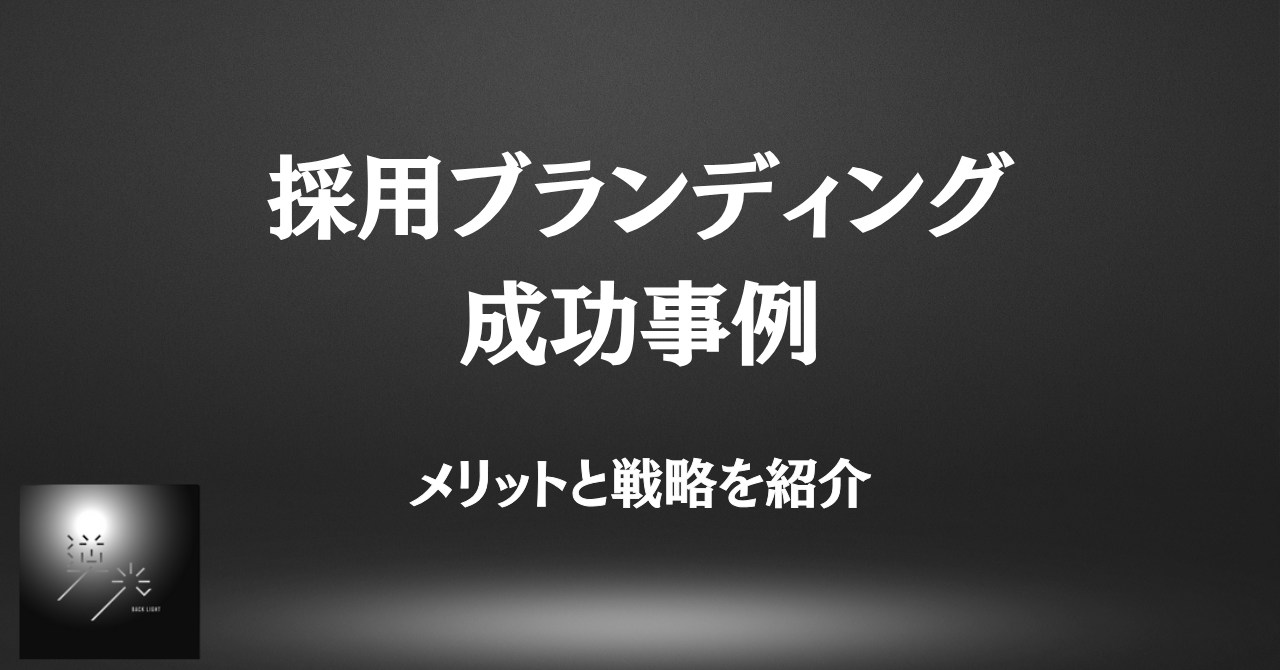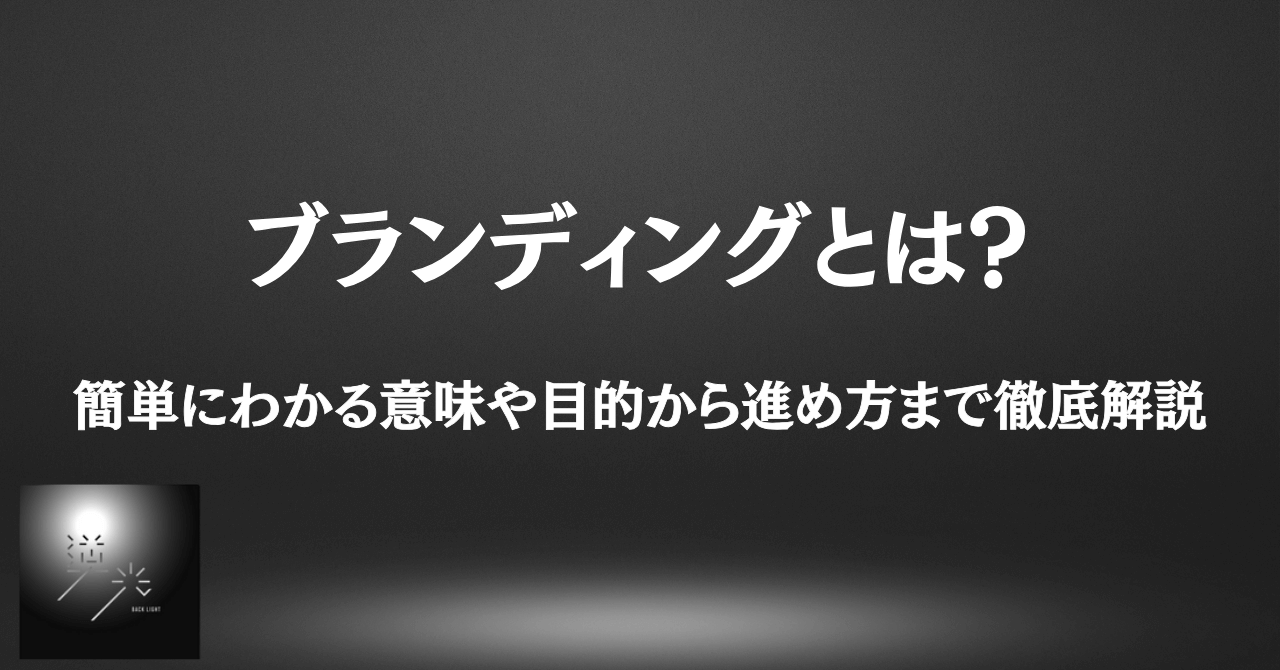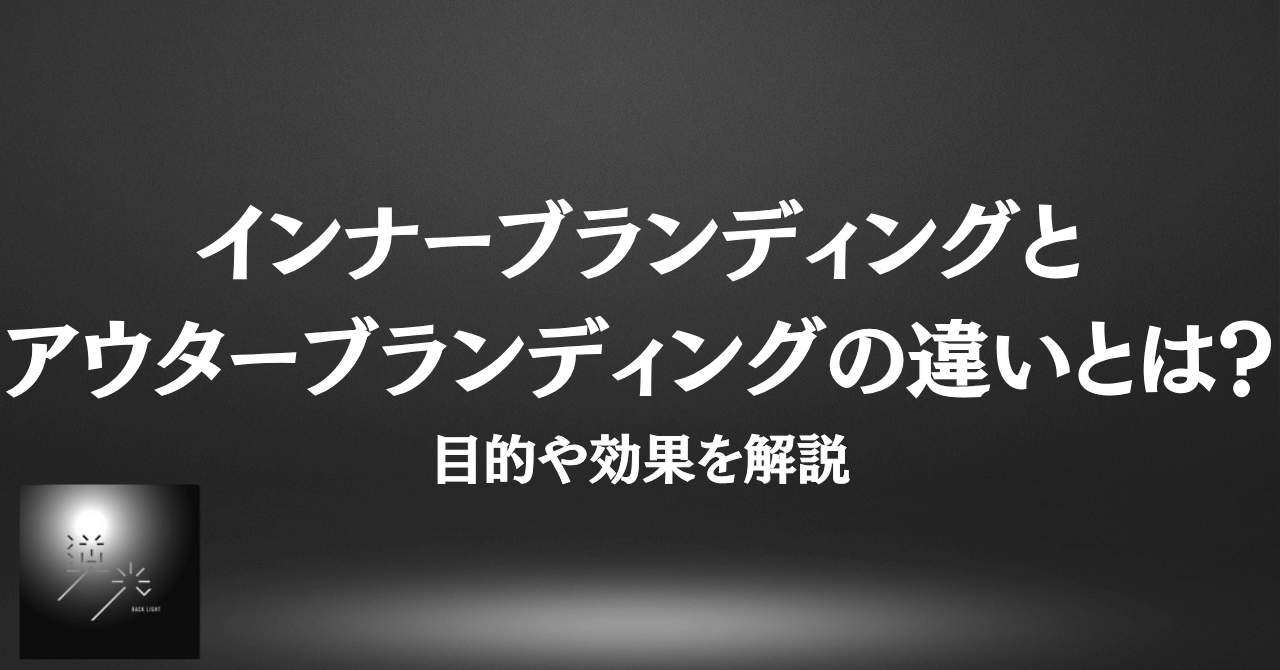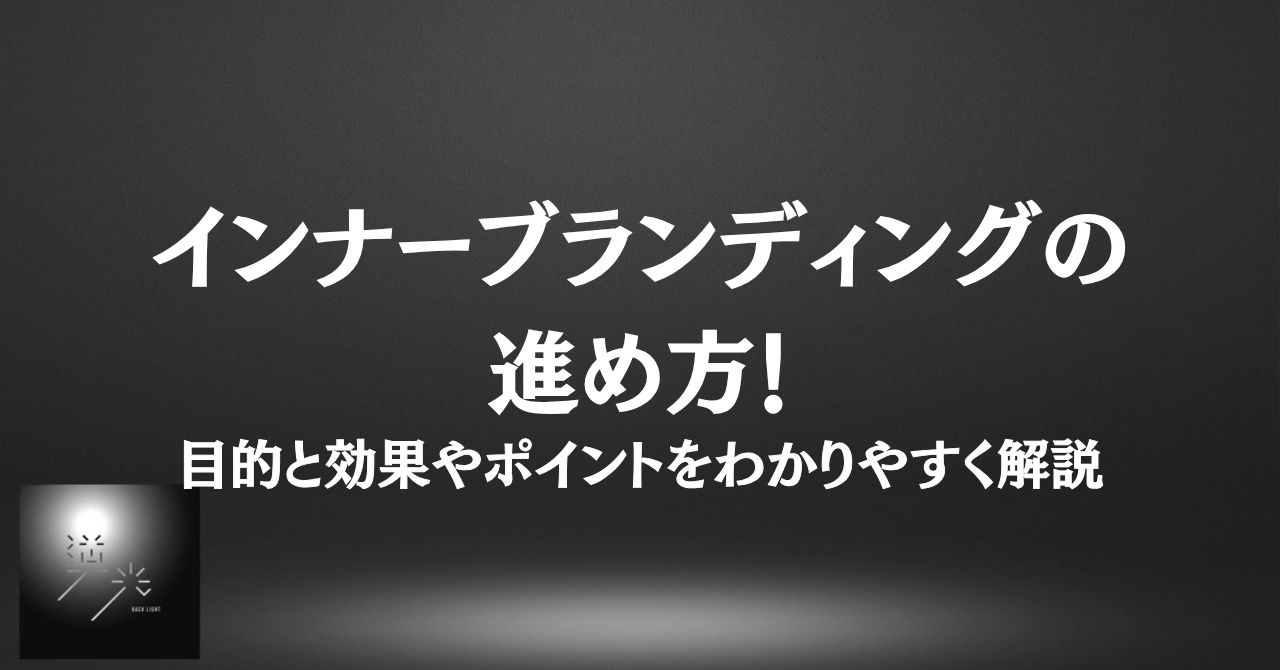「優秀な人材から応募が来ない」「内定を出しても辞退されてしまう」。
そんな悩みを抱えていませんか。
採用競争が激化する現代において、従来の手法だけでは求める人材に出会うことは困難です。
この状況を放置すれば、事業成長の鈍化は避けられません。解決の鍵を握るのが「採用ブランディング」です。
企業の魅力を正しく伝え、共感を呼ぶことで、採用活動を有利に進める戦略を指します。
本記事では、採用ブランディングのメリットや具体的な進め方、そして国内企業の成功事例10選を徹底解説します。
成功と失敗の両面から学び、自社の採用戦略をアップデートしましょう。
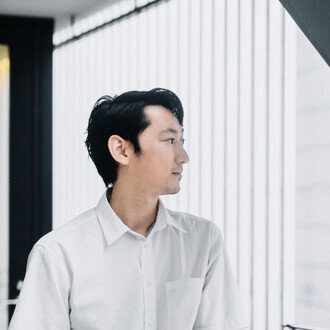
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
INDEX
- 採用ブランディングとは?
- 採用ブランディングのメリット2選
- 応募者の質と量が向上する
- 採用コスト削減につながる
- 採用ブランディングの成功事例10選
- 三幸製菓株式会社
- 株式会社メルカリ
- 日本マクドナルド株式会社
- 株式会社サイバーエージェント
- ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)
- エイベックス株式会社
- 伊藤忠商事株式会社
- ソフトバンクグループ株式会社
- 株式会社SmartHR
- サイボウズ株式会社
- 採用ブランディングを成功させる5ステップ
- ターゲット人材を具体化する
- EVPを言語化し社内外に発信
- インナーブランディングで社員を巻き込む
- タッチポイントを最適化する
- 効果測定と改善を継続する
- 採用ブランディングの成功事例から見えた共通ポイント
- 経営者コミットメント
- 社員参加型ストーリーテリング
- 多チャネル発信と一貫性
- データドリブンな改善
- 採用ブランディングの失敗例4選
- EVPと現実の乖離
- 一過性キャンペーン依存
- 測定指標の欠如
- 社内浸透不足
- 採用ブランディングの成功事例に関してよくある質問
- 採用ブランディングを成功させるコツは?
- 失敗するとどうなる?
- 採用ブランディングでやることは?
- 採用ブランディングのターゲットは?
- 採用ブランディングの成功事例を自社に活かすコツ【まとめ】
採用ブランディングとは?
採用ブランディングとは、求職者に対して企業の魅力を発信し「この会社で働きたい」というイメージを高めるための戦略です。
商品ブランドづくりと異なり、「働く場所」としての企業の価値や理念、カルチャーを多面的に伝えるのが特徴になります。
具体的には、自社の企業価値や目指す姿を言語化し、求職者にアピールする活動を指します。
単に採用サイトや求人広告を作るだけでなく、他社にはない自社ならではの魅力を発信し、企業イメージを向上させていく取り組みです。
島根県は、求職者やその家族が感じる
- 「企業の価値」
- 「その企業で働くイメージ」
を高めるために、企業理念やビジョン、理想の社員像、職場の雰囲気などを戦略的に情報発信する採用活動を「採用ブランディング」と定義しています。
また、この取組によって採用活動を効率的に進められ、採用力の向上に繋がるとされています。
実際、島根県では若者へのアピールを意識した中小企業の採用ブランディング取組に対し、経費の一部を補助する制度も設けられているのです。
単なる人材募集ではなく、長期的視点で自社にマッチする人材を確保し、企業の競争力を高めるための重要な戦略とも言えます。
採用ブランディングの基本的な考え方についてはこちらをご参照ください。
→採用ブランディングとは?目的や方法・メリットを事例とともに解説
採用ブランディングのメリット2選
採用ブランディングに力を入れることで、企業は多くの恩恵を受けられます。
ここでは、採用活動に直結する特に大きな2つのメリットを解説します。
応募者の質と量が向上する
採用ブランディングに取り組む最大のメリットは、応募者の質と量がともに向上することです。
企業の理念やビジョン、働く環境のリアルな姿が明確に伝わることで、それに共感し、自社のカルチャーにマッチする可能性の高い人材からの応募が増加します。
なぜなら、求職者は事前に「この会社は自分に合っているか」「入社後に活躍できるか」を具体的にイメージできるため、入社意欲の高い状態で選考に進むからです。
結果として、採用プロセスにおけるミスマッチが減少し、内定承諾率の向上や入社後の定着・活躍が期待できます。
これは、数打てば当たるといった場当たり的な採用から脱却し、企業の未来を共に創る仲間を集めるための、極めて効果的なアプローチです。
採用コスト削減につながる
採用ブランディングは、長期的な視点で見ると採用コストの大幅な削減を実現します。
「あの会社で働きたい」というブランドイメージが市場に浸透すれば、企業の知名度や魅力そのものが求職者を引きつける力を持つからです。
具体的には、高額な費用がかかる求人広告媒体や人材紹介サービスへの依存度を下げられます。
自社の採用サイトやオウンドメディア、SNS経由での直接応募が増加し、採用単価を抑制できるのです。
実際に、ブランディングに成功している企業では、広告費をかけずとも優秀な人材からの応募が絶えない状態を作り出しています。
初期投資は必要ですが、将来的に持続可能でコスト効率の高い採用体制を築くための、効果的な一手といえるでしょう。
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用ブランディングの成功事例10選
ここでは、採用ブランディングに成功している企業の具体的な事例を10社紹介します。
各社がどのような戦略で求職者の心を掴んでいるのか、その工夫を見ていきましょう。
三幸製菓株式会社

新潟発のお菓子メーカー、三幸製菓株式会社の採用ブランディング成功事例です。
同社は知名度が大手に比べ低く、限られた採用予算で人材獲得を図る必要がありました。
そこで三幸製菓は大胆なアイデアで自社の魅力を発信します。
例えば、応募者に選考内容を選ばせる「カフェテリア採用」や、たった一問で完結する「日本一短いES(エントリーシート)」を導入しました。
これらユニークな取り組みがテレビや新聞で話題となり、企業認知度が飛躍的に向上します。
結果として、三幸製菓の新卒エントリー数は300名から13,000名へ急増しました。
自社を全国にアピールしファンを増やしたことが奏功し、地方企業でありながら優秀な学生を全国から集めることに成功したのです。
「雪の宿」「チーズアーモンド」といった製品ブランドの親しみやすさも活かしつつ、会社そのものの魅力を発信した三幸製菓は、採用ブランディングにおける地方企業の成功例として知られています。
株式会社メルカリ
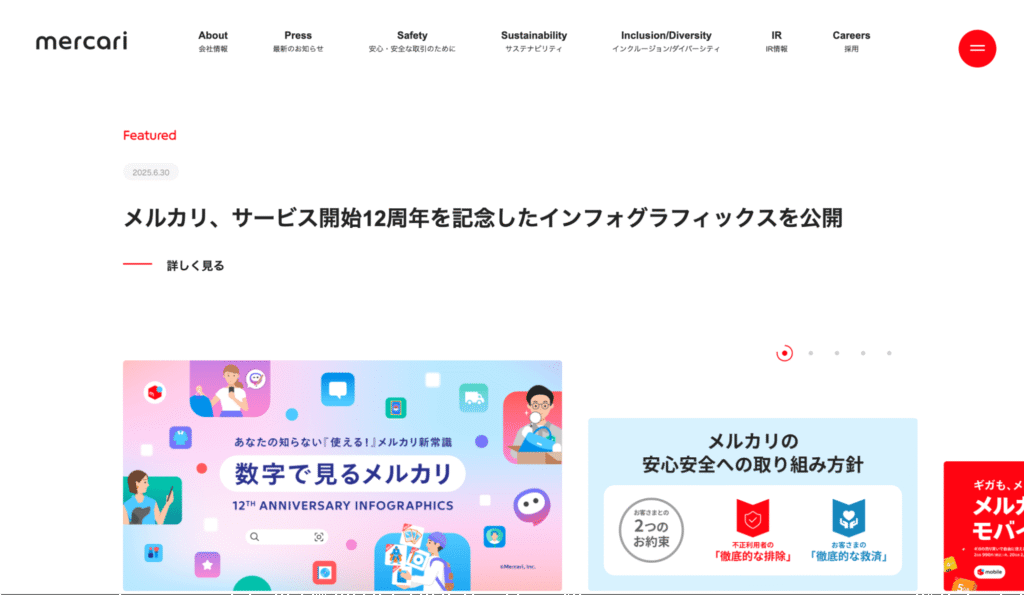
フリマアプリで急成長を遂げたメルカリは、「Go Bold(大胆にやろう)」をはじめとする3つのバリューを軸にした採用ブランディングを展開しています。
採用サイトやオウンドメディア「mercan(メルカン)」を通じて、社員の挑戦や失敗談、多様な働き方などを赤裸々に発信。
企業の価値観に共感する人材を世界中から惹きつけ、事業の成長を支える組織基盤を強固なものにしています。
日本マクドナルド株式会社

世界的なブランドである日本マクドナルドは、特にアルバイト採用において強力な採用ブランディングを展開しています。
同社が発信するメッセージの核は「成長」。
年齢や経験に関わらず、誰もがクルーとして働きながら成長できる機会があることを一貫して伝えています。
テレビCMやウェブサイト、店舗でのポスターなどを通じて、実際に働くクルーの生き生きとした姿や成長ストーリーを発信。
これにより、「マクドナルドで働くことは、スキルアップや自己成長につながる」というポジティブなイメージを確立し、安定した人材確保を実現しています。
株式会社サイバーエージェント

サイバーエージェントは、「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンのもと、挑戦意欲の高い若手人材を惹きつける採用ブランディングで知られています。
新卒採用においては、内定者時代から事業責任を任せる「CA-GYM」や、事業プランコンテスト「ジギョつく」など、成長機会の豊富さを具体的に提示。
「実力主義」「挑戦できる環境」を求める学生にとって、非常に魅力的な企業イメージを確立しています。
経営層が自らSNSやメディアでビジョンを語ることも多く、一貫したメッセージが求職者に強く響いています。
ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)

ユニクロを展開するファーストリテイリングは、「グローバルワン・全員経営」という考え方を採用ブランディングの核に据えています。
採用メッセージとして「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」を掲げ、単なるアパレル企業ではなく、世界を舞台に社会課題を解決する企業であるという壮大なビジョンを発信。
地域正社員制度の導入や、若いうちから店長として経営経験を積めるキャリアパスを提示することで、多様な働き方を求める人材や、グローバルなキャリアを目指す優秀な人材の獲得に成功しています。
エイベックス株式会社
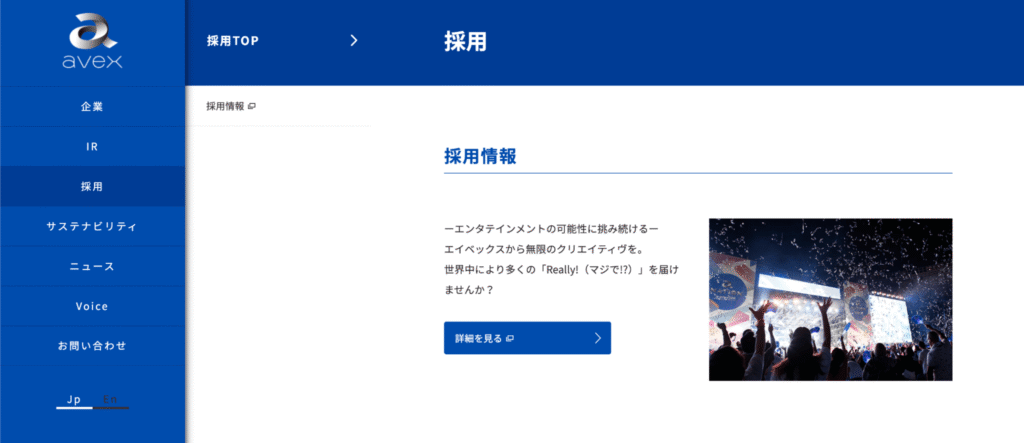
エイベックス株式会社は、「Mad Pure」というタグラインを掲げ、エンターテインメント業界で尖った才能を求める姿勢を鮮明に打ち出しています。
これは「熱狂して、ピュアにやり抜く」という意味が込められており、同社が求める人材像を端的に表現した言葉です。
採用サイトやSNSでは、常識にとらわれず新しいエンタテインメントを創造しようとする社員の姿や、その情熱を伝えるコンテンツが数多く発信されています。
このブランディングにより、「自分の個性や情熱を仕事に活かしたい」「エンタメの世界で何かを成し遂げたい」と考える尖った才能を持つ求職者からの応募を集めることに成功。
企業が本当に求める人材にだけ響く強いメッセージを発信することで、採用のミスマッチを防ぎ、組織の創造性を高め続けています。
伊藤忠商事株式会社

伊藤忠商事株式会社は、「ひとりの商人、無数の使命」というコーポレートメッセージのもと、商社パーソンとしての哲学や働きがいを伝えることで、他社との差別化を図っています。
特に「朝型勤務」の導入など、先進的な働き方改革を積極的にアピールしているのが特徴です。
長時間労働が当たり前とされがちな商社業界において、健康的に働き、生産性を高めるというメッセージは、ワークライフバランスを重視する現代の優秀な学生にとって非常に魅力的です。
また、個々の社員が「商人」として主体的にビジネスを創造していくストーリーを発信することで、仕事のやりがいやスケールの大きさを伝えています。
結果として、企業の利益だけでなく社会的な使命も追求したいと考える、質の高い人材の獲得に成功しています。
ソフトバンクグループ株式会社
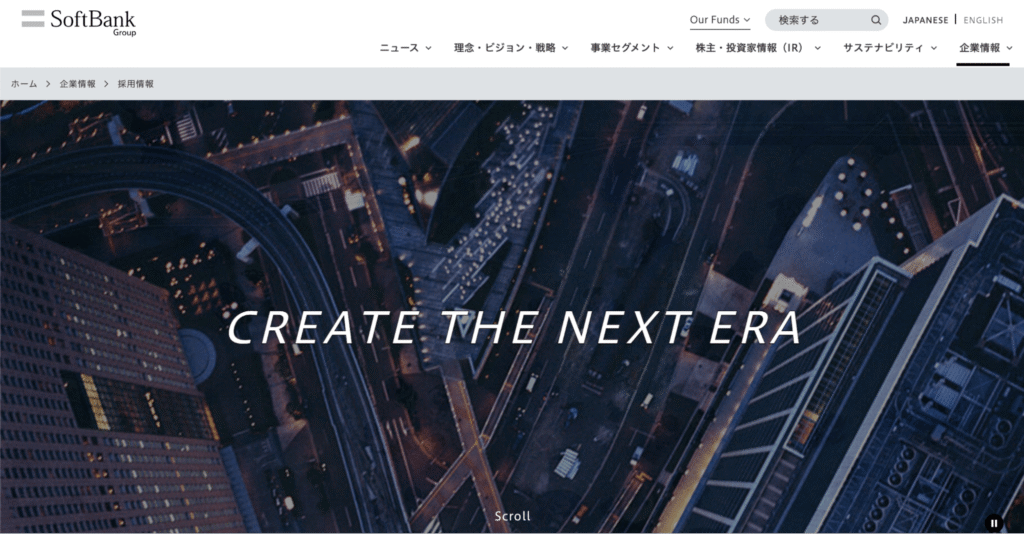
「情報革命で人々を幸せに」という経営理念を軸に、常に未来志向で挑戦的な企業イメージを打ち出しているのがソフトバンクです。
採用活動においても、孫正義社長自らがビジョンを語る姿や、AIなどの最先端技術への大規模な投資といったニュースそのものが強力なブランディングとなっています。
「No.1」にこだわる姿勢や、圧倒的なスピード感、世界を変えるような大きな仕事に携われる可能性を示すことで、野心と情熱を持った人材を世界中から集めています。
株式会社SmartHR

クラウド人事労務ソフトを提供するSmartHRは、「オープンな社内情報」を武器に採用ブランディングを成功させています。
自社の情報を可能な限りオープンにするというカルチャーのもと、全社員の給与テーブルや評価制度、議事録までをも公開。
この徹底した透明性が、求職者に対して「誠実な会社である」という強い信頼感を与えています。
結果として、同社のカルチャーにマッチし、自律的に働ける優秀な人材が、会社の規模拡大と共に集まり続けています。
サイボウズ株式会社

グループウェアで知られるサイボウズは、「100人100通りの働き方」を標榜し、多様なワークスタイルを許容する企業文化で知られています。
育児や介護との両立、副業、在宅勤務など、社員一人ひとりの事情に合わせた働き方を実現している事例をオウンドメディアで発信。
働きやすさを追求する姿勢が、優秀で自律した人材から選ばれる大きな理由となっています。
採用ブランディングを成功させる5ステップ
成功事例をただ真似るだけでは、自社に合った採用ブランディングは実現できません。
ここでは、自社の魅力を最大限に引き出し、効果的なブランディングを構築するための5つのステップを解説します。
より包括的な採用戦略の構築についてはこちらをご参照ください。
→採用戦略の成功事例!フレームワークを活用した作り方や戦略の立て方を分かりやすく徹底解説!
ターゲット人材を具体化する
採用ブランディングを成功させる第一歩は、「誰に」「何を」伝えたいのかを明確にすることです。
つまり、自社が本当に必要としているターゲット人材(ペルソナ)を具体的に定義します。
年齢やスキル、経験といった表面的な情報だけでなく、価値観、仕事観、キャリアプラン、情報収集の方法までを詳細に設定することが重要です。
このペルソナが明確であればあるほど、発信するメッセージやコンテンツの精度が高まり、ターゲットの心に響くブランディングが可能になります。
EVPを言語化し社内外に発信
次に、定義したターゲット人材に対して、自社が提供できる独自の価値を明確にする「EVP(Employee Value Proposition)」の言語化が必要です。
EVPとは「従業員価値提案」と訳され、社員がその企業で働くことで得られる魅力的な体験や報酬の総体を指します。
EVPは、給与や福利厚生といった金銭的な報酬だけでなく、事業の社会貢献性、挑戦的な仕事内容、良好な人間関係、キャリア成長の機会、独自の企業文化といった非金銭的な価値も含まれます。
「なぜ他社ではなく、自社で働くべきなのか」という問いに対する、説得力のある答えそのものです。
このEVPを明確な言葉にし、採用サイトや面接など、あらゆる接点で一貫して発信することが、ブランディングの核となります。
インナーブランディングで社員を巻き込む
採用ブランディングは、人事部だけで完結するものではありません。
社内に向けた「インナーブランディング」を通じて、全社員を巻き込むことが成功の鍵を握ります。
社員一人ひとりが自社のEVP(従業員価値提案)を深く理解し、共感し、自らの言葉で語れる状態を目指します。
なぜなら、社員こそが最も信頼性の高い「企業の広告塔」だからです。
社内報や全社集会での情報共有、理念研修などを通じて、自社の魅力を再認識してもらう機会を設けましょう。
社員が自社に誇りを持ち、友人や知人に自社のことをポジティブに語るようになれば、リファラル採用の活性化にもつながり、強力な採用チャネルとなります。
インナーブランディングの詳しい効果についてはこちらで解説しています。
→インナーブランディングの効果とは?メリットや成功事例をわかりやすく解説
タッチポイントを最適化する
VPをターゲットに届けるための具体的な施策を実行するフェーズです。
求職者が企業と接触するあらゆる「タッチポイント(接点)」で、一貫したメッセージを発信することが重要になります。
| タッチポイントの例 | 施策の例 |
|---|---|
| 採用サイト・LP | EVPを体現したデザインやコンテンツ、社員インタビューの掲載 |
| SNS (X, Instagram, etc.) | 日常の社内の雰囲気や社員の紹介、イベントの告知 |
| オウンドメディア | 企業のカルチャーや事業の裏側、社員の働きがいを伝える記事 |
| 会社説明会・イベント | EVPに基づいたプレゼンテーション、社員との座談会 |
| 面接・面談 | 面接官がEVPを理解し、求職者の魅力引き出しと自社PRを行う |
これらのチャネルを連携させ、どこに触れても「〇〇社らしさ」が伝わる状態を目指します。
効果測定と改善を継続する
採用ブランディングは、一度実施して終わりではありません。
設定した目標(KPI)が達成できているかを定期的に測定し、改善を繰り返すPDCAサイクルを回すことが成功の鍵です。
応募者数や内定承諾率、採用単価といった定量的な指標に加え、応募者の質の変化や面接時の志望動機の深度といった定性的な変化も追跡します。
データに基づいて施策の効果を客観的に評価し、より効果的な発信方法やコンテンツへと継続的にブラッシュアップしていく姿勢が求められます。
採用ブランディングの成功事例から見えた共通ポイント
数々の成功事例を分析すると、いくつかの共通点が見えてきます。
ここでは、自社の戦略立案に役立つ4つの成功ポイントを解説します。
経営者コミットメント
成功している企業では、例外なく経営層が採用ブランディングに深くコミットしています。
経営者自らがビジョンを語り、採用イベントに登壇し、SNSで発信するなど、その熱意が求職者に直接伝わっています。
採用を単なる人事マターではなく、経営の最重要課題と位置づける姿勢が、全社的な協力体制を生み、ブランディングに強力な推進力を与えるでしょう。
社員参加型ストーリーテリング
成功事例に共通するもう一つのポイントは、社員が主役となる「ストーリーテリング」を実践している点です。
企業の魅力は、公式発表の言葉よりも、そこで働く社員のリアルな体験談を通じてこそ、深く伝わります。
実際に働く社員が、仕事のやりがいや困難を乗り越えた経験、職場の雰囲気などを自らの言葉で語るコンテンツは、求職者にとって高い信頼性と共感性を持ちます。
オウンドメディアでのインタビュー記事や、社員が登壇するイベント、SNSでの日常的な発信など、社員が自然な形で登場する機会を増やすことが重要です。
企業が語る「理想」と社員が語る「現実」が一致していることで、ブランドの信頼性は飛躍的に高まります。
多チャネル発信と一貫性
現代の求職者は、一つの情報源だけを鵜呑みにしません。
採用サイト、SNS、口コミサイト、ニュース記事など、複数のチャネルから情報を収集し、多角的に企業を評価します。
採用ブランディングの成功企業は、この求職者の行動を理解し、様々なチャネルを組み合わせて戦略的に情報を発信しています。
そして、最も重要なのは、全てのチャネルで発信するメッセージや世界観に「一貫性」があることです。
採用サイトで語られるビジョンと、SNSで見える日常の風景、面接官の言葉がすべてリンクしていることで、求職者は企業に対して一貫したブランドイメージを抱き、信頼を深めるのです。
データドリブンな改善
勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて戦略を改善していく姿勢も共通しています。
どのチャネルからの応募が採用に結びついているのか、どのようなコンテンツが求職者の関心を引いているのか、といったデータを分析し、次の施策に活かしています。
応募者数や内定承諾率といったKPIを定期的に観測し、PDCAサイクルを回すことで、ブランディング活動を継続的に最適化しているのです。
採用ブランディングの失敗例4選
成功の裏には多くの失敗も存在します。
ここでは、多くの企業が陥りがちな4つの失敗パターンを知り、同じ轍を踏まないための対策を学びましょう。
EVPと現実の乖離
最も陥りやすい失敗が、発信する魅力(EVP)と、入社後の現実が大きくかけ離れているケースです。
採用サイトや説明会で「風通しが良く、挑戦できる社風」とアピールしても、実態がトップダウンで保守的な文化であれば、新入社員はすぐにギャップを感じて離職してしまいます。
これは企業の評判を著しく損ない、結果的に採用をさらに困難にします。
ブランディングは、等身大の魅力を誠実に伝えることから始めるべきです。
一過性キャンペーン依存
採用ブランディングを、短期的なキャンペーンや派手な採用イベントのことだと誤解しているケースも見られます。
一時的に注目を集めることはできても、日常的な情報発信や社内文化の醸成が伴わなければ、ブランドとして定着しません。
採用ブランディングは、継続的な情報発信と社内外での地道なコミュニケーションの積み重ねによって成り立つ、長期的な取り組みであると認識することが重要です。
測定指標の欠如
「何となく良さそうだから」という理由で施策を始め、効果を測定する指標(KPI)を設定していないケースも失敗に繋がります。
KPIがなければ、どの施策が成功し、どの施策が失敗したのかを客観的に評価できません。
結果として、効果のない施策にコストと時間を費やし続けることになります。
応募者の質や量、内定承諾率、採用単価など、具体的な指標を定めて効果測定を行うことが不可欠です。
社内浸透不足
経営層や人事部だけが盛り上がり、現場の社員が「会社が何をしようとしているのか知らない」「協力するメリットがわからない」という状態では、ブランディングは形骸化します。
面接官が採用コンセプトと違う話をしてしまったり、リファラル採用に協力が得られなかったりと、様々な弊害が生まれます。
インナーブランディングを通じて、全社員を巻き込み、同じ方向を向いて活動することが不可欠です。
社内浸透の具体的な進め方についてはこちらで詳しく解説しています。
→インナーブランディングの進め方!目的と効果やポイントをわかりやすく解説
採用ブランディングの成功事例に関してよくある質問
最後に、採用ブランディングに関して多く寄せられる質問にお答えします。
疑問点を解消し、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。
採用ブランディングを成功させるコツは?
採用ブランディングを成功させるコツは、自社の「らしさ」を深く理解し、それを一貫して伝え続けることです。
具体的には、ターゲット人材(ペルソナ)を明確に定め、その人に響く自社独自の価値(EVP)を定義します。
そして、経営者から現場社員まで全社を巻き込み、採用サイトやSNS、面接といった全ての接点で、その価値を誠実に、そして継続的に発信し続けることが成功の鍵となります。
失敗するとどうなる?
採用ブランディングに失敗すると、複数の悪影響が生じます。
まず、発信したメッセージと実態の乖離が大きい場合、早期離職者が増加し、企業の評判(口コミ)が悪化します。
これにより、優秀な人材から敬遠され、応募者の質が低下。
結果として採用コストは増大し、事業成長に必要な人材を確保できないという悪循環に陥る可能性があります。
採用ブランディングでやることは?
採用ブランディングでやることは、大きく5つのステップに分けられます。
- 自社が求める人材像を具体化する「ペルソナ設定」
- 自社が提供できる価値を定義する「EVPの言語化」
- 社員の共感を得る「インナーブランディング」
- 求職者との全接点で一貫したメッセージを伝える「タッチポイントの最適化」
- 効果を測定し改善を続ける「PDCAサイクルの実行」
これらを計画的に進めることが重要です。
採用ブランディングのターゲットは?
採用ブランディングのターゲットは、大きく分けて「社外(求職者)」と「社内(既存社員)」の2つです。
社外に対しては、自社が最も必要としている潜在的な候補者層(採用ペルソナ)がメインターゲットとなります。
一方で、社内の社員に対してインナーブランディングを行うことも非常に重要です。
社員が自社の魅力に共感し、誇りを持つことで、採用活動への協力やリファラル採用の活性化につながり、結果的に社外へのブランディング効果も高まります。
採用ブランディングの成功事例を自社に活かすコツ【まとめ】
本記事では、採用ブランディングの基礎知識から具体的な成功事例、成功のためのステップまでを網羅的に解説しました。
採用ブランディングとは、企業の独自の魅力を発信し、求職者から「選ばれる」存在になるための戦略です。
成功すれば、応募の質と量が向上し、採用コストの削減にも繋がります。
成功の鍵は、まず自社が求める人材像を明確にし、競合にはない独自の価値「EVP」を定義すること。
そして、そのメッセージを経営者から社員まで全社一丸となって、採用サイトやSNSなど様々なチャネルで一貫して発信し続けることです。
紹介した成功事例は、いずれも自社の「らしさ」を深く理解し、それを誠実に、そして継続的に伝えています。
まずは自社の魅力は何か、誰に伝えたいのかを議論することから始めてみてはいかがでしょうか。
この記事が、貴社の採用活動を成功に導く一助となれば幸いです。