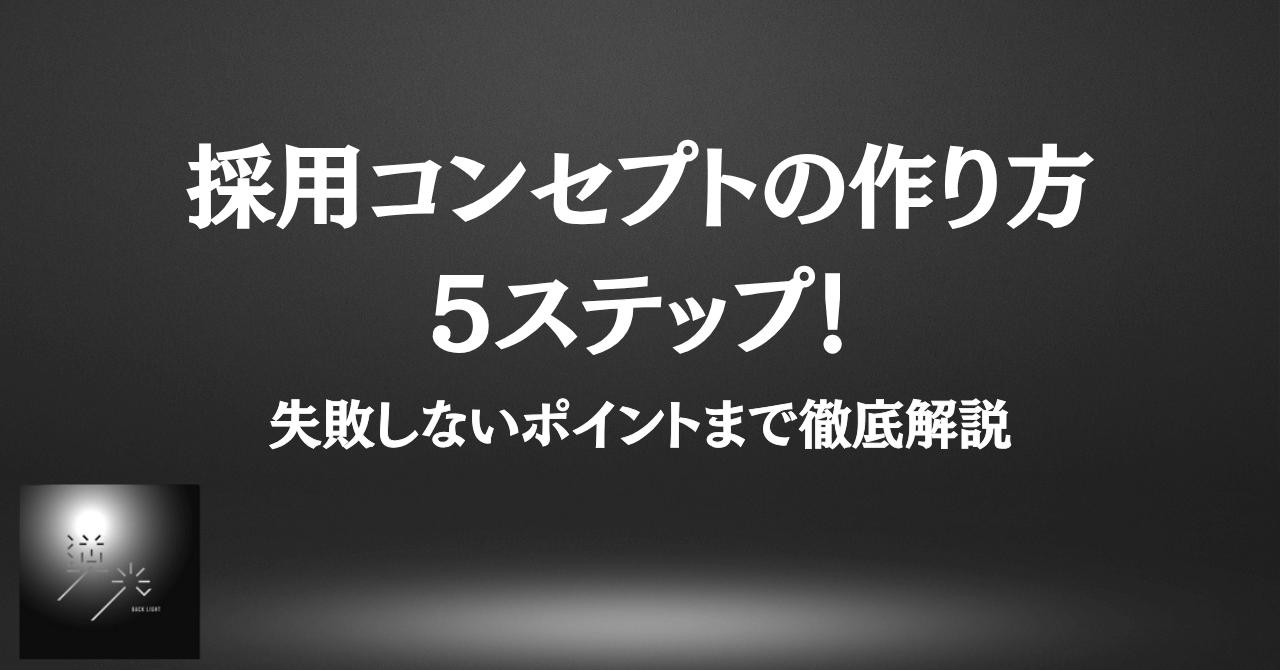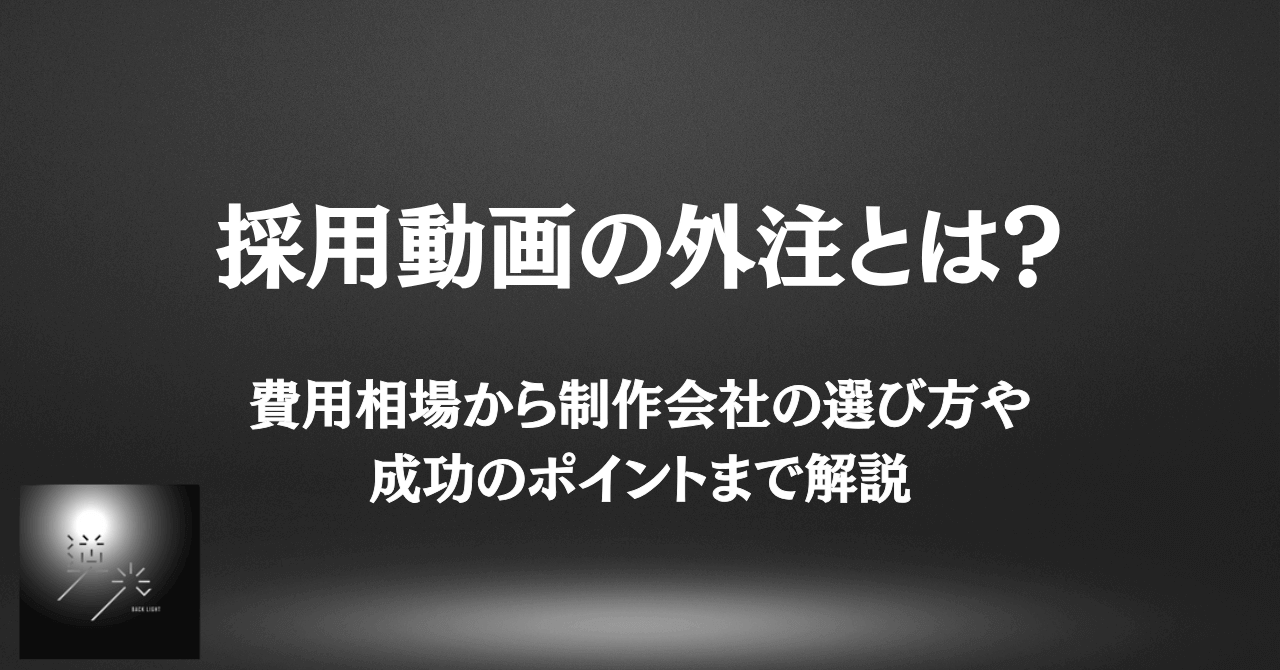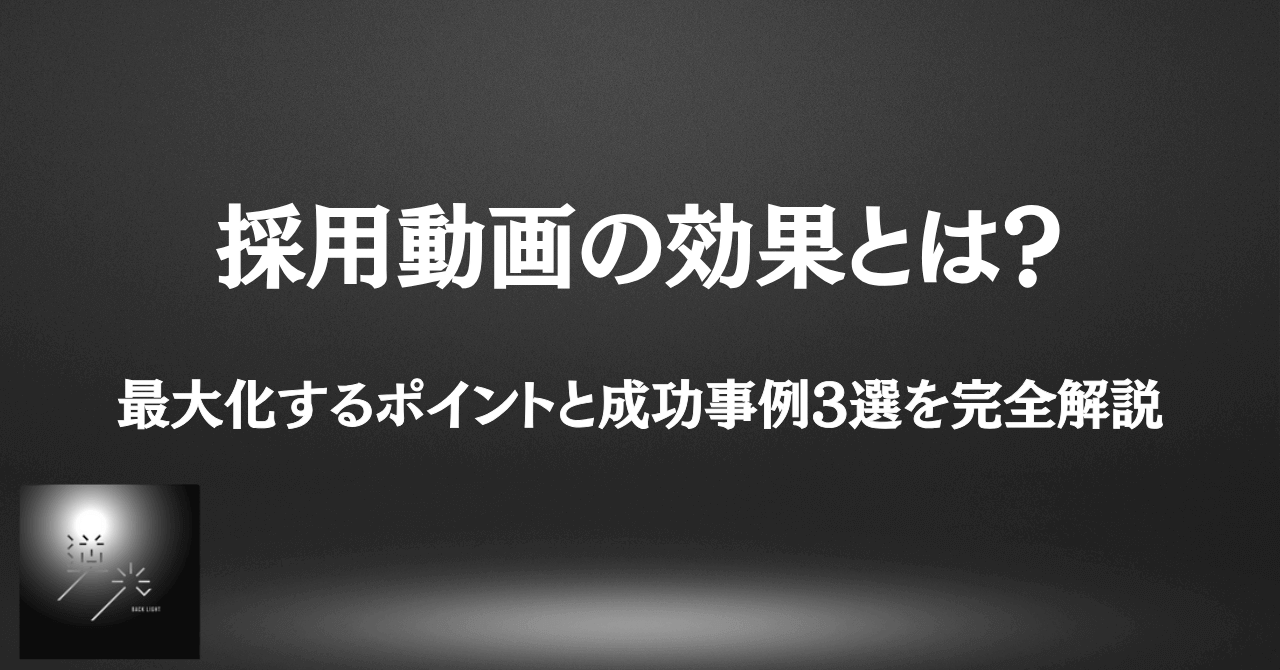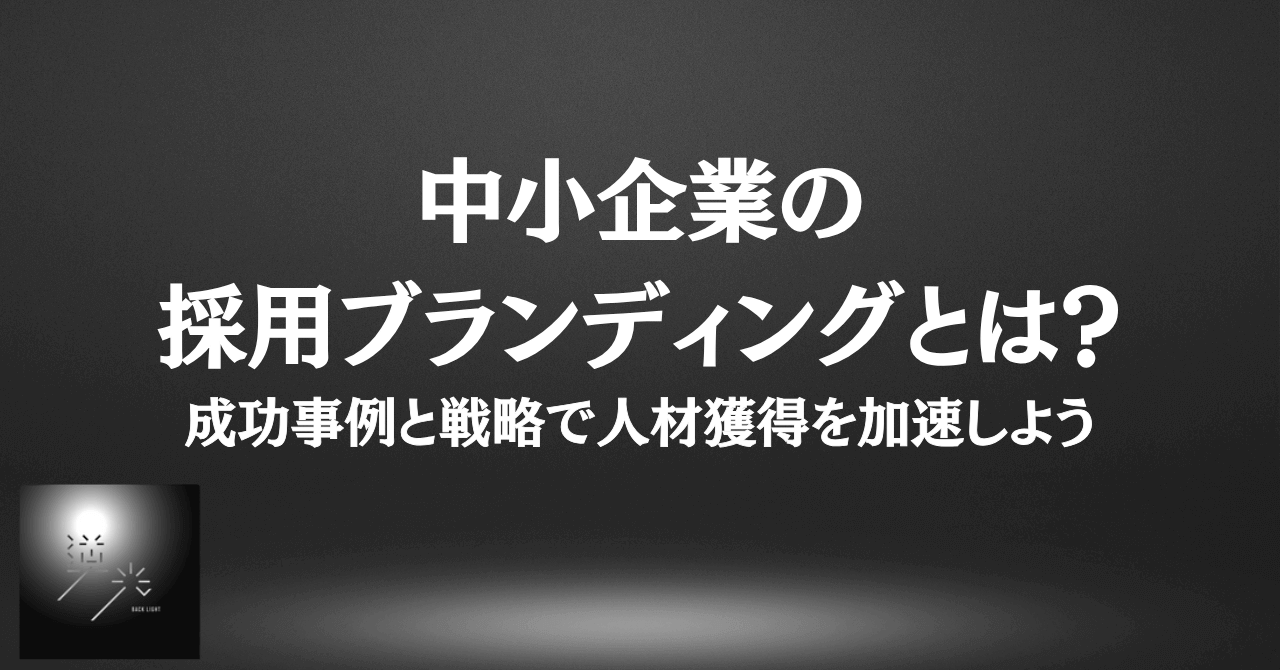「求める人材から応募が来ない」「内定を出しても辞退されてしまう」そんな悩みを抱えていませんか。
採用市場の競争が激化する中、ただ求人を出すだけでは優秀な人材の獲得は困難です。
このままでは採用コストばかりが増え、事業成長の足かせになりかねません。
その根本的な原因は、貴社の魅力が求職者に正しく伝わっていないことにあります。
この記事では、採用活動の羅針盤となる「採用コンセプト」の作り方を5つのステップで徹底解説。
誰でも実践でき、失敗しないためのポイントまで網羅しています。
ぜひ最後まで読み、競合に差をつける採用戦略の第一歩を踏み出してください。
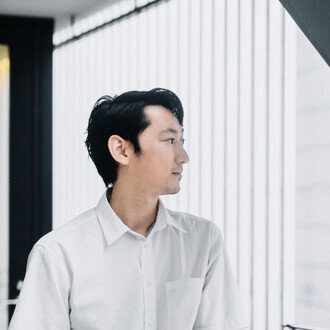
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用コンセプトとは?
採用コンセプトとは、「自社がどんな人材を、なぜ、どのように採用するのか」という採用活動の根幹をなす考え方やメッセージのことです。
多くの企業が採用活動を行う中で、他社との差別化を図り、採用活動全体に一貫性を持たせるために必要不可欠な要素といえます。
これは単なるキャッチーなスローガンや採用キャッチコピーとは一線を画します。
採用活動における「羅針盤」のような役割を果たし、「誰に」「何を」「どのように」伝えるかを明確に定義するものです。
「挑戦を楽しむ異端児、求む」といったコンセプトがあれば、求める人物像が明確になり、求人広告の文面、説明会の内容、面接での質問まで、すべてに一貫性が生まれます。
つまり、採用活動の成功を左右する重要な軸であり、戦略的な指針が採用コンセプトなのです。
採用ブランディング全体の戦略についてはこちらをご参照ください。
→採用ブランディングとは?目的や方法・メリットを事例とともに解説
採用コンセプトがもたらすメリット5選
採用コンセプトを明確にすることで、採用活動は劇的に変わり、様々な好影響が期待できます。
ここでは、企業が享受できる具体的な5つのメリットを詳しく解説します。
応募率の向上
採用コンセプトを明確にすることで、応募率を向上させることが可能です。
自社の魅力や求める人物像を明確な言葉で打ち出すことで、メッセージがターゲット人材の心に深く刺さり、「この会社で働いてみたい」と強く惹きつけられるためです。
例えば、「世界を驚かすプロダクトを、本気で創る仲間募集」というコンセプトを掲げたとします。
この熱量の高いメッセージに共感した、高い技術力と情熱を持つエンジニアからの応募は、漠然とした条件だけを並べた求人情報を出すよりも格段に増えるでしょう。
結果として、応募の「量」だけでなく「質」も高まり、効率的で質の高い母集団形成につながります。
内定辞退率の低減
内定辞退率の低減も、採用コンセプトがもたらす大きなメリットの一つです。
採用コンセプトを通じて、企業の価値観、文化、そして入社後の働き方を具体的にイメージできるため、求職者が抱く期待と入社後の現実とのギャップを最小限に抑えることが可能です。
選考過程でコンセプトに基づいた一貫性のある情報提供を続けることで、求職者は「説明会で聞いた話と、面接官の話が違う」といった不信感を抱きにくくなります。
企業への理解と共感が深まった状態で内定に至るため、入社意欲が非常に高まり、他社の内定と迷うことなく自社を選んでくれる可能性が高まります。
このように、入社前から求職者の期待値を適切にコントロールすることが、最終的な内定辞退率の低下につながるのです。
SNS拡散による母集団形成
魅力的な採用コンセプトはSNSで拡散され、結果的に母集団形成を促進します。
共感を呼ぶコンセプトは社員や候補者によってSNS上でシェアされやすく、普段リーチできない層にも企業の魅力が伝わります。
例えば、ある企業では、思わず共有したくなる斬新な採用コンセプトを掲げた結果、SNS経由で他業界志望だった人材からも応募が集まり採用の裾野が広がりました。
このようにSNS拡散によって自社に興味を持つ潜在層を増やせるのも、強い採用コンセプトならではのメリットです。
結果として応募者の母集団が拡大し、より多くの優秀な人材と出会える可能性が高まります。
SNS採用の詳しい施策についてはこちらで解説しています。
→SNS採用とは?メリットデメリットや成功事例でわかるソーシャルリクルーティングの始め方
TikTok採用の詳細についてはこちらをご参照ください。
→Tiktok採用とは?成功事例やメリットデメリットを網羅的に解説
面接官の評価軸統一
採用コンセプトは、社外へのアピールだけでなく、社内、特に面接官の評価軸を統一するという重要な役割も果たします。
「自社は、どのような価値観やスキルを持った人材を求めているのか」という明確な基準ができるため、面接官個人の主観や経験則による評価のブレがなくなります。
コンセプトに基づいて作成された評価シートや具体的な質問項目を用いることで、どの面接官が担当しても、一貫した基準で候補者の適性や能力を評価することが可能です。
これにより、「A面接官は合格にしたが、B面接官は不合格にした」といった評価の属人化を防ぎ、自社に本当にマッチした人材を見極める精度が格段に高まります。
結果として、採用の質が安定し、組織全体のパフォーマンス向上にもつながるのです。
ミスマッチ防止で早期離職率低減
採用コンセプトがもたらす最も重要なメリットは、入社後のミスマッチを防ぎ、早期離職率を大幅に低減させることです。
採用コンセプトによって、企業の価値観や文化、働き方に心から共感する人材が集まりやすくなるため、入社後に「こんなはずではなかった」と感じるケースが減少します。
実際に、厚生労働省の「新規学卒就職者の離職状況」によると、新規大学卒業就職者の就職後3年以内の離職率は32.3%(令和3年3月卒業者)と、依然として高い水準でした。
この大きな原因の一つとして、入社前後のギャップが挙げられています。
採用コンセプトは、このギャップを埋めるための強力なツールです。
例えば、「失敗を恐れず、100回の挑戦を称賛する文化」というコンセプトを掲げる企業には、安定志向の強い人材よりも、チャレンジ精神旺盛な人材が集まります。
入社後もその価値観が尊重される環境で働けるため、エンゲージメントが高く定着し、長期的な活躍が期待できるのです。
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用コンセプトの作り方5ステップ
ここからは、実際に自社に合った採用コンセプトを作るための具体的な5つのステップを解説します。
この手順に沿って一つずつ丁寧に進めれば、誰でも自社の魅力が伝わる効果的なコンセプトを設計できます。
現状分析と課題抽出
最初のステップは、自社の採用活動における現状を客観的に分析し、課題を明確に抽出することです。
まずは現在地を正確に把握しなければ、目指すべきゴール(=コンセプト)を正しく設定することはできません。
過去数年間の応募数、書類選考通過率、内定承諾率、入社後の定着率・離職率といった定量的なデータを分析し、ボトルネックがどこにあるのかを探ります。
それに加え、経営層や現場のマネージャー、活躍している社員や早期離職してしまった元社員、そして人事担当者など、様々な立場の人にヒアリングを行います。
「なぜ応募が少ないのか」「どんな人が定着し、活躍しているのか」「自社の本当の魅力や、逆に改善すべき点は何か」といった定性的な生の声を収集することが重要です。
ここで「理想の採用」と「現実」との間に存在するギャップを浮き彫りにすることが、的確な採用コンセプトを立てるための揺るぎない土台となります。
ターゲット人材ペルソナ設定
次に行うべきは、採用したいターゲット人材の具体的な人物像(ペルソナ)を詳細に設定することです。
「誰に」メッセージを届けたいのかが明確でなければ、誰の心にも響かない、ぼんやりとしたコンセプトになってしまいます。
年齢、性別、学歴、スキルといった表面的な情報だけでは不十分です。
その人物の価値観、性格、仕事に対する考え方、キャリアプラン、プライベートの過ごし方など、内面やライフスタイルまで深く掘り下げて設定します。
「どんな仕事のやりがいを感じるのか」「どんな働き方を理想としているのか」などを具体的にイメージすることで、そのペルソナに「刺さる」メッセージの輪郭がはっきりと見えてきます。
現在、社内で活躍しているハイパフォーマーをモデルに、その人物の特性を分析してペルソナを作成するのも非常に有効な方法です。
このペルソナ設定の解像度が高いほど、コンセプトの訴求力も格段に高まります。
企業らしさの言語化
続いて、競合他社にはない、自社ならではの魅力、つまり「企業らしさ」を言語化していきます。
求職者は複数の企業を比較検討しているため、その他大勢に埋もれない、自社が選ばれるべき理由を明確にする必要があります。
ここでは、マーケティングの基本的なフレームワークである「3C分析」を活用するのが非常に効果的です。
| 分析項目 | 内容 |
|---|---|
| 自社 (Company) | 企業理念、ビジョン、事業の独自性、技術力、社風、福利厚生、働く環境、社員の人柄など、自社の強みや特徴を徹底的に洗い出します。 |
| 競合 (Competitor) | 採用市場における競合他社が、どのような採用メッセージを発信し、どのような魅力を打ち出しているかを調査・分析します。 |
| 求職者(Customer) | ステップ2で設定したペルソナが、企業に対して何を求め、どのような点に魅力を感じるのかを分析します。 |
この3つの円が重なり合う部分、すなわち「競合にはなく、自社にあり、かつペルソナ(求職者)が強く求めている価値」。
これこそが、貴社独自の揺るぎない魅力(USP:Unique Selling Proposition)となります。
このUSPを明確な言葉に落とし込むことが、コンセプトの核を創り上げる上で極めて重要です。
採用戦略全体のフレームワークについてはこちらをご参照ください。
→採用戦略の成功事例!フレームワークを活用した作り方や戦略の立て方を分かりやすく徹底解説!
ワンフレーズ化するコツ
言語化した「企業らしさ」という核を、覚えやすく、心に響くワンフレーズへと磨き上げていきます。
採用コンセプトは、社内外の誰もが瞬時に理解し、記憶に残るようなシンプルさが求められるからです。
秀逸なワンフレーズを生み出すには、いくつかのコツがあります。
- ターゲットの言葉を使う
ペルソナが普段使っている言葉や、共感するような表現を取り入れることで、メッセージが「自分ごと」として捉えられやすくなります。 - ベネフィットを伝える
求職者がその会社で働くことで得られる魅力的な未来(スキルアップ、社会貢献、理想のワークライフバランスなど)を具体的に提示します。 - 意外性やインパクトを持たせる
「え?」と思わず二度見してしまうような、常識を覆す言葉や意外な言葉の組み合わせは、強く印象に残すことが可能です。(例:「日本で一番、社員が休む会社。」) - 行動を促す言葉を入れる
「~しようぜ」「~する仲間、求む」といった、仲間として参加を呼びかけるような言葉は、求職者の心を動かします。
いきなり一つに絞ろうとせず、まずはブレインストーミングで多くの候補を出すことが大切です。
そして、ペルソナに近い年齢層の若手社員などに意見を聞き、最も共感を得られたフレーズを選定することが望ましいです。
このワンフレーズが、今後の採用活動全体の旗印となります。
社内外への浸透施策
採用コンセプトは、作って終わりではありません。
社内外のステークホルダーに浸透させ、実際の採用活動に落とし込んで初めて価値を発揮します。
社外に向けては、採用サイト、求人広告、会社説明会、SNSなど、候補者との全ての接点でコンセプトに基づいたメッセージを発信します。
デザインや写真、動画などもコンセプトの世界観と一貫性を持たせることが重要です。
同時に、社内への浸透も不可欠です。特に、候補者と直接対話する面接官やリクルーターには、コンセプトの背景や意図を深く理解してもらうための研修を実施します。
全社員が自社の採用コンセプトを自分の言葉で語れる状態になることが理想です。
コンセプトが組織文化として根付くことで、採用活動はより強力なものになります。
採用コンセプト設計で陥りやすい失敗例
多くの企業が採用コンセプト作りに挑戦しますが、残念ながら意図した効果を得られず、失敗に終わるケースも少なくありません。
ここでは、そうした轍を踏まないために、よくある3つの失敗例とその対策を解説します。
理念とかけ離れたキャッチコピー化
よくある失敗は、実態や企業理念とかけ離れた、ただ耳障りの良いだけのキャッチコピーになってしまうことです。
良く見せたいという気持ちが先行するあまり、企業の本当の姿が反映されていない言葉を選んでしまうと、すぐに見抜かれてしまい、かえって企業の信頼を損なうことになります。
トップダウン文化なのに「ボトムアップで挑戦できる」と謳うなど、実態とかけ離れた魅力を伝えると、入社後のギャップから求職者に強い不信感を与えてしまうので注意が必要です。
これは内定辞退や早期離職の直接的な原因となり、企業の評判を落とすことにもなりかねません。
採用コンセプトは、必ず企業理念やビジョン、そして現場のリアルな実態に基づいた、等身大の言葉でなければなりません。
ターゲット不在でメッセージが散漫になる
「誰に」届けたいのかというターゲットが曖昧なままコンセプトを作ってしまうと、「すべての人」に向けた当たり障りのないメッセージになり、結果的に誰にも深く届きません。
「成長意欲のある方」といった、どの企業でも言えるような漠然とした人物像では他社との差別化は不可能です。
重要なのは、ペルソナ設定を丁寧に行い、価値観や「仕事で何を実現したいか」まで深く掘り下げて人物像を鮮明にすることです。
届けたい相手を「たった一人」に絞り込むくらいの覚悟でターゲットを明確にすることで、初めてメッセージの訴求力が高まり、多くの共感者を生む成功の鍵となります。
社内浸透不足で形骸化する
せっかく素晴らしいコンセプトを作っても、社内に浸透せず、採用担当者だけが知っている「お題目」になってしまっては意味がありません。
面接官によって言うことが違ったり、現場社員がコンセプトを理解していなかったりすると、求職者に不信感を与えてしまいます。
コンセプトは、作って終わりではなく、社内に浸透させて初めて価値を持ちます。
定例会議で繰り返し伝えたり、評価制度にコンセプトを反映させたりするなど、社員が日常的にコンセプトに触れる機会を設けることが不可欠です。
全社を巻き込み、一丸となってコンセプトを体現していく姿勢が、採用成功の鍵を握ります。
採用コンセプトに関してよくある質問
ここでは、採用コンセプトに関して人事担当者の方からよくいただく質問にお答えします。
疑問点を解消し、より深く理解を深めることで、コンセプト設計をスムーズに進めましょう。
採用ブランディングとの違いは?
採用ブランディングとの違いは、採用コンセプトが採用活動の核となるメッセージであるのに対し、採用ブランディングは企業全体の魅力を伝える活動全般を指す点です。
採用コンセプトはすべての採用コミュニケーションの軸となる一言のメッセージです。
一方、採用ブランディングはそのコンセプトを基に、候補者に自社の魅力や価値を一貫して伝えていく取り組み全般を指します。
言い換えれば、採用コンセプトが土台となる核の言葉であり、採用ブランディングはその言葉を活かして企業の採用力を高めるための戦略です。
両者は密接に関係しており、明確なコンセプトがあることで効果的なブランディング施策を展開できます。
作った後の運用方法は?
採用サイト、求人票、説明会資料、面接、SNS投稿など、求職者とのあらゆる接点で一貫して使用し続けることが重要です。
コンセプトは金庫にしまっておくものではなく、常に活用してこそ意味があります。
具体的には、求人票のキャッチコピーや仕事内容の説明文にコンセプトを反映させたり、会社説明会の冒頭でコンセプトに込めた想いを社長や人事責任者が熱く語ったりすることです。
また、面接の質問項目もコンセプトに基づいて設計し、「自社が求める人物像に合致するか」を見極める客観的な基準とします。
社外への発信と同時に、社内報やイントラネットで定期的にコンセプトに触れ、社員の意識を高め続けることも、非常に大切な運用方法です。
外部パートナーへ依頼すべき?
外部パートナーに依頼するかどうかは、自社のリソースと専門性次第です。
採用コンセプトは自社の理解が不可欠なため、可能であれば自社内で策定することが望ましいです。
自社で検討する過程そのものが、本当の自社らしさを再発見する貴重な機会にもなります。
一方、社内にノウハウがなかったり客観的な視点が欲しい場合には、外部の採用コンサルタントやコピーライターに協力を依頼する方法もあります。
ただし外部任せにしすぎると自社らしさが薄まる恐れがあるため、最終決定には自社も深く関与しましょう。
コンセプト変更のタイミングは?
事業内容の大きな変化、経営方針の転換、求める人材像が明確に変わったタイミングなどが、コンセプトを見直すべき時期です。
採用コンセプトは一度作ったら永遠に不変というわけではありません。
企業の成長ステージ(創業期、成長期、安定期など)や、市場環境の激しい変化によって、企業が求める人材の要件や、求職者に打ち出すべき魅力も変わっていきます。
例えば、スタートアップ期から成熟期に移行した際には、「0→1を生み出す創造者」から「既存事業を10→100に拡大させる推進者」へと、求める人材像が変わるかもしれません。
定期的に採用活動の成果(応募者の質、採用決定者のパフォーマンスなど)を振り返り、コンセプトとの間にズレがないかを検証し、必要であれば柔軟に見直していくことが重要です。
採用コンセプトのまとめ
本記事では、採用コンセプトの重要性から具体的な作り方、そして失敗しないためのポイントまでを網羅的に解説しました。
採用コンセプトとは、「自社がどんな人材を、なぜ採用するのか」を明確にし、採用活動全体の軸となる考え方です。
優れた採用コンセプトは、応募率の向上やミスマッチの防止といった直接的な効果だけでなく、社内の意識統一や企業ブランドの向上にも繋がります。
作成にあたっては、現状分析からペルソナ設定、企業らしさの言語化というステップを丁寧に行い、企業の理念からブレない、ターゲットに響くメッセージを練り上げることが重要です。
採用活動がうまくいかないと感じているなら、それは個々の施策の問題ではなく、活動の根幹となるコンセプトが定まっていないからかもしれません。
この記事を参考に、ぜひ貴社ならではの採用コンセプトを設計し、採用活動を成功へと導いてください。