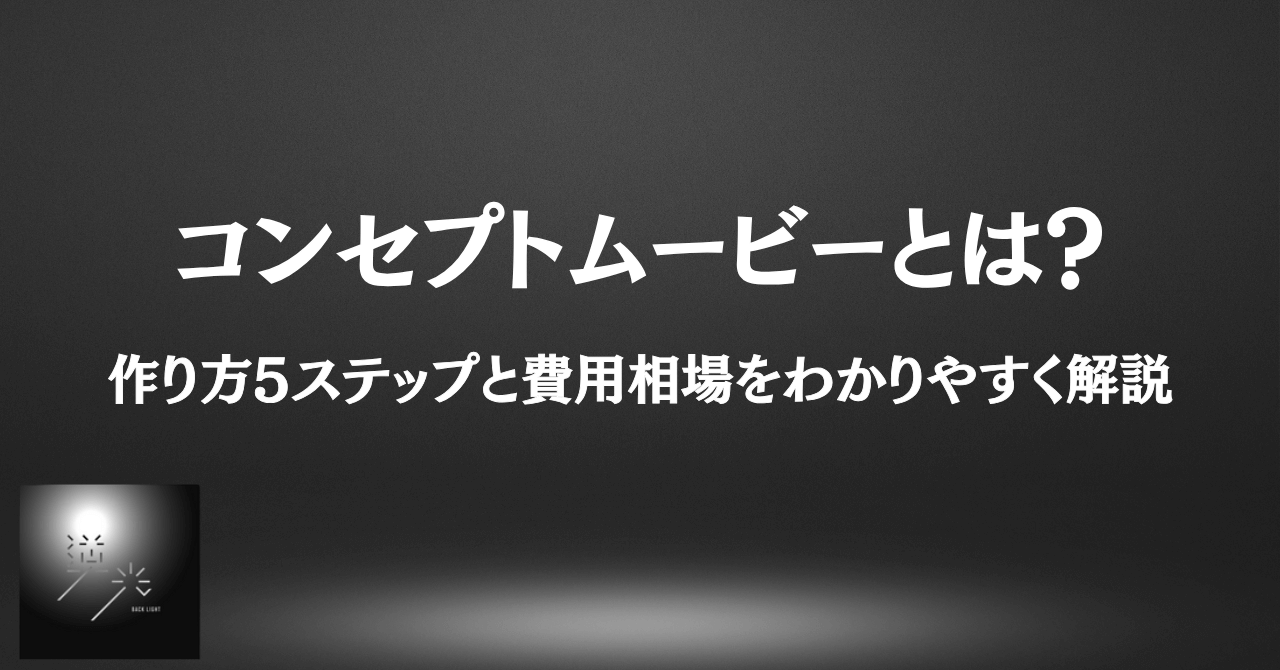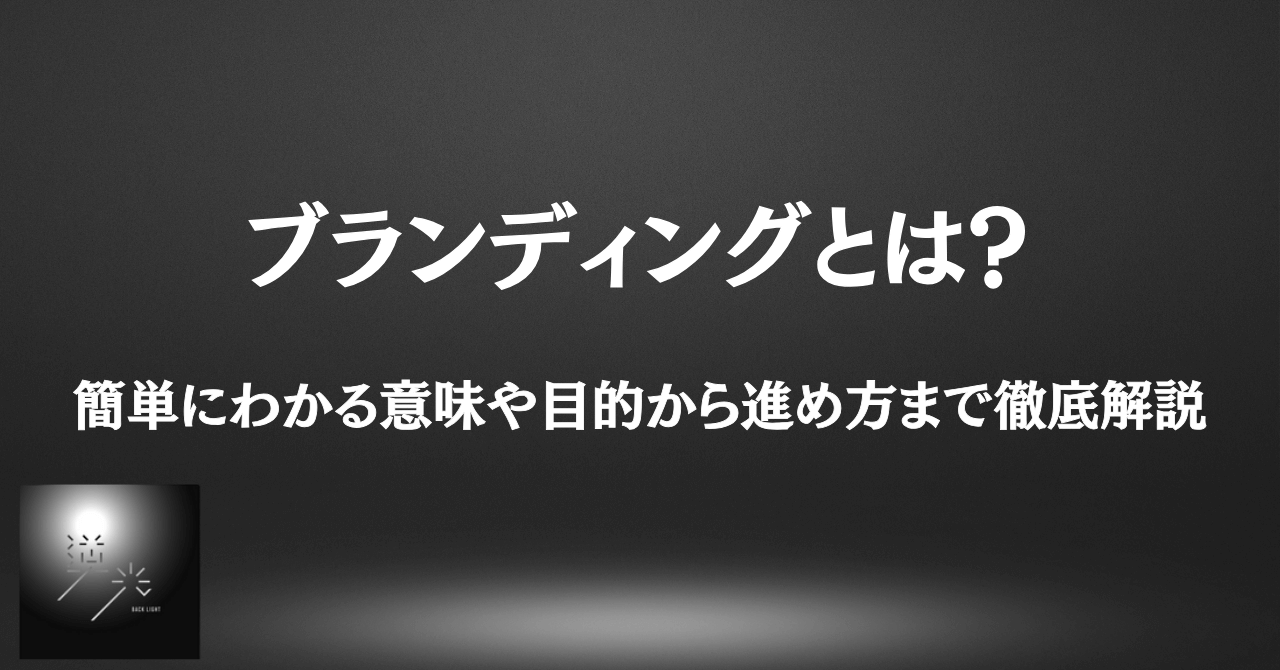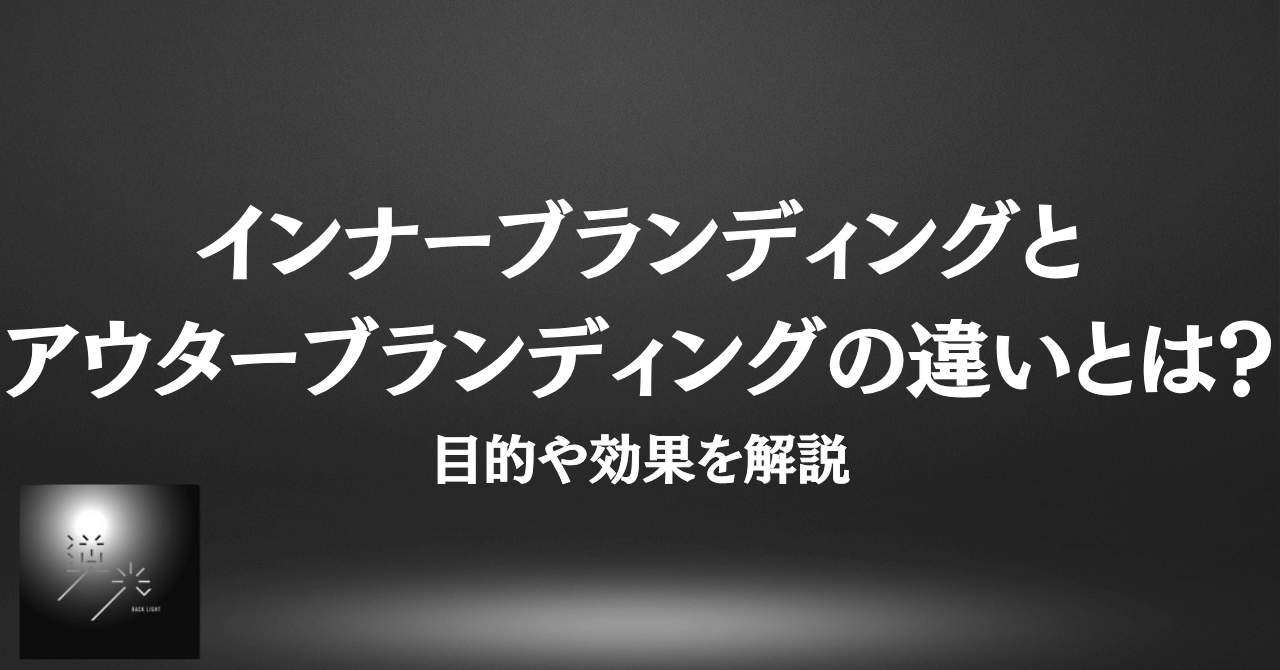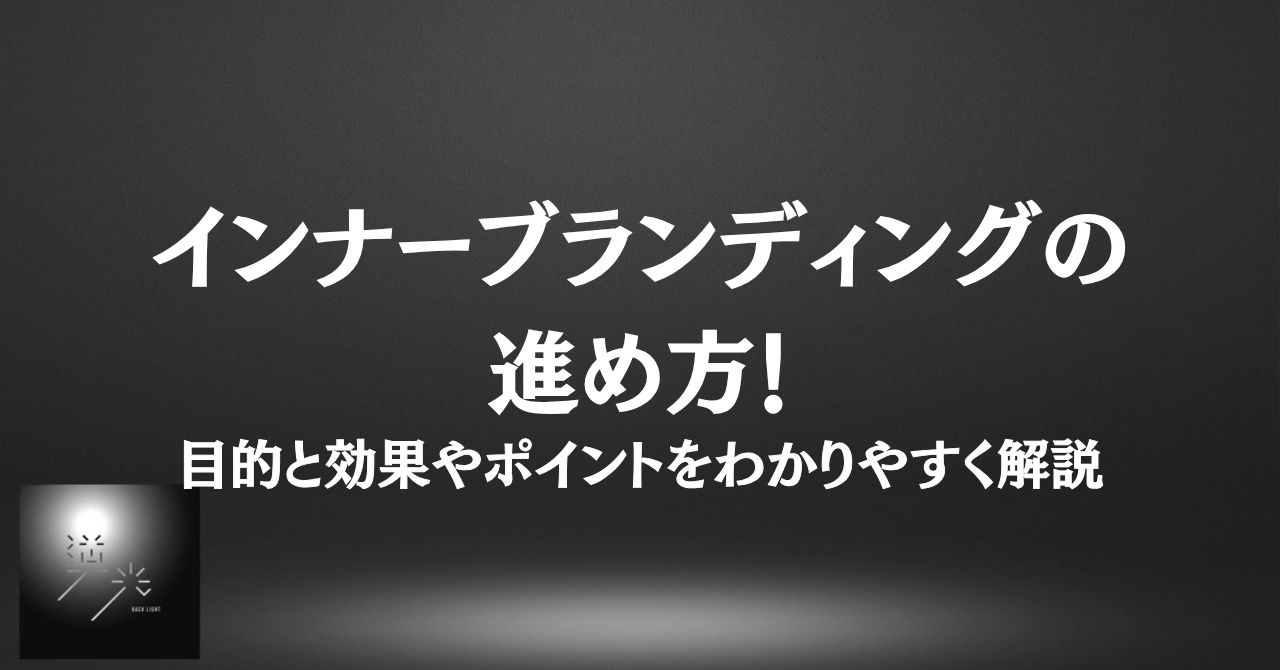「自社の魅力が、いまひとつ伝わりきらない…」。
そんな悩みを抱えていませんか。
Webサイトや資料だけでは表現しきれない、製品に込めた情熱や企業の理念。
その熱量を的確に届け、顧客や求職者の心を動かす答えが「コンセプトムービー」です。
単なる説明ではなく、貴社の物語を伝えることで深い共感と信頼を育みます。
本記事では、作り方から費用相場、成功事例までを網羅的に解説していきます。
>>企業のすべてを魅力化するブランディングの相談をしてみる
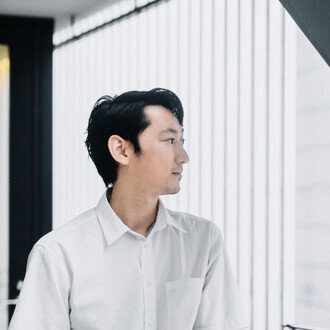
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
INDEX
コンセプトムービーとは?
コンセプトムービーとは、企業や商品、サービスが持つ根源的な「概念(コンセプト)」を、ストーリー性のある映像で表現する動画のことです。
単なる機能の紹介に留まらず、その背景にある想いやビジョン、世界観を伝えることで、視聴者の感情に訴えかけ、深い共感やブランドへの愛着を醸成することを主な目的とします。
創業者がどのような想いで事業を立ち上げたのか、といったエモーショナルな物語を通じて、視聴者はその企業やブランドをより身近に感じ、ファンになっていきます。
Webサイトのトップページや会社説明会、展示会など、企業の顔となる様々な場面で活用され、ブランドイメージを統一し、メッセージの浸透を加速させる強力なツールです。
ブランディング全般についてはこちらで詳しく解説しています。
→ブランディングとは?簡単にわかる意味や目的から進め方まで徹底解説
コンセプトムービーのメリット3選
コンセプトムービーを制作することで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。
ここでは、企業がコンセプトムービーを活用することで得られる3つの主要なメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。
感情移入を誘発しブランド好意度を向上
最大のメリットは、視聴者の感情に直接訴えかけ、ブランドへの好意度を劇的に向上させる点です。
製品のスペックや価格といった情報だけでは、他社との差別化が難しく、顧客の記憶に残りません。
コンセプトムービーを通じて、企業の描く未来や社会への貢献といったビジョン、開発者の情熱といったストーリーに触れることで、視聴者は登場人物に自分を重ね感情移入します。
この共感こそが、「この会社を応援したい」「この製品を使ってみたい」という強い動機付けとなり、価格競争から一線を画した、強固なブランドロイヤリティの構築に繋がるのです。
結果として、単なる顧客ではなく、ブランドを愛し、共に育ててくれる「ファン」を獲得することが可能になります。
ブランディング動画全般の効果についてはこちらで詳しく解説しています。
→ブランディング動画のメリットと成功事例!活用方法や制作ポイントを徹底解説
社内外コミュニケーションの統一軸になる
コンセプトムービーは社外向けだけでなく、インナーブランディングにも絶大な効果を発揮します。
文章では抽象的で浸透しにくい理念やビジョンを、誰もが直感的に理解できる映像で共有することが可能です。
これにより全社員のベクトルを一つに揃え、「目指す未来」という共通認識を育みます。
結果として、日々の業務へのモチベーションや組織への帰属意識が高まるのです。
さらに、社員一人ひとりが自社の「伝道師」となり、一貫性のあるメッセージを発信するため、企業全体のブランド力を底上げする重要な基盤が築かれます。
社内外コミュニケーションの詳細についてはこちらをご参照ください。
→インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは?目的や効果を解説
採用・営業・IRへ横展開できる長期資産
一度制作したコンセプトムービーは、企業の根幹メッセージを伝えるため、時代を超えて活用できるコストパフォーマンスの高い「資産」とすることが可能です。
その活用シーンは多岐にわたり、採用では企業文化を伝えミスマッチを防ぎ、営業では商談を円滑にする信頼関係を築き、IRでは投資家からの共感を得るツールになります。
このように部署や目的を横断して活用できるため、制作費を遥かに上回る価値を生み出す、企業の永続的な資産となるのです。
採用動画としての活用についてはこちらをご参照ください。
→採用動画の効果とは?最大化するポイントと成功事例3選を完全解説
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
コンセプトムービーの制作フロー5ステップ
ハイクオリティなコンセプトムービーを制作するためには、戦略的なプロセスを踏むことが不可欠です。
ここでは、企画から公開まで、失敗しないための制作フローを5つの具体的なステップに分けて解説します。
コンセプト設計(ターゲットやメッセージ抽出)
制作フローの中で最も重要なのが、このコンセプト設計です。
ここでの設計が、動画全体のクオリティと成果を決定づけます。
まず、「誰に(Target)」「何を伝え(Message)」「どのような行動を促したいのか(Action)」を徹底的に明確化します。
目的(Why)、ターゲット(Who)、伝えたいメッセージ(What)、活用シーン(Where)、公開時期(When)、具体的な表現方法(How)を言語化していくと良いでしょう。
ターゲットの年齢層や価値観、抱えている課題などを深く理解し、どのようなメッセージが彼らの心に響くのかを分析します。
この段階で関係者間の認識を完全にすり合わせておくことで、後の手戻りを防ぎ、一貫性のある動画を制作することが可能です。
この設計図がしっかりしていればいるほど、最終的なアウトプットの精度は高まります。
ブランドコンセプト設計の詳細についてはこちらをご参照ください。
→ブランディングにおけるコンセプトとは?作り方や成功のポイントを紹介
シナリオ&ストーリーボード作成
コンセプトが固まったら、次はその「想い」を具体的な映像の物語に落とし込む作業です。
シナリオ作成では、コンセプト設計で定めたメッセージを、視聴者が感情移入できるストーリーとして構築していきます。
冒頭で視聴者の心を掴む「フック」、共感を呼ぶ「展開」、そしてメッセージが最も伝わる「クライマックス」というように、物語の構成を練り上げます。
そして、シナリオを元に作成するのが「ストーリーボード」です。
これは、映像の各シーンの構図、登場人物の動きや表情、テロップ、ナレーション、BGMなどをコマ割りのイラストで可視化した、映像の設計図です。
ストーリーボードがあることで、撮影前に完成イメージを関係者全員で共有でき、認識のズレを防ぐことができます。
この段階で細部まで作り込むことが、撮影・編集作業の効率を大幅に向上させ、動画のクオリティを保証します。
プリプロダクション(キャスティングやロケハン)
プリプロダクションとは、撮影に入る前の「準備段階」を指し、プロジェクトの成否を分ける重要な工程です。
ストーリーボードで描かれた世界観を、現実の映像として具現化するための具体的な準備を行います。
主な作業内容は以下の通りです。
- キャスティング:企業の顔となる出演者(役者、モデル、あるいは社員)を選定します。
- ロケーションハンティング(ロケハン):撮影場所を探し、許可を取ります。場所の雰囲気や光の入り方などが映像の質を大きく左右する作業です。
- スタッフ編成:監督、カメラマン、照明、音声など、必要な専門スタッフをアサインします。
- 香盤表・スケジュール作成:撮影当日の段取りを分刻みで計画することで、関係者全員がスムーズに動くことが可能です。
- 美術・衣装の準備:映像の世界観に合った小道具や衣装を用意します。
この準備をいかに徹底できるかが、撮影当日のトラブルを減らし、限られた時間と予算の中で最高のパフォーマンスを引き出すための鍵となります。
撮影&編集
続いて撮影(プロダクション)と編集(ポストプロダクション)の工程です。
まず、シナリオに沿って実際に映像素材を撮影します。
カメラマンや音声担当などスタッフを配置し、計画通りに必要なカットをすべて収録します。
撮影が完了したら、収録素材をもとに編集作業で一本の動画に仕上げていくのです。
編集工程では映像カットを適切に繋ぎ、テロップの挿入や色調補正などを行います。
また、BGMや効果音、ナレーションを加えて演出面を強化し、メッセージがより伝わるよう細部を整えます。
必要に応じてアニメーションやCG効果を追加し、情緒に訴える映像表現に磨きをかけるのです。
こうして撮影素材に編集・音響処理を施すことで、コンセプトに沿った魅力的な動画が完成します。
公開&運用(SNS最適化や多尺展開)
高品質な動画が完成しても、それだけでは目的を達成したことにはなりません。
「どのようにしてターゲットに届け、見てもらうか」という公開・運用の戦略が極めて重要です。
まず、動画を公開するプラットフォームを決定します。
自社Webサイトのトップページ、YouTube公式チャンネル、採用サイト、SNS(Facebook,Instagram,Xなど)が主な選択肢となります。
SNSで活用する場合は、各プラットフォームの特性に合わせた最適化が必要です。
例えば、冒頭数秒で惹きつける工夫や、音声なしでも伝わるテロップの活用、スマートフォンの縦型視聴を意識した画角などが挙げられます。
イベントや広告配信用に、オリジナルの動画を短く編集した「多尺展開(15秒版、30秒版など)」を行うことで、活用の幅はさらに広がります。
公開後は、再生回数や視聴維持率などのデータを分析し、効果を測定しながら改善を繰り返していくことが、動画という資産の価値を最大化する上で不可欠です。
コンセプトムービー制作を成功させる3つのテクニック
制作フローを理解した上で、さらに質の高いコンセプトムービーを作るためには、いくつかの実践的なテクニックがあります。
ここでは、競合との差別化を生み、視聴者の心に深く刻まれるコンセプトムービーを制作するための3つの重要なテクニックをご紹介します。
リフレーミングで視点を変える
効果的なコンセプトムービーには「リフレーミング」という手法が有効です。
リフレーミングとは、同じ事象を異なる視点や枠組みで捉え直すことを指します。
例としては、ある家具メーカーが自社製品を単なる「椅子」ではなく「家族の会話が生まれる場所」とリフレーミングしたことで、機能性だけでなく情緒的価値を訴求し、大きな反響を得ました。
自社のサービスや製品を、ユーザーのニーズや時代背景に合わせてどう再定義できるかが、競合との差別化を生む強力な武器になります。
情報を削ぎ落としてメッセージを研ぎ澄ます
コンセプトムービーで最も重要なのは、伝えたいコンセプトを明確にするために、不要な言葉や情報を削ぎ落として凝縮することです。
動画で伝えられる情報には限りがあり、情報量が多ければ多いほど、メッセージの核心がぼやけてしまいます。
企業やブランドが本当に伝えたい核となる情報だけを抽出し、それを映像・音楽・ナレーションで表現することで、視聴者の記憶に強く残るコンセプトムービーが完成します。
「あれもこれも伝えたい」という欲を捨て、一つの明確なメッセージに絞り込む勇気が、共感を生むコンセプトムービーの秘訣です。
縦型動画とサウンドデザイン
近年のコンセプトムービー制作では、視聴環境の変化に対応した工夫が求められています。
TikTokやInstagram Reels、YouTube Shortsなど、スマートフォンでの縦型視聴が主流になった今、従来の横型動画だけでなく9:16の縦型フォーマットも想定した構成が必要です。
特にSNSでは冒頭3秒で約70%のユーザーが視聴を継続するか判断するというデータもあり、最初の数秒でユーザーを惹きつける工夫が極めて重要です。
セーフティゾーン(重要な情報が画面端で切れないエリア)の設計や、縦型視聴に最適化されたテロップ配置など、SNS特有の視聴習慣を意識した設計が求められます。
またサウンドデザインへのこだわりも重要度が増しており、BGM、効果音、ナレーションのトーンは、映像と同等かそれ以上にブランドの世界観を左右します。
視覚と聴覚の両面から「らしさ」を設計することで、視聴者の記憶に深く刻まれるコンセプトムービーが完成するのです。
コンセプトムービー費用相場と予算シミュレーション
コンセプトムービーの制作を検討する上で、最も気になるのが費用ではないでしょうか。
ここでは、費用の内訳から価格帯によるクオリティの違い、そして見積もりを取る際の注意点まで、具体的かつ実践的な情報を提供します。
コンセプト設計~撮影までの内訳
コンセプトムービー制作費用の主な内訳は、「企画(コンセプト設計)」「撮影」「編集・仕上げ」の3つの工程に分類できます。
それぞれの工程で必要となる作業と費用の目安は以下のとおりです。
| 企画費用 (コンセプト設計・構成) | プロデューサーやディレクターによる企画立案・台本作成などの費用。 相場は約10~50万円程度 プロデューサー費5~10万円 ディレクター費5~25万円 台本作成費3~15万円前後 |
| 撮影費用 | 実写映像を撮影する工程にかかる費用。 撮影規模によりますが合計で約10~100万円が目安です。 撮影クルーの人件費 撮影機材レンタル費 ロケハン費 キャスティング費 スタジオ費 交通宿泊費など |
| 編集・仕上げ費用 | 撮影素材の編集・加工や音入れにかかる費用。 相場は約5~100万円と幅があり、内容によって変動します。 動画編集費 BGM・効果音追加 ナレーション録音 グラフィック制作 最終書き出し作業など |
以上を合計したコンセプトムービー1本あたりの制作費用相場は概ね数10万円~数100万円規模になります。
例えば、インタビュー中心のシンプルな構成なら数十万円で済むケースもありますが、本格的なドラマ仕立てで凝った演出にする場合は撮影日数やスタッフも増えるため100~200万円程度かかることも珍しくありません。
自社のニーズに合わせて、どの工程に重点を置くかを検討しましょう。
10万~400万円:コストを左右する要因
コンセプトムービーの費用相場は、一般的に数十万円から数百万円と幅広く、クオリティや内容によって大きく変動します。
低価格帯の10万円~50万円では、撮影を1日に限定し、社員が出演、編集もシンプルな構成になることが多いです。
本格的なクオリティを求める場合、100万円~400万円以上が目安となります。
プロの役者をキャスティングしたり、複数日にわたる地方ロケを行ったり、CGやアニメーションを多用したりすると費用は上昇します。
特に、撮影日数、スタッフの人数、使用機材のグレード、キャスティング、ロケ地の数などがコストを左右する主な要因です。
どこまでこだわるか、目的と予算のバランスを制作会社と相談しながら決めていくことが重要です。
見積もりチェックポイント7項目
複数の制作会社から見積もりを取る際は、金額の安さだけで判断せず、内容を精査することが失敗を防ぐ鍵です。
以下の7つのポイントを必ず確認しましょう。
- 作業範囲は明確か:企画、撮影、編集、修正など、どこからどこまでが含まれているか。修正回数に上限はあるか。
- 各項目の内訳は詳細か:「一式」という表記が多くないか。人件費や機材費などの内訳が具体的に記載されているか。
- 追加費用の可能性は記載されているか:どのような場合に別途費用が発生するのか(例:修正回数の超過、撮影の延長など)が明記されているか。
- 権利関係はクリアか:制作した動画の著作権はどちらに帰属するのか。二次利用(多尺展開や別媒体での使用)に追加料金は発生しないか。
- BGMや素材のライセンスは問題ないか:使用する音楽や映像素材が、商用利用可能なライセンスをクリアしているか。
- 担当者の実績やスキルは十分か:見積もりを作成した担当者や、実際の制作を担当するディレクターの実績が豊富か。
- 納期とスケジュールは現実的か:提示されたスケジュールに無理がないか。各工程の所要時間が明記されているか。
これらの点を細かくチェックし、不明な点は必ず事前に質問することで、後々のトラブルを防ぎ、安心して制作を任せることができます。
コンセプトムービー制作に失敗しない制作会社の選び方
コンセプトムービーの成否は、パートナーとなる制作会社選びで9割決まると言っても過言ではありません。
自社の想いを正確に汲み取り、期待を超えるクリエイティブを提供してくれる会社を見極めるための3つの視点をご紹介します。
実績ジャンルとKPI提案力
まず確認すべきは、その制作会社が持つ過去の実績です。
特に、自社と同じ業界や、類似した課題を持つ企業のコンセプトムービーを手がけた経験があるかは重要な判断材料になります。
業界特有の文脈やターゲットのインサイトを理解している会社であれば、より的確で効果的な企画を期待できます。
さらに、単に「良い動画を作る」だけでなく、「成果に繋がる動画を作る」という視点を持っているかも重要です。
「Webサイトの問い合わせ数を〇件増やしましょう」のように、動画制作の目的(KGI)と、達成するための具体的な成果指標(KPI)をセットで提案してくれる会社は信頼できます。
制作前のヒアリングで、自社のビジネス課題について深く質問してくる会社は、成果へのコミットメントが高いと言えるでしょう。
企画提案の具体度
複数の会社を比較検討する際は、企画提案の具体度を注意深く見てください。
こちらの要望をただ受け入れるだけでなく、プロの視点からプラスアルファの提案をしてくれるかどうかが腕の見せ所です。
優れた制作会社は、ヒアリングした内容を元に、「弊社のターゲットには、このようなストーリーが響くのではないでしょうか」といった、具体的で創造的な提案をしてくれます。
その提案に、自社の課題解決に繋がるロジックと、心を動かすクリエイティビティの両方が感じられるかを見極めましょう。
ストーリーボードや参考映像などを用いて、完成イメージが具体的に共有される提案は、制作後の「思っていたのと違う」というミスマッチを防ぐ上で非常に有効です。
アフターサポートの有無
動画は公開してからが本当のスタートです。
そのため、制作後のアフターサポートが充実しているかどうかも、長期的なパートナーシップを築く上で重要なポイントとなります。
具体的には、以下のようなサポートが提供されるかを確認しましょう。
- 効果測定とレポーティング:YouTubeアナリティクスなどを活用し、公開後の視聴データを分析・報告してくれるか。
- 改善提案:データに基づいて、動画の改善点や次の施策を提案してくれるか。
- 多用途展開のサポート:SNS用の短尺動画への編集や、展示会用のループ動画作成などに柔軟に対応してくれるか。
- 動画広告の運用代行:必要に応じて、YouTube広告などの運用を任せられるか。
作って終わりの関係ではなく、動画活用の成果を最大化するために、共に走り続けてくれるパートナーを選ぶことが、コンセプトムービーの成功に不可欠です。
コンセプトムービーは自社制作vs外注どちらが向いている?
動画制作のツールが身近になった今、「内製(自社制作)」か「外注」かで悩む企業も多いでしょう。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に最適な選択をすることが重要です。
内製に適したケース
内製は、コストを抑えられ、スピーディに制作できる点が最大のメリットです。
以下のようなケースでは、内製が適していると言えるでしょう。
- 予算が限られている場合:外注費用をかけずに制作したい。
- 求めるクオリティがそこまで高くない場合:まずはテスト的に動画を作ってみたい、社内向けの簡単な動画で十分、といった場合。
- 社内に専門知識を持つ人材がいる場合:動画制作の経験がある、あるいはデザインやマーケティングのスキルを持つ社員がいる。
- 頻繁に動画を制作・更新したい場合:多くの本数をスピーディに発信したいSNS運用など。
- 機密性が非常に高い情報を扱う場合:社外に情報を出したくないプロジェクト。
ただし、企画から編集まで全ての工程を自社で行うには、相応の知識と時間、そして専用の機材やソフトが必要です。
クオリティが低いために、かえってブランドイメージを損なうリスクがあることも理解しておく必要があります。
ハイブリッド型のメリット
「内製」と「外注」のどちらか一方を選ぶのではなく、両方の良い部分を組み合わせる「ハイブリッド型」も有効な選択肢です。
これは、自社の強みを活かしつつ、専門性が求められる部分だけをプロに任せるという考え方です。
例えば、
- 企画やシナリオ作成は自社で行い、撮影と編集だけを外注する。
- 撮影は自社で行い、高度な編集やアニメーション制作だけを外注する。
このようなハイブリッド型にすることで、コストを抑えながらも動画のクオリティを担保できます。
また、制作会社との協業を通じて、社内に動画制作のノウハウを蓄積できるというメリットもあります。
どこまでを自社で担当し、どこからをプロに任せるか、自社のリソースと動画の目的を照らし合わせて検討してみましょう。
外注で失敗しない発注書テンプレート
外注に出す場合は、事前準備として発注内容を的確に伝えることが成功の鍵です。
制作会社に共有する発注書(制作ブリーフ)には、以下の項目を盛り込むとスムーズです。
- 動画の目的・KPI:何を達成したい動画か(例:「採用応募数増加」「ブランド認知向上」など)を明記。評価指標もあれば指定。
- ターゲット層:想定視聴者の属性やペルソナ。誰に響く動画にしたいのかを具体的に。
- 訴求したいメッセージ:動画を通じて最も伝えたいキーワードやストーリーの概要。企業のコンセプトや商品価値など核心部分を記載。
- 動画の尺と形式:希望する動画の長さ(例:90秒程度)や画面比率、実写かアニメか等の形式的要件。
- 参考動画・イメージ:イメージに近い他社の動画や過去のCM等があればURL共有し、演出トーンの参考にしてもらう。
- 納期・スケジュール:完成希望日や公開予定日、それまでの中間チェック日程など。余裕のない場合はその旨伝える。
- 予算目安:大まかな予算レンジ。伝えておけば、その範囲でできる企画提案を受けやすくなります。
このような情報を盛り込んだ発注書テンプレートを用意して制作会社に渡せば、相手も要件を正確に把握できミスマッチの少ない提案・見積もりが期待できます。
特に、コンセプトムービーは抽象的な表現が多いため、発注側の意図を可能な限り言語化して共有することが大切です。
テンプレートを活用し、お互いの認識を擦り合わせた上でプロジェクトをスタートさせましょう。
コンセプトムービーに関してよくある質問
コンセプトムービーの制作を検討する上で、多くの方が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。
コンセプトムービーの効果は?
視聴者の共感を生みファン化につなげる効果があります。
コンセプトムービーは企業の理念や物語を伝えることで感情移入を誘発し、ブランドへの好感度や信頼感を高めます。
その結果、商品やサービスの購入、採用応募など視聴者のアクションにつながりやすくなるのです。
また差別化要素を打ち出すことで競合との差異を印象付ける効果や、社内向けに一体感を醸成する効果も期待できます。
制作費はいくらかかりますか?
制作費は、クオリティや内容によって10万円程度から400万円以上と大きな幅があります。
一般的な相場としては、プロの制作会社に依頼する場合、50万円~200万円の価格帯で制作されることが多いです。
費用は、企画の内容、撮影日数、出演者の有無、アニメーションのクオリティなどによって変動します。
複数の会社から見積もりを取り、内容を比較検討することが重要です。
動画の最適な尺は?
活用シーンによって最適尺は異なりますが、Webで公開する場合は「90秒~3分程度」が一般的です。
長すぎると視聴者が途中で離脱してしまうリスクがあります。
一方で、SNS広告などで使用する場合は、最初の数秒で心を掴む必要があるため「15秒~30秒」の短尺動画が効果的です。
伝えたいメッセージの量と、視聴される媒体の特性を考慮して、最適な長さを決定することが重要です。
ブランドムービーとの違いは?
コンセプトムービーとブランドムービーは、ほぼ同義で使われることが多いですが、厳密には伝える対象の範囲に違いがあります。
コンセプトムービーは、特定の事業や商品、プロジェクトの「概念」に焦点を当てることが多いです。
ブランドムービーは、企業全体の「ブランド哲学」や世界観といった、より広範で包括的なテーマを扱う傾向があります。
しかし、どちらも企業の根幹にある想いを伝えるという目的は共通しており、明確な使い分けの定義はありません。
コンセプトムービーとCMの違いは?
CMは商品購入を直接促す広告、コンセプトムービーは企業の想いや世界観を伝えるコンテンツです。
CMは15〜30秒の短尺で、広告枠を購入してテレビやWebで配信し「買ってください」というメッセージを発信します。
一方コンセプトムービーは90秒〜3分程度の尺で、企業理念やブランドストーリーを丁寧に伝え、視聴者の共感を通じて長期的な関係構築を目指します。
目的も配信方法も異なるため、自社が何を達成したいのかを明確にした上で、適切な動画形式を選ぶことが重要です。
コンセプトムービーのまとめ
本記事では、コンセプトムービーの概要からメリット、具体的な制作フロー、費用相場、そして成功するための制作会社の選び方までを網羅的に解説しました。
コンセプトムービーとは、企業やブランドの根幹にある理念や価値観を物語として描き、視聴者の深い共感を生むための映像です。
その効果は、ブランド好意度の向上、社内外コミュニケーションの円滑化、そして採用や営業など多方面で活用できる長期的な資産となる点にあります。
制作は「コンセプト設計」「シナリオ作成」「プリプロダクション」「撮影・編集」「公開・運用」という5つのステップで進められ、費用は内容により数十万から数百万と変動します。
成功の鍵は、実績豊富で、自社の課題に寄り添った具体的な企画提案をしてくれる信頼できるパートナー企業を見つけることです。
この情報が、貴社の想いを形にし、ブランド価値を飛躍させる一助となれば幸いです。