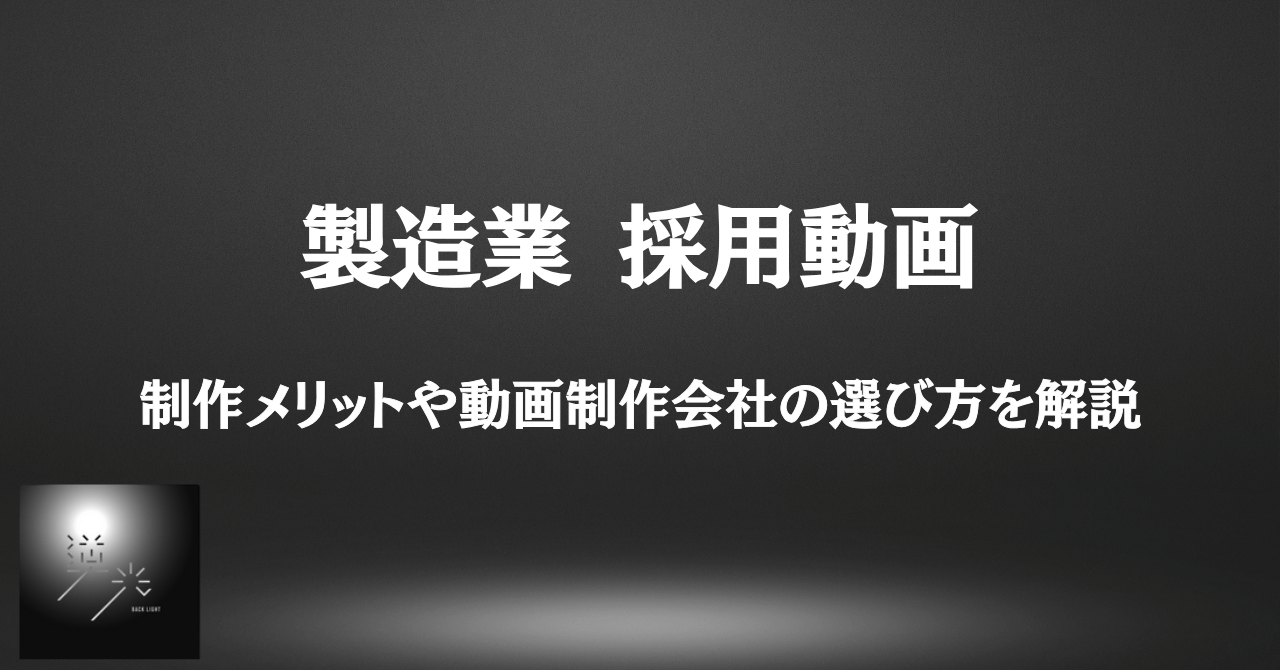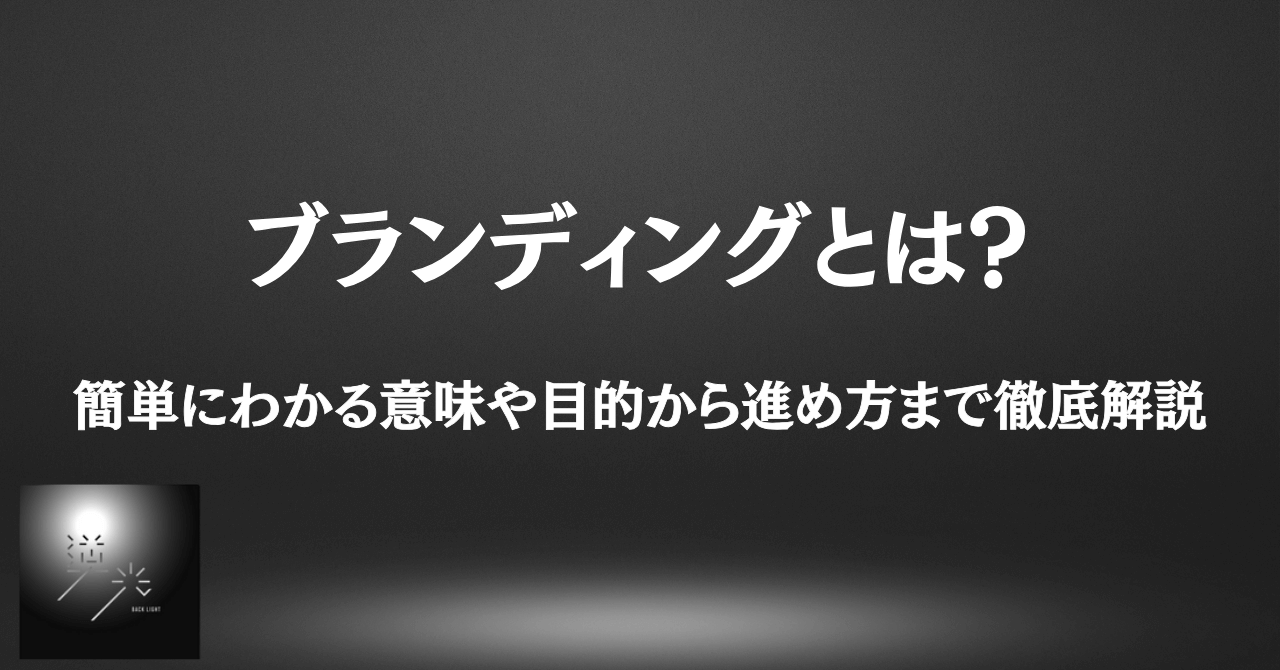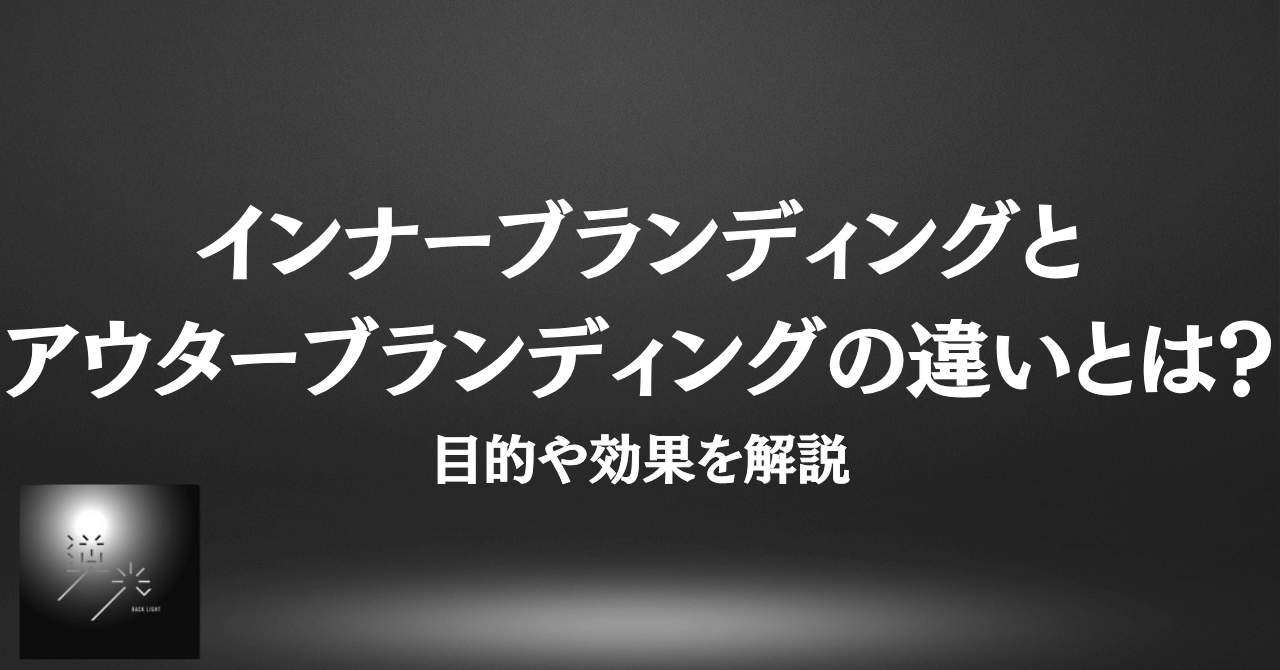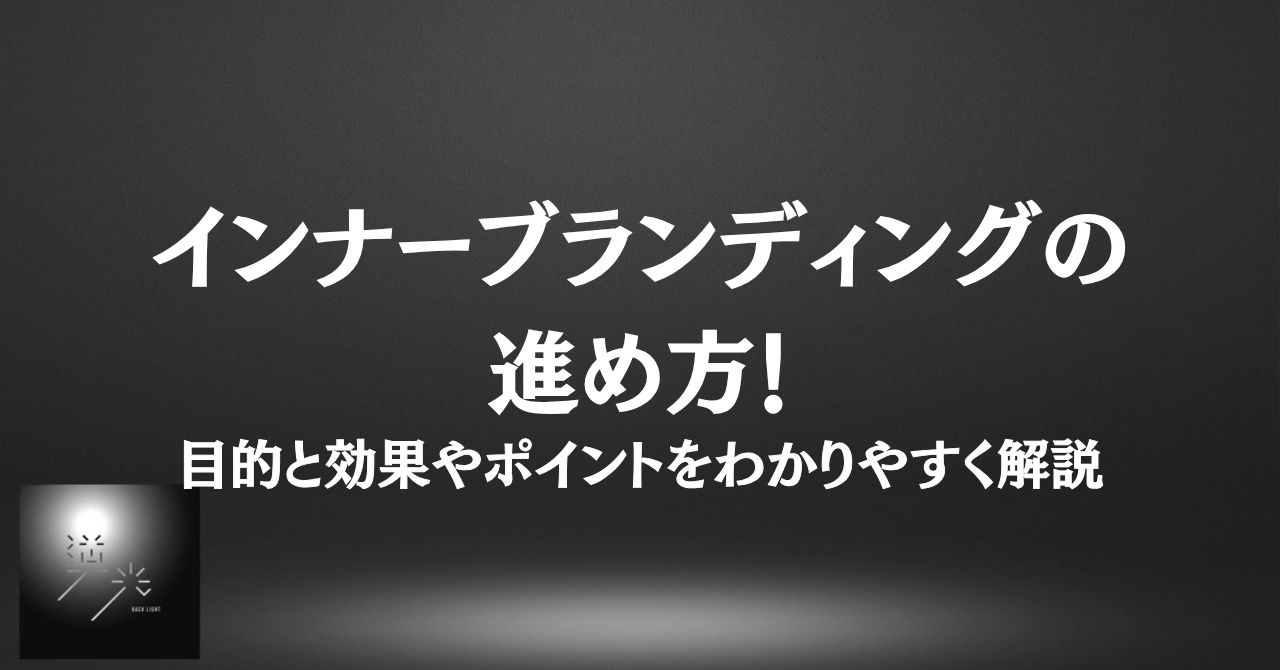製造業での採用活動において、思うような人材確保が難しいと感じていませんか?
「求人を出しても応募が集まらない」「応募者と実際の業務内容とのギャップが埋まらない」といった課題を抱える企業は少なくありません。
こうした課題を解消し、優秀な人材を惹きつけるために効果的なのが採用動画の活用です。
動画を使うことで、会社の魅力や現場のリアルをわかりやすく伝えられ、応募者の興味をぐっと高めることができます。
今回は、製造業向けの採用動画制作のメリットや事例、そして制作会社の選び方について解説します。
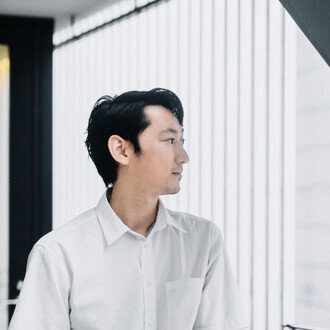
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
INDEX
採用戦略の成功事例や基本を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。
→採用戦略の成功事例!フレームワークを活用した作り方や戦略の立て方を分かりやすく徹底解説!
製造業で採用動画を制作するメリット4選
まずは製造業が採用動画を導入することで得られるメリットを理解することが重要です。
以下の4つのポイントを押さえることで、動画制作に取り組む意義や期待できる効果をより深く実感できるはずです。
短時間で企業理解を深められる
製造業の現場は製品の種類や工程も多岐にわたり、文章や写真だけでは伝わりにくい部分が多くあります。
しかし、動画であれば、製品が出来上がる過程や職場の雰囲気をリアルに映し出せるため、短時間でも企業への理解を深めることが可能です。
これにより、採用動画を視聴した求職者は「どんな製造現場か」「仕事のイメージはどうか」を具体的に把握しやすくなります。
加えて、視覚と聴覚に訴求できることで記憶にも残りやすく、情報発信の効率が高まるでしょう。
現場のリアルを伝えてミスマッチを防げる
採用後のミスマッチは企業・求職者双方にとって大きな負担です。
特に、製造業の場合、騒音がある、作業服着用が必須、また立ち仕事が多いなど、現場特有の環境を事前に理解してもらうことが重要となります。
そこで、動画を使い、実際の作業場面や社員の声を映し出すことで「この会社は自分に合っていそうだ」「想像より作業が大変そうだがやりがいを感じる」といった判断を求職者側が正確に行いやすくなります。
結果として、企業側の早期離職リスク軽減につながり、定着率もアップするのです。
オンライン選考時代の訴求力強化できる
近年、オンライン面接や説明会の導入が急速に進み、求職者との直接コミュニケーションの機会が限られるようになっています。
このような環境下では、動画を活用することで従来の会社説明会のような熱量や雰囲気をデジタル上でも伝えやすくなるのが大きな利点です。
求職者としても、時間や場所を選ばずに会社の雰囲気を知ることができるため、オンライン選考でも企業理解を深めやすくなります。
結果的に「どんな現場かイメージがつかめない」という不安を解消でき、応募意欲の向上につながるでしょう。
採用コスト削減と応募率向上
製造業は大量採用や定期採用が必要となるケースが多く、人材紹介会社や求人広告へのコストがかさむことがしばしばあります。
そこで、採用動画を効果的に運用すると、企業の魅力を短期間で多くの候補者に伝えられるため、求人広告費の削減や面接回数の軽減などが期待できます。
また、動画による企業ブランディングが成功すると応募率が高まり、より自社にマッチした人材の応募につながりやすくなるのです。
結果として、効率的かつ質の高い採用活動の実現が期待できます。
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用動画の効果をさらに高めたい方は、活用方法をまとめたこちらの記事も参考になります。
→ 【採用動画の効果とは?最大化するポイントと成功事例3選を完全解説】
製造業の採用動画の種類とトレンド
次に、製造業で多く採用されている動画の種類と、最近注目されている表現手法を押さえましょう。
複数のフォーマットを知っておくことで、自社の採用コンセプトや伝えたいイメージにあった動画を制作しやすくなります。
企業・事業紹介動画
製造業では企業の歴史や製品・サービス内容を総合的にアピールする「企業・事業紹介動画」が定番です。
特に、創業の背景や企業の成り立ち、どんな市場で勝負しているのかといった点を映像化することで、求職者に企業の理念やビジョンを深く理解してもらいやすくなります。
また、トップメッセージを交えることで、経営者の考えや組織風土をより直接的に伝えることも可能です。
こうした包括的な動画はウェブサイトのトップページや会社説明会など、さまざまな場面で汎用性が高い点が特徴といえるでしょう。
工場ツアー/生産ライン紹介
製造業ならではの強みを一番わかりやすく伝えられるのが、現場の工場ツアー動画や生産ライン紹介です。
普段は立ち入りが難しいエリアまで撮影することで、製品が作られる様子やこだわりの品質管理体制をリアルに示すことができます。
また、工場施設の規模や最新設備の有無など、他社と差別化できるポイントをビジュアルでアピールできるため「こんなハイテクな環境で働けるのか」と求職者の興味を大きく引き出せるでしょう。
同時に、安全対策や作業環境の清潔さを示すことで、働く安心感を与えられるのもポイントです。
社員インタビュー・一日密着
採用動画で最も人気のある手法が、現役社員の声を取り入れるインタビューや一日密着動画です。
実際に働く社員が「仕事で感じるやりがい」「職場の雰囲気」「組織風土」などを語ることで、求職者との距離感を一気に縮めます。
また、若手社員やベテラン社員、それぞれの視点を混ぜることで、多様なキャリアパスや職場環境をよりリアルに伝えられます。
特に、現場の作業内容を細部まで映す一日密着は、求職者が仕事内容をイメージしやすく、応募動機形成にも大きく寄与するのです。
プロジェクトストーリー/技術開発密着
高度な技術や特別なノウハウを持つ製造業にとっては「プロジェクトストーリー」や「技術開発密着」の動画が効果的です。
具体的には、新製品や画期的な技術開発を追いかけるドキュメンタリータッチの制作が挙げられます。
苦労や試行錯誤のプロセス、メンバー間のチームワークなどを描くことで「チャレンジできる仕事」「研究開発力の高い企業」といった印象を強く打ち出せます。
技術職志望の学生やエンジニアにとっては、より魅力的に映る要素となるでしょう。
アニメーション・インフォグラフィック
文字や写真では一度に伝えきれない複雑な工程やデータを、アニメーションやインフォグラフィックで視覚的に簡潔にまとめる手法も注目されています。
特に、安全管理や生産ラインの流れなどを図解する場合、イラストや動画モーションを用いることで理解度が高まります。
また、製品の仕組みや生産プロセスをわかりやすく視覚化することで、多様なバックグラウンドを持つ求職者への訴求が可能となるでしょう。
さらに、映像表現が洗練されていると企業の先進性やクリエイティビティを感じさせるため、ブランディング効果も大きくなります。
製造業などの採用動画成功事例
実際にどのような採用動画が効果を上げているのか、事例を知ることで自社に取り入れるヒントが得やすくなります。
ここでは福祉事業所や製造業の事例を紹介しますが、企画や演出のポイントは業種を越えて参考になる部分も多いので、ぜひチェックしてみてください。
製造業
上記では、現場スタッフのインタビューを中心に進める構成や、実際の作業風景を映しながら具体的な仕事イメージを伝える手法が特徴的です。
視聴者に「自分が働く姿」を想像させるため、ナビゲーターとなる人物を配置し、カメラ目線で現場を紹介することで親近感を高めています。
また、工場内の臨場感ある撮影を行うことで「製造業=堅苦しい」といったイメージを払拭することにも成功しています。
福祉事業所
「このレベルの動画は、実際いくらで制作できるの?」と気になる方は、
費用相場をまとめた以下の記事をご覧ください。
→ 【採用動画の費用相場と料金の内訳】
製造業で採用動画を制作する流れ6ステップ
採用動画を成功させるには、段取りよく制作工程を把握することが重要です。
以下のステップを押さえることで、スムーズな動画制作と効果的な運用が可能になります。
ステップ1.目的・KPI設計とペルソナ設定
最初に行うべきは「何のために採用動画を作るのか」を明確にし、その効果を測定するためのKPIを設定することです。
応募数やエントリー数を増やしたいのか、より企業理解を高めた上での内定承諾率アップを目指すのかなど、目的によって動画の内容や尺が大きく変わります。
同時に、求める人物像やターゲット層を想定したペルソナ設定も重要です。
理想の人材に適切にアプローチできるよう、年齢層や興味関心、就職活動での重視ポイントなどを具体的に整理しておきましょう。
ステップ2.シナリオ作成と絵コンテ
目的とペルソナが決まったら、次に動画の台本(シナリオ)と絵コンテを作成します。
シナリオでは、メインメッセージをどのシーンで伝えるか、どのような人物が登場するかなど、構成の骨組みを固めます。
その後、絵コンテを用いてカメラアングルやテロップの位置、撮影カットの繋ぎ方などを具体的に可視化していきます。
この段階でしっかりイメージを共有しておくことで、後の撮影や編集をスムーズに進行できるため、制作全体のクオリティを向上させることができます。
ステップ3.撮影準備(安全対策・5S)
製造業特有の工程として、撮影現場での安全対策や整理整頓(5S)を徹底する必要があります。
工場内での撮影ではヘルメットや保護具の着用義務、撮影範囲の制限、危険区域の表示などが求められる場合があります。
また、映像に余計なゴミや資材が映りこまないようにすることも重要です。
撮影前に5Sを徹底し、整理されたクリーンな状態を保つことで、会社の衛生意識や品質管理への真摯さを訴求できます。
4.撮影・編集の現場実務
撮影当日はシナリオと絵コンテに沿ってカットを取りこぼさないよう注意を払いながら進行します。
製造現場ではライン稼働のタイミングやスタッフの動きに合わせて柔軟に撮影スケジュールを調整する必要があるため、現場スタッフと綿密に連携しましょう。
映像素材が揃ったら編集作業に移りますが、企業イメージを伝えるためのBGMやカラースキーム、テロップのデザインなども重要な要素です。
製造業の場合、機械音や作業の臨場感を活かしつつ、見やすさとのバランスを考慮した編集が求められます。
ステップ5.字幕・多言語/アクセシビリティ対応
近年、動画に字幕をつけることは標準的な対応になりつつあります。
社内や海外拠点とのやり取りが多い製造業では、英語や中国語など多言語対応を行うことで、採用候補者の幅をさらに広げることができます。
また、視聴障害者や聴覚障害者の方にも配慮したアクセシビリティ対応を進めることで「人を大切にする企業」という印象を与えられるでしょう。
字幕はテロップと被らないよう配置するなど、視認性を考慮することもポイントです。
ステップ6.公開後の効果測定と改善サイクル
動画を公開して終わりではなく、実際の効果を定量的に把握し、継続的に改善するサイクルを回すことが重要です。
具体的には、動画の視聴回数やエントリー率、内定率の変化などをチェックし、目標未達の場合は要因を分析します。
例えば、「尺が長すぎて最後まで見られていない」「字幕が多言語対応されていないため海外人材の応募が少ない」などの問題点を洗い出し、随時修正していきましょう。
こうしたPDCAを回すことで、採用動画のクオリティと成果を着実に高められます。
製造業の採用に強い動画制作会社の選び方
製造業の採用動画を外注する際は、工場撮影のノウハウや安全基準の理解など、業種特有のポイントを押さえている制作会社を選ぶことがカギとなります。
ここではチェックすべき主な判断基準を紹介します。
製造現場の安全基準への理解
製造業の現場は常に危険要素と隣り合わせであり、安全対策の徹底が求められます。
そのため、撮影スタッフが安全教育を受けているか、機械稼働時の撮影ルールを理解しているかなどを事前に確認することが重要です。
安全面に配慮しないまま撮影を進めると、予期せぬトラブルを招くリスクが高まります。
動画制作会社を選ぶ際は、工場内撮影の実績や安全対策に関するマニュアルの有無を確認し、安心して撮影を依頼できるパートナーを見つけましょう。
BtoB商材の訴求実績
製造業の場合、BtoBでの取引が中心となることが多く、一般消費者向けの動画とは異なる演出や訴求が求められます。
例えば、製品の技術的な強みや品質管理システムなど、専門的な内容をわかりやすくまとめる力が必要です。
また、映像の雰囲気も華やかさより信頼性や専門性を重視したテイストにすることが多いため、過去にBtoB向け動画制作経験がある会社はノウハウを持っています。
制作会社の事例や実績をチェックし、自社の業務領域に近いテーマを扱った経験があるかどうかを確認しましょう。
工場撮影機材・ドローン対応
工場や生産ラインを撮影するには、広角レンズや安定した照明機材、高音に強い録音機材など、専門的な装備が必要な場合があります。
また、大規模な工場全体を俯瞰で撮るためにドローン撮影を行うケースも増えています。
ドローンを使用する際は飛行許可や安全管理が必要となるため、対応実績のある動画制作会社を選ぶと安心です。
機材や技術面で不足があると、撮りたい映像が撮れないだけでなく、安全面のトラブルにもつながる恐れがあります。
マーケティング支援と運用サポート
採用動画を作成しても、掲載する場所やタイミング、広告配信のノウハウがなければ思うような効果は出にくいものです。
動画制作会社の中には、マーケティング支援や運用サポートまで行う総合型のサービスを提供しているところがあります。
制作した動画を自社サイトやSNS、求人媒体などでどのように露出していくか、どのように効果測定を行うかなどをトータルで相談できる会社を選ぶと、スムーズに成果を上げやすいでしょう。
製造業の採用動画に関てよくある質問
最後に、製造業向けの採用動画を導入する際によくある疑問点をまとめました。
疑問や不安を解消することで、導入へのハードルを下げ、効果的な活用に繋げてください。
最適な動画尺は何分?
結論としては、1~3分程度の短尺がおすすめです。
特に、スマホで視聴されるケースも多いため、短時間で企業の魅力を伝えられる構成が理想的といえます。
長尺にする場合でも、視聴者の興味を引き続けられる工夫を入れて、コンテンツの途中離脱を防ぐことが大切です。
機密情報や撮影許可はどうする?
製造業では製品の仕様や製造工程に関わる機密情報が多いです。
動画撮影時は機密エリアを避ける、撮影範囲を限定するなどの事前準備を徹底しましょう。
社内規定やクライアントとの契約によっては、撮影許可の取得や編集段階でのモザイク処理が必要になる場合もあります。
スマホ撮影でも採用動画は可能?
低コストでスピーディに制作したい場合、スマホ撮影を活用する選択肢もあります。
ただし、画質や音声のクオリティが下がると企業イメージにも影響するため、編集ソフトや外部マイクなど、最低限の撮影機材を整えることを検討しましょう。
シンプルな現場密着動画なら、工夫次第で十分スマホ活用可能です。
費用対効果を測る指標は?
主に、動画の再生回数やエントリー数、内定承諾率の変化などをKPIとして設定する企業が多いです。
また、SNS上でのリアクションや、面接時に「採用動画を見て応募した」といった声が増えたかどうかも効果測定の目安になります。
数値と定性情報の両面から成果を把握しましょう。
多言語字幕は必要?
海外からの人材採用を視野に入れている場合は、多言語字幕に対応する価値は十分にあります。
特に、製造業では外国人材の活用が進んでいるケースも多いため、英語やベトナム語、中国語など、ターゲット人材が話す言語を考慮して準備を行いましょう。
早い段階でインフラを整備しておけば、人材確保の幅が広がります。
製造業の採用動画まとめ
製造業にとって採用動画の活用は、企業理解を深めやすくミスマッチを減らすうえで非常に効果的です。
実際の工場や生産ラインを映し出すことで臨場感が高まり、求職者に納得感を与えることができます。
また、経済産業省が公表する統計資料でも、製造業の人材不足が課題となっている現状が示されており、動画を活用したブランディングは今後さらに注目度が高まるでしょう。
自社の特性や募集要件に合う動画を制作し、ターゲット層に効果的に届けるためには、制作会社選びやPDCAサイクルの継続がカギとなります。