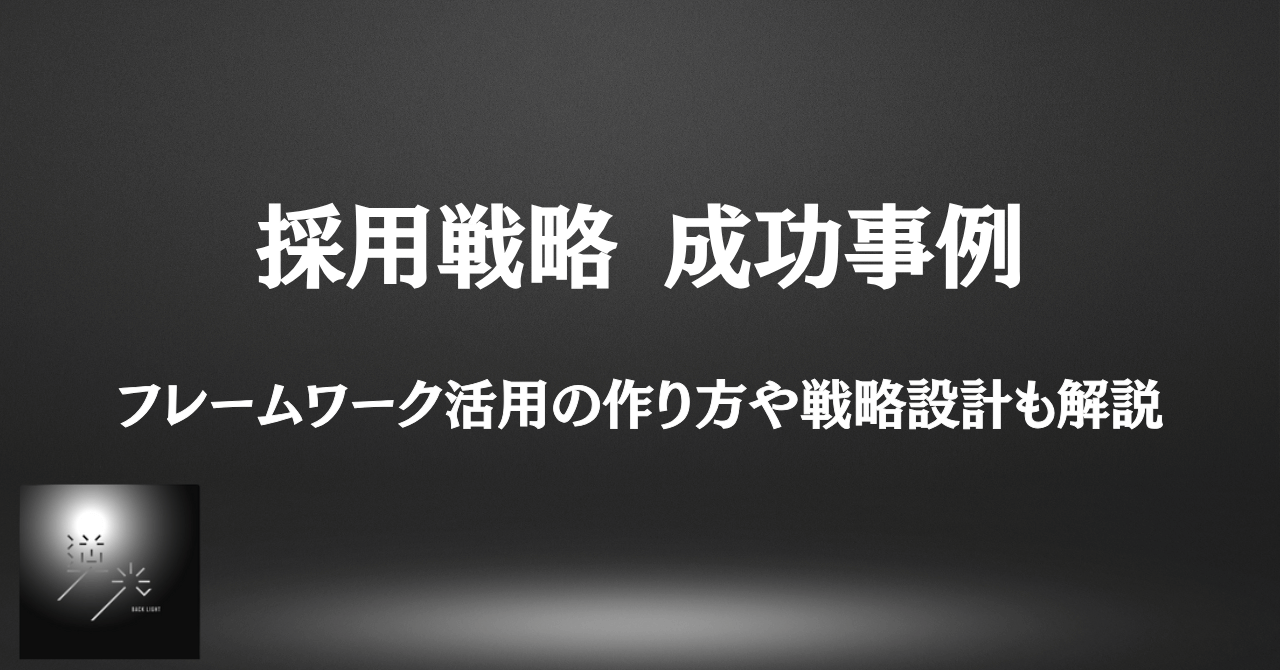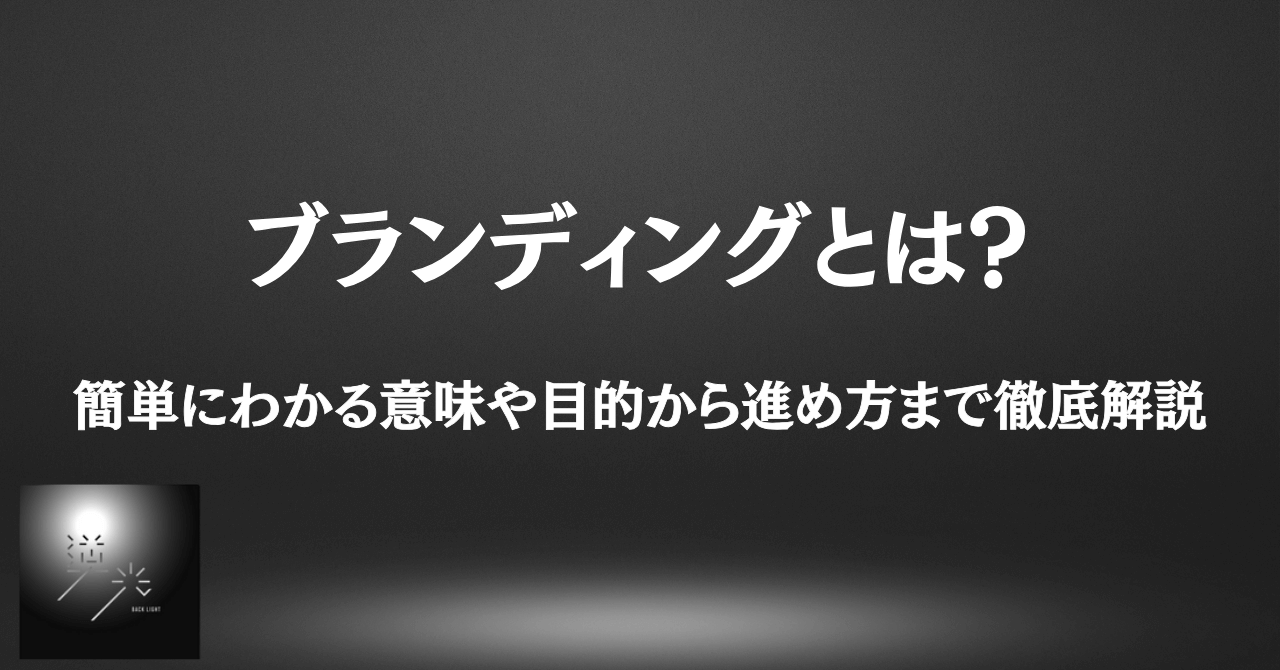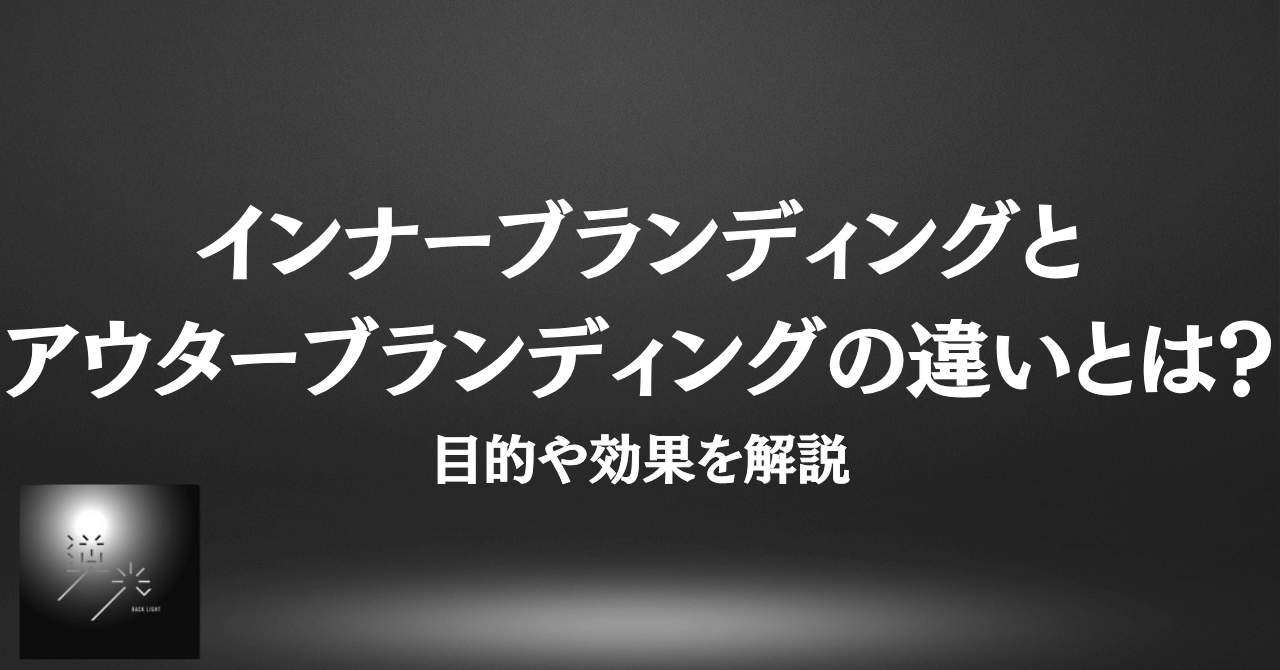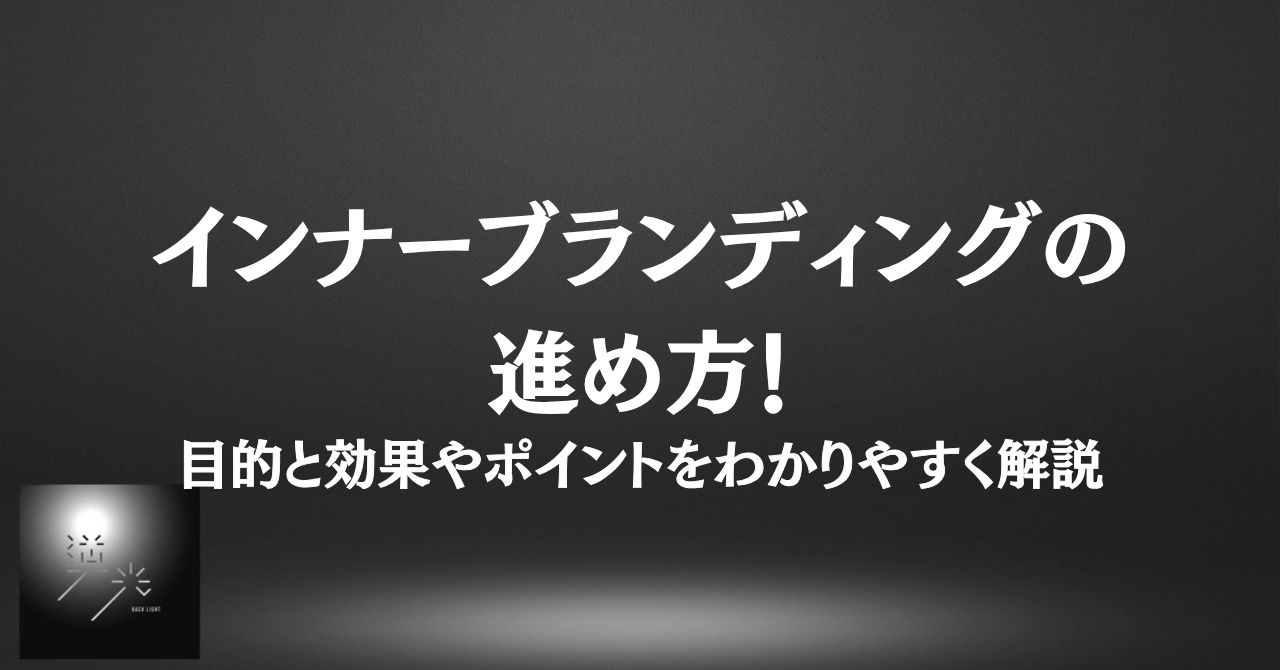企業が成長を続けるためには、優秀な人材を獲得し、長期的に活躍してもらうための採用戦略が欠かせません。
しかし「具体的にどのように採用戦略を立てればよいのか」「他社の成功事例を参考にしたい」と悩む企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、成功事例をもとに採用戦略を構築する手順やフレームワークを詳しくご紹介します。
読み進めることで、自社の課題を可視化し、より効果的な採用を実現するヒントを得ることができるでしょう。
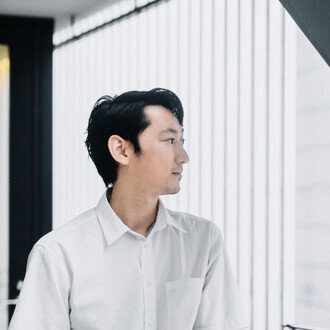
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用戦略とは?
採用戦略とは、企業が必要とする人材を確実に獲得し、組織へ定着させるために中長期的な視点で計画を練り、具体的な採用活動へと落とし込む指針のことです。
単なる「人を採用する」行為だけではなく、「どのような人材が必要か」「どうすればその人材に選ばれるか」といった視点を持ち、広報手段から面接プロセス、社内体制の整備まで一気通貫で考える点が特徴となります。
一般的に採用活動では、求人媒体の選択や面接フローの設計など部分的な施策に目が向きがちです。
しかしながら、経営ビジョンとリンクさせたうえで人材要件を明確にし、長期的に企業ブランドを発信することが重要です。
企業ブランドを発信する採用ブランディングの具体的な手法については、以下の記事で詳しく解説しています。
→採用ブランディングとは?目的や方法・メリットを事例とともに解説
また、企業規模や業種・職種によって必要な人材像や効果的な手法は異なるため、現状の分析と戦略の策定が欠かせません。
厚生労働省が公表している「令和4年雇用動向調査結果」においても、採用後の早期離職やミスマッチの課題が指摘されています。
こうした課題を防ぐためにも、明確な採用戦略を立て、実行と改善を繰り返すプロセスが不可欠です。
採用戦略の成功事例
採用戦略の成功事例を知ることで、具体的な施策の方向性や自社に落とし込む際のヒントを得られます。
以下の事例を読むことで、企業規模や業種に応じた取り組みのポイントを明確にし、実践イメージをより具体化することができるでしょう。
大手企業の戦略:ブランディングと長期施策
大手企業の成功事例では「企業ブランドの確立」と「長期的なリレーション構築」の2つが重要なカギとなっています。
例えば、有名な電機メーカーやIT企業では、学生時代からインターンシップや講演会、プロジェクトコンテストなどを通じて自社の強みや魅力をアピールしています。
こうした接点づくりにより「入社後のキャリアパスを具体的にイメージできる」「企業文化や価値観を体感できる」といったメリットが生まれ、優秀な層からの応募や内定承諾率の向上につながっているのです。
採用ブランディングで成果を上げた企業の具体的な施策については、以下の記事で紹介しています。
→採用ブランディングの成功事例10選!共通ポイントや進め方を解説
さらに、大手企業では広報やマーケティング部門との連携を強化し、採用活動自体をブランディングの一環として位置づけます。
具体的には、自社商品のCMやSNS配信などに採用担当者や現場社員が登場するケースも多く、応募者に「企業の姿が身近に感じられる」効果をもたらします。
こうしたアプローチによって「早期から自社に興味を持ってもらう」「応募者が入社後を想像しやすくなる」という長期施策が成功のポイントです。
中小企業の工夫:地域特化・紹介活用
一方、中小企業ではリソースが限られているからこそ「地域特化型の採用戦略」や「紹介・リファラルの活用」が目立ちます。
地域に根付いた企業として高校や大学、専門学校のキャリアセンターと緊密に連携し、インターンシップや会社見学を積極的に受け入れるケースが多いです。
地元での高い知名度がある企業はもちろん、知名度に不安がある場合でも「地域密着」「地元で働きたい学生を応援する」といったメッセージを押し出すことで、学生に響くブランディングとなります。
また、社内の社員ネットワークによる「リファラル採用(社員紹介制度)」の強化も有効です。
社員が実際に知人や友人を紹介するので、企業のカルチャーにマッチした人材が集まりやすく、入社後の定着率も比較的高い傾向があります。
その結果、採用コストの削減にもつながり、かつ紹介者・被紹介者がともに満足感を得られる仕組みができあがるため、社内のモチベーション向上にも寄与します。
中小企業が限られたリソースで採用を成功させるための戦略については、以下の記事で詳しく解説しています。
→中小企業の採用ブランディングとは?成功事例と戦略で人材獲得を加速しよう
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用戦略の成功事例に共通するポイント
成功事例を紐解くと、多様なアプローチがある一方で、共通して押さえているポイントが見えてきます。
以下の内容を読むことで、採用戦略をより体系的に捉え、自社独自の施策へ落とし込むための基本指針を確認できるでしょう。
KPIとファネル管理
採用戦略を成功に導くには、まず採用活動をファネル化し、各ステージでの目標(KPI)を定義することが重要です。
例えば、「応募数」「書類選考通過率」「内定承諾率」など段階的に目標を設定し、実際の数値を継続的にモニタリングします。
これにより、応募者数は十分でも面接通過率が低い、内定が出ても承諾されないといった問題点を特定しやすくなるのです。
KPIを設定し、ファネルのどこにボトルネックがあるかを把握することで、改善施策を効率的に打ち出せるようになります。
社員の巻き込みと広報の工夫
採用担当者だけでなく、現場社員や広報部門を巻き込んで行う広報活動や情報発信も、採用成功の要因としてよく挙げられます。
具体例としては、現場社員が運営に関わるSNSアカウントで職場の雰囲気や仕事のやりがいを発信したり、採用イベントで社員が登壇し、リアルなエピソードを共有するなどがあります。
社員を巻き込むことで、自社への親近感や安心感を高められ、「ここで働いている人が魅力的だから、自分も一緒に働きたい」と思わせる効果が期待できます。
また、広報部門との連携によって、企業ブランドを横断的にアピールすることも大切です。
例えば自社サイトの採用ページだけでなく、企業HPやSNS、プレスリリースなど多角的に情報を配信することで、求職者がさまざまな場所で企業の魅力に触れやすくなります。
結果的に応募者との接点が増え、採用効率の向上につながるのです。
SNS採用の具体的な進め方と成功事例については、以下の記事をご覧ください。
→SNS採用とは?メリットデメリットや成功事例でわかるソーシャルリクルーティングの始め方
ターゲット層に合わせた手法選定
採用戦略では「求める人材像」に応じて、アプローチ手法を最適化することも欠かせません。
新卒採用なら、就職イベントや大学のキャリアセンターとの連携、専門職なら業界イベントや専門メディアの利用、中途採用なら転職サイトやエージェントの活用など、手段は多岐にわたります。
例えば、ITエンジニアを求める場合、エンジニア向けの勉強会やコミュニティで情報発信するほうが、有効な人材と出会える可能性が高まります。
また、ターゲット層が求める魅力の訴求ポイントも、年齢や職種、価値観によって異なります。
「ワークライフバランス」「福利厚生」「キャリアアップ」「社会貢献」など、相手が何を重視しているのかを見極め、適切にアピールすることで応募意欲を高められるのです。
分析と改善の継続
採用戦略で成功を収めている企業は、実施後の分析と改善を繰り返すPDCAサイクルを徹底しています。
例えば、「SNS採用を始めたが思ったより応募者が集まらない」「イベントに参加したが内定承諾につながらない」といった結果が出た場合、すぐに理由を検証し、次の施策を打ち出すプロセスが大切です。
広告費用対効果など、数値データに基づく意思決定を行うことで、採用活動全体の質を高められます。
こうした継続的な改善を行う上では、社内の関係者(現場責任者や経営陣)へのレポーティングや共有も欠かせません。
定期的なミーティングや採用報告書を通じて、問題点や成功事例を全社で共有し、協力体制を維持しながら採用戦略をブラッシュアップしていくことが重要です。
採用戦略の立て方4ステップ
ここからは、具体的に採用戦略を立てるためのステップをご紹介します。
以下の内容を読むことで、自社の状況を整理し、最適な手法や改善策を設計するフレームワークを実践できるようになるでしょう。
ステップ1.採用課題の可視化と現状分析
採用戦略を練るうえで最初に行うべきは、自社が抱える採用課題の洗い出しと現状分析です。
例えば、新卒採用であれば「内定承諾率が低い」、中途採用であれば「応募は多いがミスマッチが発生している」など、現状を客観的に把握します。
- 既存の採用データの確認
過去数年の応募数・採用数・内定辞退率などを集計し、どのステージで問題が起きているか見極める。 - 採用対象の分析
人材市場全体の動向や業界の競合状況などを踏まえ、どのくらいの応募が見込めるかを概算する。
現状分析により、具体的な課題を特定できれば、戦略を立てる指針が明確になります。
一度辞めた社員を再度採用するアルムナイ採用といったまだあまり知られていない採用手法などもリサーチしておくことがおすすめです。
ステップ2.求める人材像の明確化
次に、自社が求める人材像を明確に定義します。
ここで「何でもできる人が欲しい」という曖昧な要件ではなく、「具体的なスキル」「経験レベル」「行動特性」など細かく設定すると効果的です。
また、企業の理念やビジョンに共感できるかどうかも重視すべきポイントとなります。
例えばベンチャー企業なら「変化に柔軟に対応し、自走力のある人」を求める場合が多いでしょう。
一方で、大手企業の専門職採用なら「特定分野の深い知識や経験、チーム内での連携スキル」を重視するといった具合です。
このフェーズで求める人物像が明確になると、後の採用チャネル選定や面接基準の統一がスムーズに行えます。
ステップ3.手法・チャネルの選定
求める人材が定まったら、それを獲得するための具体的な手法やチャネルを検討します。
代表的な手段としては、以下のようなものがあります。
- 求人媒体・転職サイト:大手求人サイトや専門職向けサイトなどを使い分ける。
- エージェントの活用:即戦力人材やハイレイヤー人材の採用に有効。
- リファラル(社員紹介):社員のネットワークを通じてカルチャーフィットの高い人材を獲得。
- SNS活用:企業アカウントだけでなく、社員個人の発信を促すケースも増加中。
- イベント・インターンシップ:交流を通じて企業文化や職場環境を体感してもらう。
また、近年では採用手法の一つとして、ショートドラマ×採用という斬新な取り組みも注目されています。
例えば「渋谷裕輝の転職転生日記」では、ドラマ仕立てのコンテンツを通して企業の魅力や価値観を発信し、ターゲット層の興味を引く試みが行われています。
こうした新しいチャネルも検討し、ターゲット人材との接点を多様化させることがポイントです。
企業の魅力を視覚的に伝える採用動画の制作方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
→かっこいい採用動画の事例を紹介!作り方や制作するメリットなどを徹底解説!
効果検証と改善
採用活動をスタートしたら、定期的に効果検証を行い、必要に応じて戦略を修正します。
冒頭でも触れたように、応募数や書類選考通過率、内定承諾率といったKPIをモニタリングし、想定より低い場合は原因を分析し施策を改善する流れです。
- 定量データの把握:スプレッドシートや採用管理システムを活用して数値の変動をチェック。
- 定性情報の収集:面接官や応募者からのフィードバックを聞き取り、プロセスの問題点を探る。
このサイクルを繰り返すことで、より洗練された採用戦略へと発展していきます。
採用戦略の事例に関してよくある質問
具体的な成功事例や採用戦略のポイントを踏まえたうえで、よく寄せられる疑問や不安を解消していきましょう。
以下を読むことで、採用戦略の設計と運用にまつわる共通の課題をスムーズに理解できます。
採用戦略と採用計画の違いは?
採用戦略と採用計画は混同されがちですが、一般的には以下のように区別されます。
- 採用戦略
「自社の経営ビジョンや組織方針に合った人材を獲得するため、どのような方向性・コンセプトで活動を進めるか」を示す大枠の指針。 - 採用計画
戦略を具体的に実行するための「スケジュール」「採用人数」「採用手段」「予算」などの詳細な計画書。
採用計画は採用戦略に基づいて立案されるため、まずは大枠の戦略を固めることが重要です。
どんな企業でも採用戦略は必要?
規模の大小や業種に関係なく、すべての企業にとって採用戦略は必要と言えます。
特に、中小企業はリソースに限りがある分、闇雲に採用活動を行うとコストや時間ばかりかかってしまい、ミスマッチが増えるリスクが高まります。
大企業であっても、時代の変化や人材市場のニーズに合わせて戦略を見直さなければ、人材獲得競争で後れを取る可能性があります。
自社のビジョンと人材ニーズを結びつけるためにも、採用戦略の策定は欠かせません。
採用戦略に活かせるツールは?
採用戦略の運用を効率化するツールとしては、以下のようなものがあります。
- ATS(ApplicantTrackingSystem)
応募者情報や選考ステータスを一元管理するシステム。 - SNS連携ツール
社員のSNS発信をサポートし、企業ブランドを拡散する。 - オンライン面接ツール
地理的な制約を超えて面接を実施でき、移動コストの削減につながる。 - アンケート調査ツール
内定者や離職者へのフォローアップ調査を効率的に行うことで、継続的な改善につなげる。
状況に応じてこうしたツールを導入し、人事担当者の工数を減らしつつ、採用フローを可視化していくことが大切です。
社内の理解をどう得るべき?
採用戦略の推進には、経営層や各部署、現場社員の協力が不可欠です。社内の理解を得るためには、以下のポイントを意識しましょう。
- 経営ビジョンとの整合性
採用の目標や人材像が経営方針と連動していることを明確に示す。 - 定期的な報告・共有
採用状況やKPIの進捗を社内にオープンにし、課題や成果を共有する。 - 巻き込み型の施策設計
社員や現場管理職が協力しやすい制度を作り、積極的な参加を促す。
こうした取り組みを通じて「採用は人事部だけの仕事ではなく、会社全体のプロジェクトである」という認識を醸成できます。
まとめ:採用戦略は事例から学び、自社に最適な戦略を描こう
採用戦略は、経営ビジョンと人材ニーズを結びつける大事な指針であり、企業規模や業種を問わず重要です。
大手企業ではブランディングや長期的なアプローチ、中小企業では地域特化やリファラル活用など、成功事例からは多くのヒントが得られます。
自社の課題を可視化し、求める人材像や手法を明確にして、分析と改善を重ねながら採用戦略を進化させていきましょう。
ショートドラマ×採用など新たな方法にも目を向ければ、他社との差別化を図る大きなチャンスとなります。