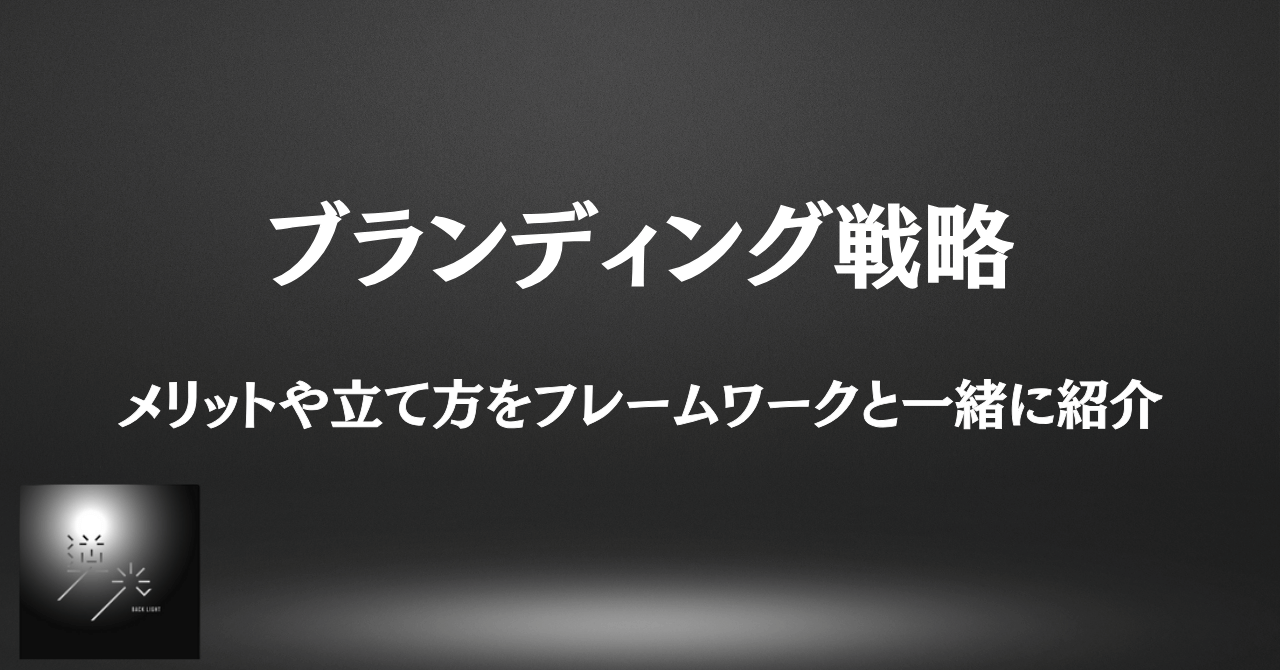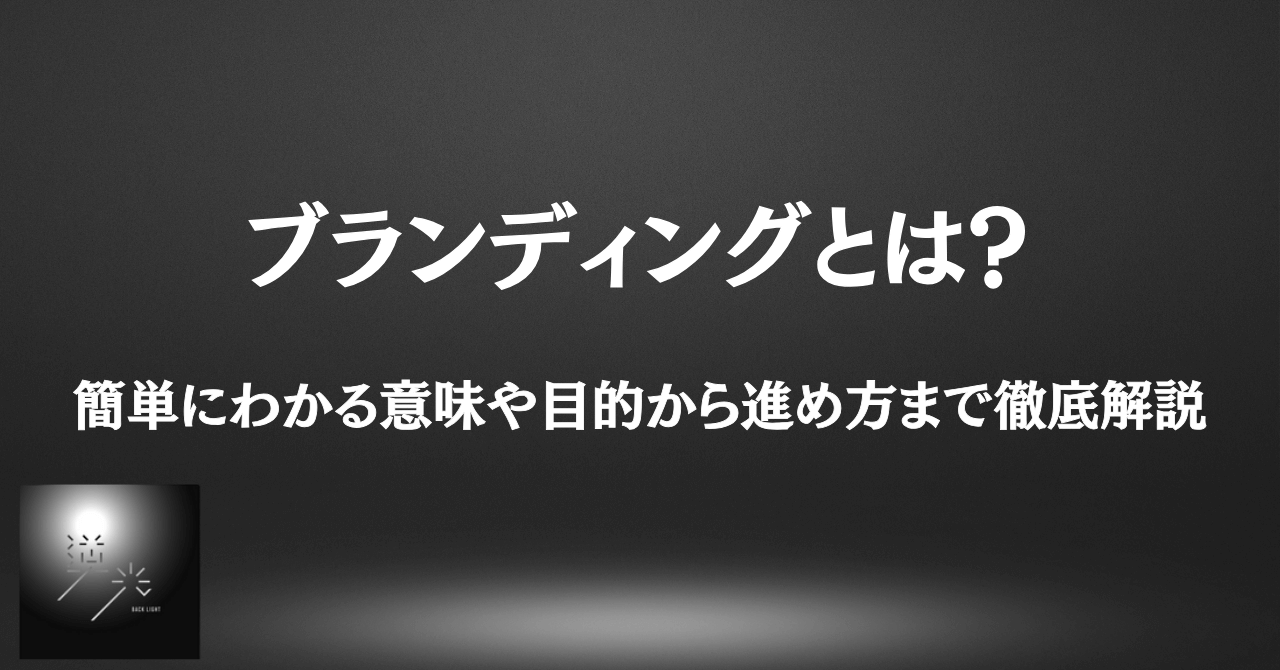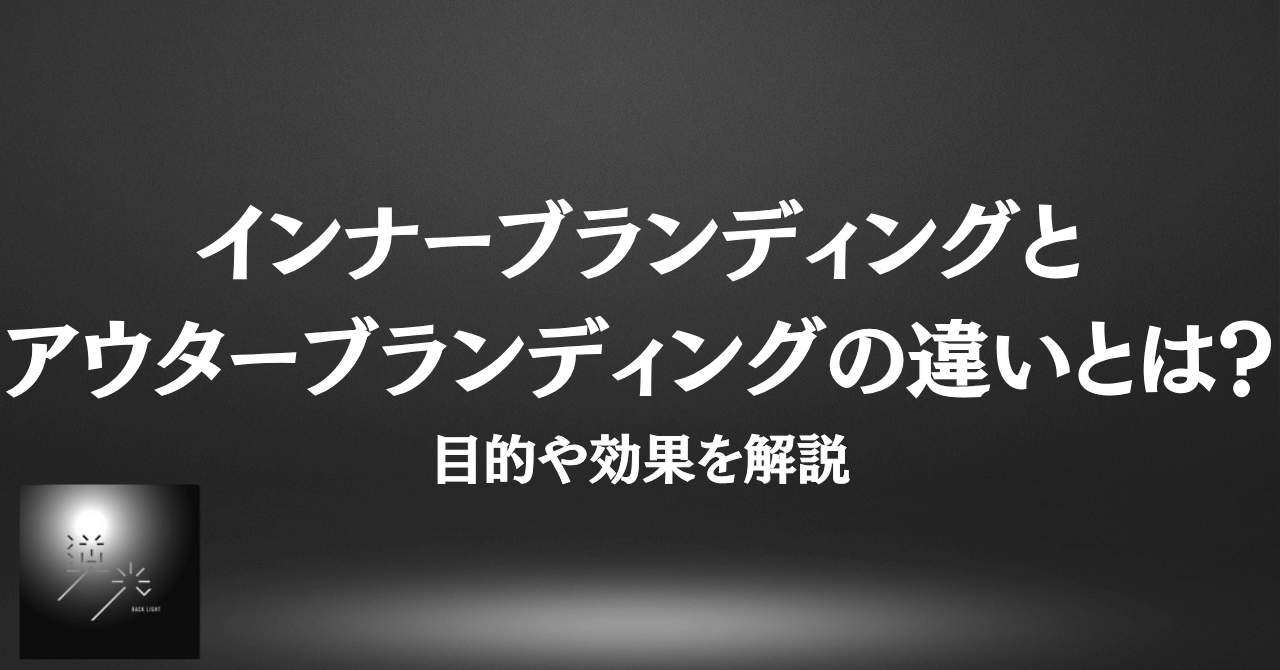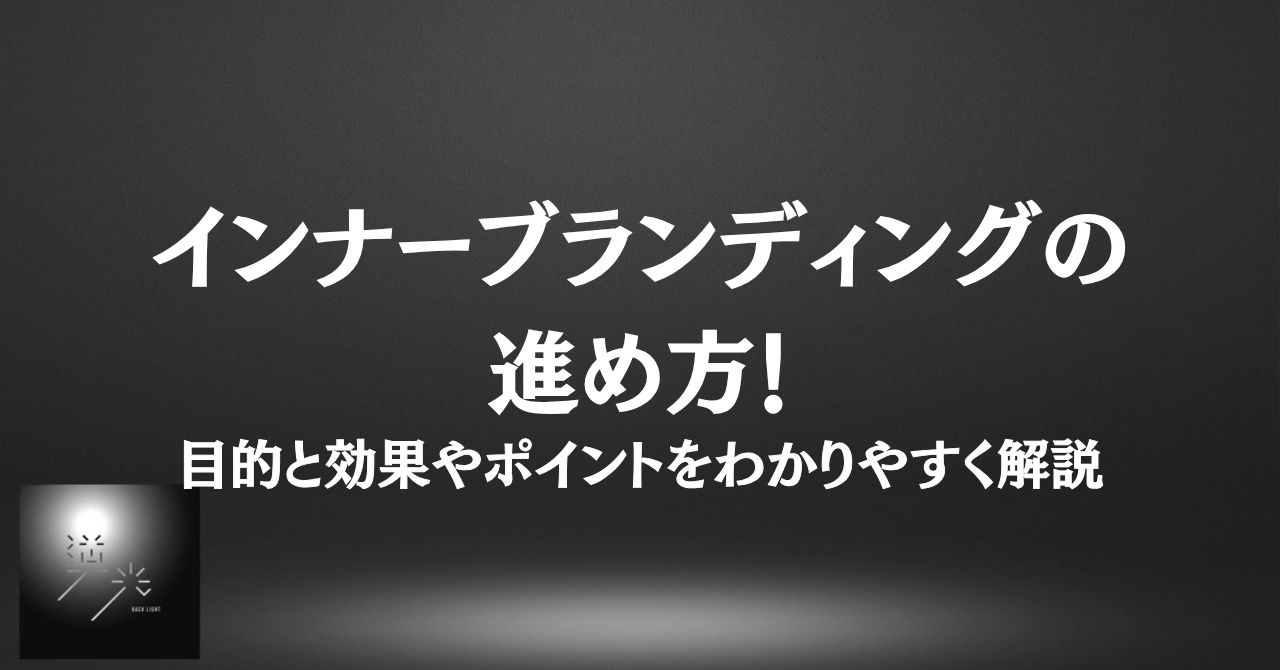企業が競合との差別化を図り、顧客から選ばれる存在になるためには、自社のブランド価値を明確に打ち出す必要があります。
そこで欠かせないのが「ブランディング戦略」です。
しかし「ブランディング戦略の立て方がわからない」「そもそもブランドをどう定義すればいいの?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事ではブランディング戦略の概要や重要性、具体的な立て方や成功に導くポイントをフレームワークとともにご紹介します。
最後までご覧いただくことで、貴社の競争力を高めるための具体的なアクションプランが見えてくるはずです。
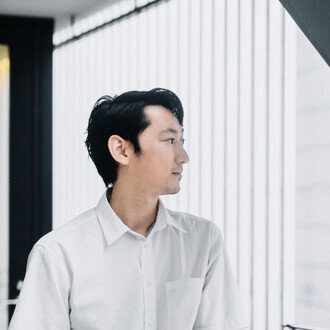
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
INDEX
ブランディング戦略とは?
ブランディング戦略とは、自社の商品やサービス、企業そのものが持つ価値や世界観を明確にし、それを社内外に伝えていく活動全般を指します。
消費者の頭の中にある「企業イメージ」や「商品の印象」を戦略的にコントロールすることで、他社と一線を画す存在になることを目指すのです。
単なる広告やデザインの見直しだけでなく、企業文化や顧客体験など多角的な要素を総合的に整理・発信していく必要があります。
その結果、価格競争に巻き込まれにくくなり、顧客ロイヤリティが高まるなど、長期的なメリットが期待できます。
ブランディングの基本概念についてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
→ブランディングとは?簡単にわかる意味や目的から進め方まで徹底解説
ブランディング戦略を立てるべき理由
このパートを読むと、ブランディング戦略がなぜ企業経営において欠かせない存在なのか、その根拠と背景を掴めます。
理解することで、日々のマーケティングや組織づくりにおいてもブランディング戦略の必要性を意識しやすくなります。
競合との差別化
市場に同種の製品やサービスが溢れるなか、顧客に「このブランドでなければならない」と思わせることが企業の生き残りには不可欠です。
そこで重要となるのが、競合との明確な差別化を生み出すブランディング戦略です。
例えば、アップル(Apple)の場合は「革新性」と「デザイン性」を武器に、競合企業との差別化に成功しました。
独自の世界観とユーザー体験を徹底して提供することで、たとえ同じジャンルの製品でも「Apple製品を選ぶ理由」が明確になり、ファンを獲得しています。
顧客ロイヤリティの向上
競合が乱立する市場で長期的に企業を成長させるには、目先の売上だけでなくリピーターやファンの存在が欠かせません。
ブランディング戦略を通じて、顧客に「共感できるブランド」として認知してもらうことで、顧客ロイヤリティが高まり、繰り返し購入やポジティブな口コミが生まれやすくなります。
スターバックスが「第三の場所(ThirdPlace)」というコンセプトを大切にするのは、顧客の居心地の良さや体験価値を提供し、ロイヤリティを高める施策の一環です。
結果として、コーヒーの味だけでなくブランド体験そのものが選ばれる理由となり、再来店率につながっています。
ブランディング戦略で得られるメリット
このパートを読むと、ブランディング戦略を行うことで得られる具体的な成果を把握できます。
どのように企業活動にプラスに働くかを理解すれば、戦略実行のモチベーション向上にも役立つでしょう。
売上と利益率の向上
ブランディングが確立されると、単に価格面だけでなく「ブランド独自の価値」によって顧客が商品を選ぶようになります。
これにより価格競争から抜け出しやすくなるため、一定の利益率を確保しやすくなるのです。
例えば、高級車ブランドや高級ファッションブランドなどは「ブランド名そのもの」が付加価値を生み出し、高額でも購入される背景があります。
結果として、売上の拡大や利益率の向上につながりやすくなります。
採用・資金調達への効果
ブランディング戦略は、外部顧客だけでなく採用活動や資金調達にも良い影響を及ぼします。
認知度と好感度の高いブランドは、人材が「この企業で働きたい」と思いやすく、優秀な人材確保がしやすくなるのです。
また、企業の世界観やビジョンがはっきり示されていれば、投資家や金融機関も企業の成長可能性を判断しやすくなり、資金調達のハードルが下がります。
結果として、ブランディング戦略が企業の発展全体を後押ししていくことが期待できます。
>>採用戦略についてはこちらの記事で紹介しています。
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
ブランディング戦略の立て方5ステップ
このパートを読むと、どのようにブランディング戦略を具体化・推進していくか、段階を踏んで理解できます。
体系的に進めることで、属人的なアイデア頼みから脱却し、組織全体でブランドをつくり上げることが可能になるでしょう。
STEP1現状把握とヒアリング整理
まずは自社やステークホルダーの現状を正しく把握し、どのような価値や課題、方向性があるのかを整理することが重要です。
経営者や主要メンバーからのヒアリングを通じて、言語化されていない想いを汲み取りましょう。
経営者自身のビジョンや理念に加え、現場の社員が抱えている小さな違和感や顧客とのやり取りのなかで得られた生の声も大切な情報源です。
またオケージョン分析を行い、顧客が商品を使用する状況や背景、動機を深掘りします。
さらに、ターゲットペルソナの価値観やライフスタイルを設定し、自社が提供できる価値と合致しているかを確認します。
こうして経営陣・現場・顧客の視点を総合的に言語化することで、次のステップでより具体的な戦略設計が可能になります。
STEP2構造分析とブランド戦略整理
STEP1で集めた情報をもとに、客観的な分析フレームワークを活用しながら自社の立ち位置を整理します。
箇条書きでまとめると以下の通りです。
- SWOT分析で強み・弱み、機会・脅威を整理
- 4C分析で顧客ニーズと自社の魅力、競合、コミュニケーション方針を検討
- ファイブ・ウェイ・ポジショニング分析で差別化戦略を検討
- ブランドポジショニングマップで競合状況と自社の立ち位置を可視化
例えば、SWOT分析や4C分析、ファイブ・ウェイ・ポジショニング分析などを組み合わせ、自社の強み・弱み、競合との違い、顧客のニーズなどを立体的に把握します。
さらに、感情設計マーケティングの視点から「ユーザーがどんな感情の動きでブランドに惹かれるのか」を読み解くことも有効です。
ここでWho(ターゲット)/What(提供価値)/How(実現方法)をまとめ、ブランドポジショニングマップを作成します。
「競合が多い領域だけれど、ここに強みを活かして入り込めるのか」「市場にまだ無い新しいポジションを狙えるのか」など、ビジネスチャンスを視覚的に確認できるのが利点です。
最終的に、コンセプトの核になる要素(共感軸・信念・勝てる理由)をリストアップし、次のステップでのコンセプト策定に備えます。
STEP3ブランドコンセプトと言語化
分析結果をもとに、企業や商品の本質的な魅力と目指す方向性を明確化し、ブランドコンセプトへ落とし込みます。
箇条書きでまとめると以下の通りです。
- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)の草案作成
- ブランドストーリーを構築し、物語性を持たせる
- パーパスやタグラインでブランドの意義・魅力を端的に表現
- キーメッセージや象徴フレーズを設定し、ブランドの軸を明確化
具体的にはMVV(ミッション・ビジョン・バリュー)やパーパスの策定、ブランドストーリーの構築が重要です。
例えば、「顧客がどのような理想像に近づく手助けをするのか」「社会にどう貢献するか」など、企業の存在意義を言葉にすることで社内外にわかりやすく伝わります。
また、「らしさ」を感じられるエピソードや創業の背景などをストーリーとしてまとめることで、ブランドに共感を呼ぶ物語をつくることができます。
最終的にキーメッセージや象徴的なフレーズを開発し、訴求力のあるブランドコンセプトを完成させましょう。
コンセプト設計の詳細についてはこちらで掘り下げています。
→ブランディングにおけるコンセプトとは?作り方や成功のポイントを紹介
STEP4ビジュアル・表現への展開
次に、言語化したブランドコンセプトを表現に落とし込みます。
箇条書きでまとめると以下の通りです。
- ロゴやVI(ビジュアルアイデンティティ)を設計し、世界観を明確化
- カラーや書体、写真・イラストなどブランドトーンを統一
- スタイルガイドを整備して制作物に一貫性を持たせる
- SNS広告など幅広いクリエイティブに拡張し、統一感を演出
ロゴや色、書体、写真、映像などのビジュアル要素は、顧客に与える第一印象を左右するため非常に重要です。
例えば、「高級感を演出するなら落ち着いた色味と上質なフォント」「若々しさを出すならポップなカラーとカジュアルなフォント」といった形で、ブランドが伝えたい世界観と合致した表現を選択します。
また、ウェブサイトやパンフレットなどに展開するときは、コンセプトトーンガイドやスタイルガイドを整備し、どのデザイナーや制作会社が関わっても統一したブランドイメージを保つことが大切です。
こうした統合感がブランドのクオリティを高め、顧客の信頼を獲得する要因となります。
STEP5内部浸透と社内文化への落とし込み
ブランドは社外向けのイメージだけで成り立つわけではなく、社員一人ひとりがブランドの意義を理解し、日々の行動に落とし込むことが欠かせません。
そのために、社内説明会やブランド浸透ワークショップを開催し、経営陣から現場まで一貫したメッセージを共有するのがポイントです。
箇条書きでまとめると以下の通りです。
- ブランド浸透ワークショップや社内説明会で全社員に方向性を周知
- 評価制度・行動指針をブランド理念と結びつける
- 社内でブランドイメージを体現する空間づくりや小物演出を行う
- 社員一人ひとりがブランドの語り手・体現者となることを目指す
また、評価制度や行動指針とブランドの理念を結びつけることで、社員が「ブランドを体現する行動」を自然に意識するようになります。
小さな工夫としては、オフィスの空間演出やノベルティのデザインなどにもブランド要素を取り入れ、社員のモチベーションと誇りを高める仕掛けを設けましょう。
こうした内部浸透が進むと、社員が自然と「ブランドの担い手」として動き、顧客とのコミュニケーションでも一貫した体験を提供できるようになります。
インナーブランディングの具体的な実装方法と成功事例については、こちらで詳しく解説しています。
→インナーブランディングの成功事例紹介!企業での進め方を具体例を交えて解説!
ブランディング戦略を強化するデジタル施策
このパートを読むと、デジタル領域での具体的なブランディング強化方法がわかります。
オンライン上での顧客接点が増えている今、これらの施策を知ることでブランド認知拡大と顧客ロイヤリティ向上を効果的に狙えるでしょう。
SNS運用とUGC活用
SNSは企業がブランドの世界観をダイレクトに発信できる貴重な場です。
ユーザーが自然に共有してくれるようなコンテンツを企画すれば、UGC(UserGeneratedContent)を通じてブランドが拡散され、多くの人に認知されます。
例えば、写真共有アプリでのハッシュタグ企画やキャンペーンなどを行うと、ブランドに共感を持つユーザーが自発的に情報を発信してくれます。
結果として広告費を抑えつつ、信頼度の高い口コミとしてブランドメッセージを届けることが可能になります。
オウンドメディアとSEO
オウンドメディアや自社ブログを活用すれば、企業の専門性やストーリーを深堀りして発信できます。
顧客にとって価値あるコンテンツを提供することで、検索エンジン経由のトラフィック獲得が可能です。
ブランディング戦略において大切なのは、一貫した世界観と専門性を示しながら、顧客の興味や課題に寄り添った情報を発信することです。
例えば、レシピサイトや健康情報サイトを運営する食品・ヘルスケア企業は、自社商品の信頼性を高めつつ、顧客との接触機会を増やしています。
SEO対策をしっかり行うことで、中長期的に顧客との接点を確保し、ブランド認知を広げることができます。
オンラインコミュニティの構築
自社ブランドに熱量の高い顧客を中心にコミュニティを形成すると、ユーザー同士の交流から新たな価値が生まれます。
コミュニティが活性化すると、顧客同士が製品の使い方や活用事例を共有し合い、ブランドへの愛着がさらに深まります。
また、コミュニティ内部で出たフィードバックを製品・サービス開発に活用すれば、顧客のリアルな声を素早く反映できるため、より高い顧客満足を実現することも可能です。
こうした積極的なコミュニケーションの場をデジタル上に設けることで、ブランドのファンを巻き込んだマーケティングが行いやすくなります。
ブランディング戦略に役立つ分析フレームワーク
このパートを読むと、ブランディング戦略に欠かせない代表的な分析手法を押さえることができます。
どのフレームワークをどのタイミングで活用すべきか知っておくと、より確実な戦略立案が可能です。
SWOT分析
SWOT分析は、内部環境のStrength(強み)・Weakness(弱み)と外部環境のOpportunity(機会)・Threat(脅威)を整理するフレームワークです。
自社の持つリソースや得意領域を把握すると同時に、市場環境や競合動向から見えてくる機会とリスクを認識することができます。
ブランディング戦略においては「強み」をどのようにブランド価値として打ち出すか、「弱み」をどう克服またはカバーするかがポイントとなります。
STP分析
STP分析は、Segmentation(市場の細分化)→Targeting(狙う顧客層の選定)→Positioning(ポジショニング策定)の流れで市場を分析する手法です。
ブランディング戦略を考える際には、まずどのセグメントを重点的に攻めるのかを明確化する必要があります。
そこから「選んでもらう理由」を明確にするポジショニングへとつなげ、コンセプトの設計やコミュニケーション戦略に反映していきます。
4P/4C
4P(Product,Price,Place,Promotion)は企業側の視点、4C(Customer,Cost,Convenience,Communication)は顧客の視点を整理するフレームワークです。
特に、ブランディング戦略では、顧客がどう感じ、どう行動するかを考慮して施策を構築することが大事です。
例えば、価格設定一つをとっても、プレミアム感を出すために高価格戦略を取るのか、それともユーザーが「続けやすい」と感じる適正価格にするのかで、ブランドのイメージが大きく変わってきます。
これらのフレームワークをコンセプト設計に活用する方法については、こちらで詳しく解説しています。
→コンセプト設計のフレームワークで差がつく!作り方の手順を完全解説
ブランディング戦略推進の組織体制とインナーブランディング
戦略が立案されても、推進組織が整っていなければ成果は得にくいものです。
このパートを読むと、ブランディング戦略を社内でどのように実行・運営するかのヒントが得られます。
インナーブランディングとアウターブランディングの違いについてはこちらをご参照ください。
→インナーブランディングとアウターブランディングの違いとは?目的や効果を解説
社内浸透策
ブランディング戦略を推進するうえで最も重要なのは、社内メンバー全員が共通認識を持つことです。
経営トップが先頭に立ってブランドの方向性を明確に示し、部署単位でワークショップや研修を実施するなど、具体的な浸透活動を行いましょう。
また「うちのブランドをもっと好きになろう」という意識づけのために、コンセプトムービーを制作したり、オフィスの空間デザインを変更したりといった取り組みも有効です。
例えば、中小企業庁が公表している資料でも「ブランドの浸透にはトップダウンとボトムアップの両面からの取り組みが必要」と言及されているように、経営層と現場のコミュニケーションを丁寧に行うことが重要です。
社内での具体的な進め方についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
→インナーブランディングの進め方!目的と効果やポイントをわかりやすく解説
部門横断プロジェクトの設計
ブランドはマーケティングだけでなく、人事、営業、開発など様々な部門が関わります。
そのため、部門横断型のプロジェクトチームを組成し、各部門の意見を取り入れながら意思決定を行うと効果的です。
定例ミーティングを設定して情報共有を密に行い、ブランドコンセプトが常に最新の状況に合わせてアップデートできるようにします。
また、社外のステークホルダー(パートナー企業や代理店)に対しても、一貫したメッセージを伝える仕組みをつくっておくと混乱を防げます。
ブランディング戦略の効果測定指標
このパートを読むと、ブランディング戦略の成果をどのように評価し、改善につなげるかがわかります。
定量指標と定性指標のバランスを考えながら、継続的に分析を行うことが大切です。
ブランド認知度
最もシンプルな指標が「ブランド認知度」です。
広告認知調査やSNSのフォロワー数、検索数の増加などを測ることで、どれだけ多くの人にブランドを知ってもらえたかがわかります。
認知度が低ければ、まずは認知向上施策を強化すべき段階だと判断できます。
NPS・ブランドロイヤリティ
NPS(NetPromoterScore)は、顧客がどれほど製品やサービスを他者に推奨したいかを数値化する指標です。
ブランドロイヤリティの高さを示すうえで有効であり、顧客満足度だけでなく「熱量」や「ファン度合い」を捉えられます。
ロイヤリティが高まれば、口コミやリピート購入につながりやすく、長期的な収益に貢献します。
KPI例:売上・LTV
最終的に経営へインパクトを与えるのは売上や利益であり、顧客あたりの生涯価値(LTV)も大きなポイントです。
ブランドの訴求力が高まれば、離脱率や価格競争の影響が下がるため、顧客一人あたりの購入額や利用継続率が向上します。
これらの数字を定期的に追いかけ、ブランド施策と売上・LTVの相関を把握して改善を繰り返すことで、ブランディング戦略を着実に育てることができます。
ブランディング戦略に関してよくある質問
このパートを読むと、ブランディング戦略にまつわる基本的な疑問が解消されます。迷いやすいポイントを把握することで、具体的なプラン実行時にもスムーズに進められるでしょう。
ブランド戦略とブランディングの違いは何ですか?
一般的にブランド戦略は、ブランド価値を高めるための長期的な計画や仕組みを指し、ブランディングはその戦略に基づいて実際に行う行動や表現を指すことが多いです。
両者は密接に関連しており、ブランド戦略がなければブランディングの方向性が定まらず、ブランディングがなければブランド戦略は実行できません。
ブランディングの3要素とは?
ブランディングを考える際によく挙げられるのが、以下の通りです。
- 視覚的要素(ロゴ、カラー、デザイン)
- 言語的要素(ネーミング、コピー、ストーリー)
- 体験的要素(接客、サービス設計、コミュニティ活動)
これら3つが一貫してブランドの世界観を伝え、顧客との深い結びつきを生み出します。
ブランディングの効果が出るまでの期間は?
一般的には短期間で劇的に変わるものではなく、半年から数年単位の時間を要します。
ブランディングは市場に浸透し、顧客の心理的な信頼や好感度を醸成するプロセスが必要なため、粘り強い取り組みが求められます。
予算の目安は?
企業規模や目的、扱う領域によって大きく変動します。
ロゴ制作やブランドコンセプト策定だけなら数十万円程度、企業全体のブランディング見直しや大規模広告展開を含む場合には数千万円規模に達することもあります。
まずは、目標と優先順位を明確にし、段階的に投資するのがおすすめです。
中小企業でも必要か?
むしろ同質化しやすい市場でこそ、ブランディングを活用して差別化を図る価値があります。
大企業に比べて認知度が低いからこそ、明確なブランドコンセプトを示し、ターゲット顧客に「選ばれる理由」を作ることが重要です。
BtoBとBtoCでの違いは?
BtoCでは感性的な要素が重視されることが多い一方、BtoBでは理性的な要素や実績・信頼性の訴求が重視されます。
ただし、どちらの場合も最終的には「相手の感情や期待をどう満たすか」が鍵であり、コミュニケーション方法やプロセスが異なるだけで目的は共通しています。
ブランディング戦略のまとめ
ブランディング戦略は競合他社との差別化と顧客ロイヤリティの向上に大きく寄与し、売上や採用力、資金調達力までも高めてくれる包括的な取り組みです。
まずは、自社の現状把握や分析フレームワークによる構造的な検討から始め、得られた洞察を言語化・ビジュアル化し、組織全体で共有するプロセスが重要となります。
オンライン施策やコミュニティづくりなどのデジタル面も強化しつつ、効果測定指標を追いかけて継続的に改善していくことで、強く愛されるブランドを築き上げることができるでしょう。