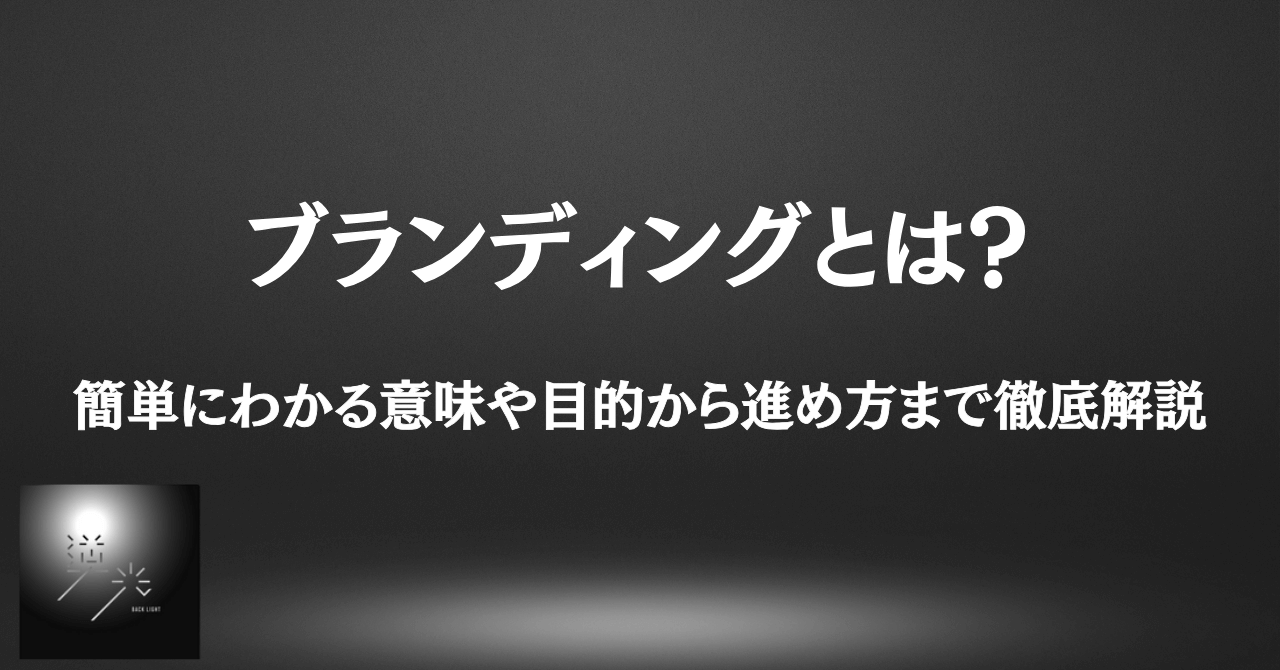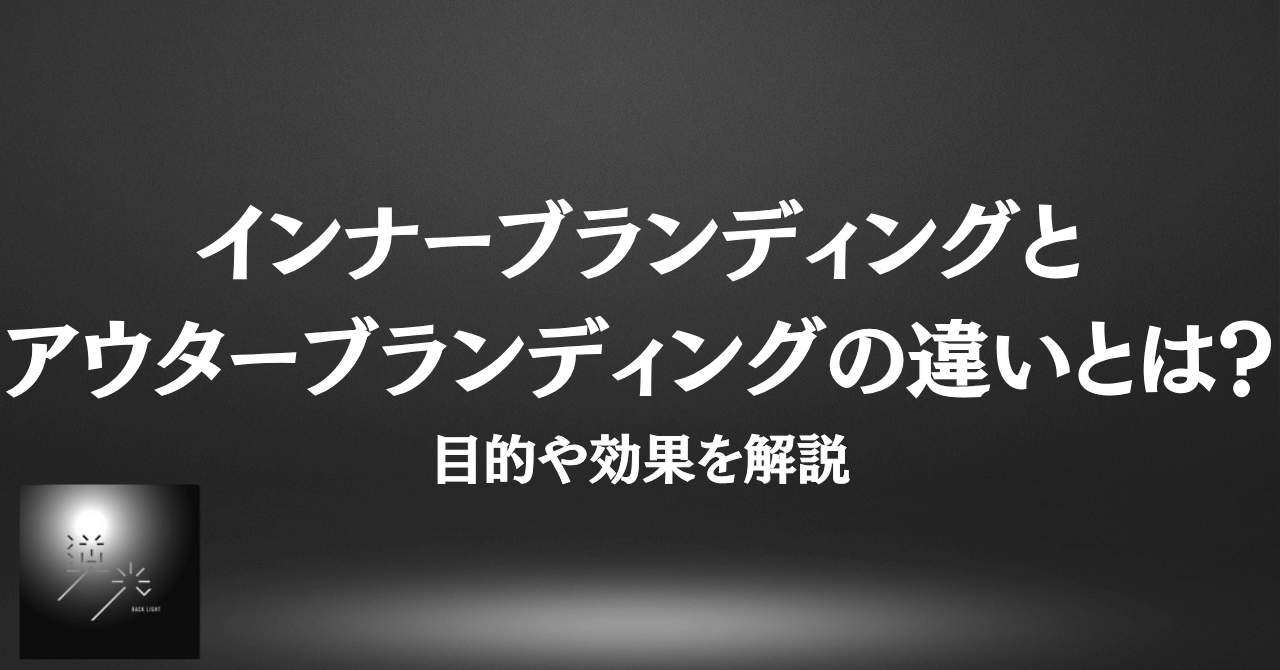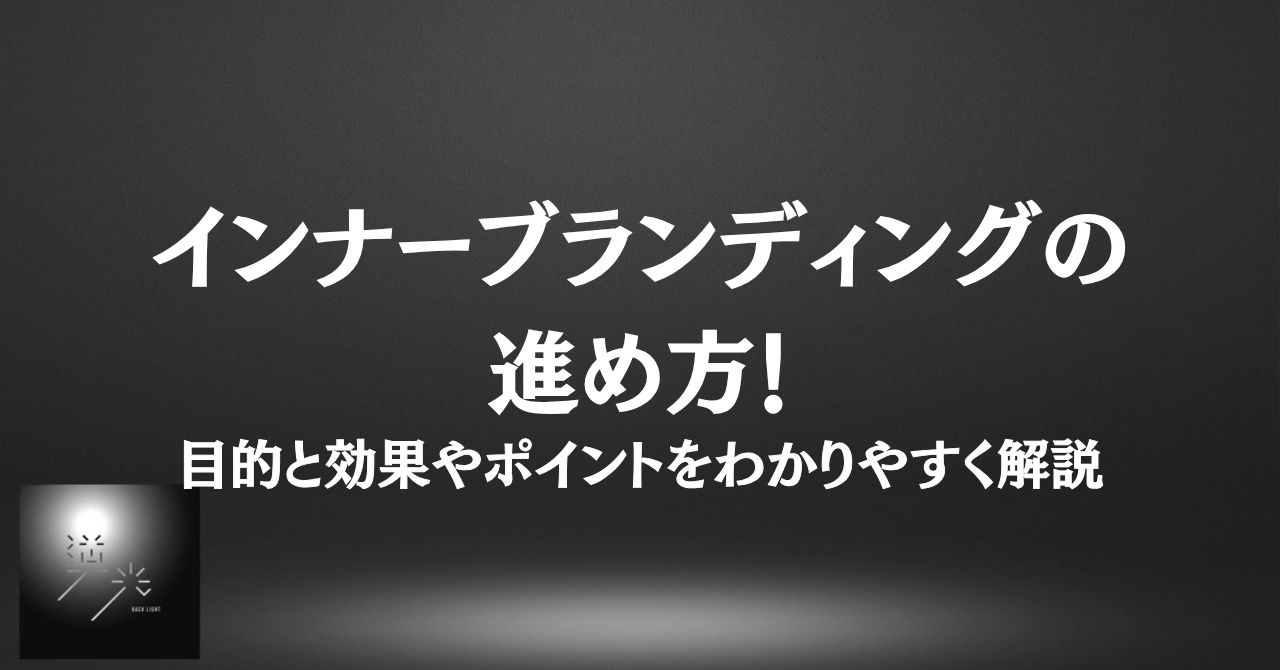近年、多くの企業が新たな採用手法として注目している「SNS採用」。
言葉は聞いたことがあっても、具体的な内容や始め方、成功のポイントまでを深く理解している方はまだ少ないかもしれません。
本記事では、SNS採用の基礎知識から、具体的なメリット・デメリット、主要SNSごとの活用法、そして国内企業の成功事例までを網羅的に解説します。
採用活動に課題を感じている人事担当者様や、新しい採用チャネルを模索している経営者様は、ぜひ最後までご覧ください。
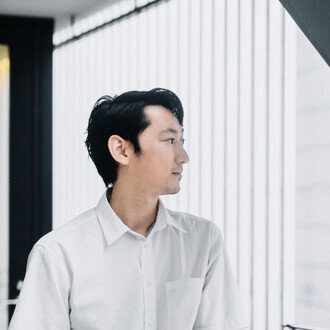
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
INDEX
SNS採用とは?
まずは、SNS採用の基本的な定義と、なぜ今これほどまでに注目されているのかについて解説します。
SNS採用の定義と目的
SNS採用とは、企業がInstagram、X(旧Twitter)、Facebook、LinkedInなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)を活用して行う採用活動全般を指します。
単に求人情報を投稿するだけでなく、企業文化や働く社員の日常、ビジョンなどを発信することで、潜在的な候補者との継続的な接点を持ちます。
そして、企業への理解や共感を深めてもらい、応募につなげることを主な目的としています。
従来の「待ち」の採用とは異なり、企業側から積極的に情報を発信し、候補者へアプローチする「攻め」の採用手法と言えるでしょう。
採用戦略全体の体系的な構築についてはこちらをご参照ください。
→採用戦略の成功事例!フレームワークを活用した作り方や戦略の立て方を分かりやすく徹底解説!
ソーシャルリクルーティングとの違い
SNS採用と似た言葉に「ソーシャルリクルーティング」があります。
これらはほぼ同義で使われることがほとんどです。
厳密には、ソーシャルリクルーティングがSNSだけでなく、ブログや掲示板など、より広範なソーシャルメディア全般を活用した採用活動を指す場合があります。
しかし、現代の採用活動においては、SNSが中心となるため、「SNS採用=ソーシャルリクルーティング」と捉えて差し支えありません。
注目度が高まる社会的背景
SNS採用が急速に普及している背景には、いくつかの社会的な変化があります。
第一に、スマートフォンの普及とSNS利用の一般化です。
特に、採用ターゲットとなる若い世代にとって、SNSは情報収集の主要なツールとなっています。
第二に、労働人口の減少に伴う採用競争の激化です。
従来の求人媒体だけでは、求める人材に出会うことが難しくなり、新たな母集団形成の手法が求められています。
第三に、Z世代をはじめとする若者の価値観の変化です。
彼らは給与や待遇だけでなく、「企業文化への共感」や「自己成長の機会」を重視する傾向にあります。
SNSは、こうした企業の目に見えない魅力を伝えるのに最適なツールなのです。
SNS採用のメリット4選
SNS採用を導入することで、企業は多くのメリットを享受できます。
ここでは、代表的な4つのメリットを具体的に解説します。
無料で認知拡大ができる
SNSアカウントの開設や運用は、基本的に無料で行えます。
従来の求人広告や人材紹介サービスに比べて、採用コストを大幅に抑えることが可能です。
また、投稿がシェアやリポストによって拡散されれば、広告費をかけずとも多くの潜在候補者に情報を届けることができ、効率的な母集団形成が実現します。
採用ブランディング強化と企業認知向上
SNSを通じて、自社のビジョンやミッション、社風、社員の働く姿などを継続的に発信することで、企業の魅力を多角的に伝えることができます。
これにより、「この会社で働きたい」「この会社は面白そうだ」というポジティブなイメージが醸成され、採用ブランディングが強化されます。
結果として、まだ自社を知らない潜在層への認知度向上にもつながります。
採用ブランディングの詳しい実装方法についてはこちらで解説しています。
→採用ブランディングとは?目的や方法・メリットを事例とともに解説
候補者のリアルな人物像を把握しやすい
候補者のSNSアカウントを閲覧することで、履歴書や職務経歴書だけではわからない、その人の興味関心や価値観、人柄などを垣間見ることができます。
もちろん、プライベートな投稿内容だけで評価を下すのは避けたほうがいいですが、面接時のコミュニケーションを円滑にするための参考情報として活用できます。
これにより、カルチャーフィットの精度を高める効果も期待できます。
選考スピードが向上する
SNSのダイレクトメッセージ(DM)機能を使えば、候補者と直接的かつスピーディーにコミュニケーションを取ることができます。
カジュアルな面談の案内や、選考日程の調整などを迅速に行えるため、候補者の熱量が高い状態を維持したまま、選考プロセスを進めることが可能です。
これにより、選考辞退率の低下にも貢献します。
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
SNS採用のデメリット4選
多くのメリットがある一方で、SNS採用には注意すべきデメリットも存在します。
対策と合わせて理解しておきましょう。
炎上・情報漏洩リスク
不適切な投稿や軽率なコメントが、企業の評判を大きく損なう「炎上」につながるリスクは常に存在します。
また、社員の投稿から、意図せずして企業の機密情報が漏洩してしまう可能性もゼロではありません。
これらのリスクを回避するためには、SNS運用に関する明確なガイドラインの策定と、担当者への徹底した教育が不可欠です。
運用工数と担当者スキル課題
SNS採用で成果を出すには、継続的なコンテンツ投稿やコメントへの返信、効果測定など、相応の運用工数がかかります。
また、ターゲットに響くコンテンツを企画・制作したり、データを分析して改善策を立案したりするには、マーケティングの知識やスキルも求められます。
誰が、どのくらいの時間をかけて運用するのか、事前に体制を整えておくことが重要です。
応募者の質がばらつく可能性
SNSは手軽に応募できる反面、企業への理解度が低いまま「とりあえず応募してみる」という候補者が増える可能性があります。
これにより、選考の初期段階でミスマッチが多く発生し、かえって人事担当者の負担が増えてしまうケースもあります。
募集要項や求める人物像を明確に提示し、ミスマッチを防ぐ工夫が必要です。
法的・倫理的な注意点
候補者のSNSを調査する際は、思想や信条、人種、病歴といった「要配慮個人情報」の取得に細心の注意を払う必要があります。
これらの情報を理由に不採用を決定することは、就職差別につながる恐れがあり、法的に問題となる可能性があります。
あくまでも候補者の公開情報から人柄や価値観を参考にする程度に留め、採用の判断基準は明確に定めておくべきです。
【主要SNS別】採用への活用方法
SNSと一言で言っても、その特性は様々です。
ここでは、主要な5つのSNSについて、採用活動への具体的な活用方法を解説します。
Instagramでビジュアル訴求
写真や動画がメインのInstagramは、企業の「雰囲気」を伝えるのに最適なプラットフォームです。
オフィス環境や社員イベントの様子、社員インタビュー動画などを投稿することで、働くイメージを直感的に伝えることができます。
24時間で消えるストーリーズ機能を使って、リアルタイムな情報や、よりカジュアルな社内の日常を発信するのも効果的です。
採用動画の制作方法と事例についてはこちらをご参照ください。
→かっこいい採用動画の事例を紹介!作り方や制作するメリットなどを徹底解説!
X(旧Twitter)で拡散力を活かす
Xの最大の特徴は、リアルタイム性と高い拡散力です。
「リポスト」機能により、有益な情報や面白い投稿は瞬く間に広がります。
これを活かし、自社のニュースリリースや説明会情報、社員の専門知識などを発信することで、幅広い層にリーチできます。
ハッシュタグ「#(キーワード)」を効果的に使うことで、特定のテーマに関心を持つユーザーに投稿を届けやすくなります。
TikTokでZ世代へアプローチ
ショート動画プラットフォームであるTikTokは、特にZ世代のユーザーが多く、若手人材の採用に強力なツールとなります。
仕事内容を面白く紹介する動画や、社員がダンスやトレンド企画に挑戦する「踊ってみた」動画など、エンターテイメント性の高いコンテンツが好まれます。
企業の堅いイメージを払拭し、親近感を持ってもらうのに有効です。
TikToKを採用チャネルとして本格的に活用する方法についてはこちらで詳しく解説しています。
→Tiktok採用とは?成功事例やメリットデメリットを網羅的に解説
LinkedInで専門職・ハイクラス採用
LinkedInは、世界最大級のビジネス特化型SNSです。
ユーザーは自身の経歴やスキルを登録しているため、専門職や管理職、グローバル人材といったハイクラス層の採用に適しています。
企業の公式ページで事業内容やカルチャーを発信するほか、企業の担当者が個人アカウントで候補者に直接アプローチする「ダイレクトリクルーティング」も可能です。
LINE公式で内定者フォローと定着支援
国内で最も利用者の多いLINEは、クローズドなコミュニケーションツールとして活用できます。
主に、一度接点を持った候補者や内定者との関係を深めるために使われます。
説明会のリマインド、選考日程の連絡、内定者向けの懇親会案内など、個別かつ確実な情報伝達に優れています。
入社前の不安を解消し、内定辞退を防ぐ効果が期待できます。
SNS採用の成功事例2選
ここでは、実際にSNS採用を成功させている企業の事例を5つ紹介します。
自社で取り組む際のヒントを見つけてください。
三和交通株式会社
タクシー会社の堅いイメージを覆すため、TikTokで社員がダンスを踊るなどのユニークな動画を投稿。
企業の認知度が飛躍的に向上し、若手からの応募が殺到しました。
結果として、乗務員の平均年齢を10歳以上若返らせることに成功しています。
株式会社カクヤス

Xで採用担当の「中の人」が、就活相談や自社の情報を親しみやすい言葉で発信。
学生とのフランクなコミュニケーションで信頼関係を築き、説明会は満席が続くなど、エンゲージメントの高い母集団形成に成功しました。
SNS採用の効果を高めるポイント
SNS採用は、ただやみくもに投稿するだけでは成果につながりません。
効果を最大化するための4つの重要なポイントを解説します。
ペルソナ設計とコンテンツカレンダー
「誰に、何を、どのように伝えるか」を明確にするため、採用したい人物像(ペルソナ)を具体的に設定します。
そのペルソナがどのような情報に興味を持つかを考え、コンテンツの方向性を決めましょう。
そして、「いつ、どのSNSで、何を投稿するか」を計画するコンテンツカレンダーを作成し、継続的かつ計画的な情報発信を心がけることが重要です。
採用コンセプトの設計方法についてはこちらで詳しく解説しています。
→採用コンセプトの作り方5ステップ!失敗しないポイントまで徹底解説
社員エンゲージメントを巻き込む仕組み
SNS採用は、人事担当者だけが頑張っても限界があります。
現場で働く社員に協力してもらい、彼らの日常や仕事のやりがいを発信してもらうことで、コンテンツにリアリティと深みが生まれます。
社員が自社のSNS投稿をシェアしたくなるような、魅力的なコンテンツ作りや、協力を評価する制度など、全社を巻き込む仕組み作りが成功の鍵です。
投稿KPI・採用KPIの二軸管理
SNS運用の効果を正しく測定するためには、2つの軸でKPIを設定することが大切です。
「いいね」数やフォロワー数、エンゲージメント率といった「投稿KPI」と、プロフィールページのクリック数や応募数、採用決定数といった「採用KPI」の両方を追跡します。
これにより、どの投稿が採用成果に結びついているのかを分析できます。
分析ツールとPDCAサイクル
各SNSが提供する分析ツールを活用し、定期的に投稿の効果を振り返りましょう。
どの曜日の、どの時間帯の投稿が伸びやすいのか。
どのような内容のコンテンツが好まれるのか。
データを元に仮説を立て(Plan)、実行し(Do)、効果を検証し(Check)、改善する(Action)というPDCAサイクルを回し続けることが、成果を最大化する上で不可欠です。
SNS採用の導入と運用フロー
実際にSNS採用を始める際の、具体的なステップを4段階に分けて解説します。
目的・目標を明確化する
まず、「何のためにSNS採用を行うのか」という目的を明確にします。
例えば、「若手人材の母集団を形成したい」「採用ブランディングを強化したい」「内定辞退率を改善したい」などです。
その上で、フォロワー数や応募数など、具体的な数値目標(KGI/KPI)を設定します。
公式アカウント開設とガイドライン策定
目的とターゲットに合ったSNSを選定し、公式アカウントを開設します。
同時に、炎上リスクなどを防ぐため、投稿内容のルールや、コメント・DMへの対応方針、緊急時の対応フローなどを定めた「SNS運用ガイドライン」を策定し、関係者間で共有します。
投稿・広告・リプライ運用の実践
策定した計画に基づき、コンテンツの投稿を開始します。
必要に応じて、特定の層にリーチするためのSNS広告も活用しましょう。
また、ユーザーからのコメントやリプライには、企業の「中の人」として誠実かつ丁寧に対応し、ポジティブな関係性を築いていきます。
応募受付〜選考プロセス連携
SNS経由での応募をスムーズに受け付けられるよう、プロフィールに応募フォームへのリンクを設置するなど、導線を設計します。
また、SNSでカジュアルに接触した候補者を、どのように通常の選考プロセスへと引き継ぐか、社内での連携フローを確立しておくことも重要です。
採用におけるSNSと他チャネルとの違いを比較
SNS採用の立ち位置をより明確にするため、他の採用チャネルとの違いを比較します。
リファラル採用とのシナジー
リファラル採用(社員紹介制度)とSNS採用は非常に相性が良い組み合わせです。
社員が自社のSNS投稿を自身のネットワークにシェアすることで、信頼性の高い情報として友人や知人に届きます。
これにより、リファラル採用のきっかけが生まれ、質の高い母集団形成につながるというシナジー効果が期待できます。
求人広告・ダイレクトリクルーティングとの違い
求人広告は、転職意欲が明確な「顕在層」にアプローチする手法です。
一方、SNS採用は、今すぐの転職は考えていない「潜在層」にもアプローチできる点が大きな違いです。
また、企業側から候補者に直接アプローチするダイレクトリクルーティング(DR)と似ていますが、SNS採用は1対1だけでなく、1対多のコミュニケーションで広くファンを育成する側面が強いのが特徴です。
SNS採用の最新トレンド2025
SNS採用の世界は常に進化しています。
今後主流になると予測される3つのトレンドを紹介します。
短尺動画主流化とUGC活用
TikTokやInstagramリールに代表される「短尺(ショート)動画」の重要性は、今後さらに高まるでしょう。
短い時間でインパクトを与え、企業の魅力を伝えるコンテンツ制作能力が求められます。
採用動画の効果測定とポイントについてはこちらをご参照ください。
→採用動画の効果とは?最大化するポイントと成功事例3選を完全解説
また、企業発信だけでなく、社員や内定者、顧客などが生み出すコンテンツをいかに活用するかも、採用ブランディングの鍵となります。
AIによる最適投稿タイミング予測
AI技術の進化により、自社のターゲットに最も情報が届きやすい曜日や時間帯、効果的なハッシュタグなどをAIが分析・予測してくれるツールが登場してきています。
これにより、データに基づいた、より効率的で効果的なSNS運用が可能になるでしょう。
コミュニティ形成でリテンション強化
単に情報を発信するだけでなく、SNS上に特定のテーマに関するコミュニティを形成し、候補者や内定者と継続的な関係を築く動きが加速します。
これにより、入社後の定着率(リテンション)向上にもつなげることができます。
SNS採用に関してよくある質問
最後に、SNS採用に関して人事担当者様からよく寄せられる質問にお答えします。
どのSNSが採用に向いていますか?
一概に「このSNSが一番良い」とは言えません。
採用したい職種やターゲット層によって最適なSNSは異なります。
例えば、若手やZ世代向けならTikTokやInstagram、エンジニアや専門職向けならXやLinkedIn、といった使い分けが重要です。
自社の採用目的とペルソナに立ち返って検討しましょう。
SNS採用の注意点は?
最も注意すべきは「炎上リスク」と「運用工数の確保」です。
企業の代表としての自覚を持ち、誠実なコミュニケーションを心がけることが大前提です。
また、継続的な運用が成果の鍵となるため、事前に担当者や運用体制をしっかりと計画しておく必要があります。
SNS採用は中小企業にも向いていますか?
はい、むしろ低コストで始められるSNS採用は、潤沢な採用予算を確保しにくい中小企業にこそ向いていると言えます。
大手企業にはない、独自の魅力や社長の人柄、風通しの良い社風などをダイレクトに伝えることで、大手との差別化を図り、共感に基づいたマッチングを実現することが可能です。
まとめ|SNS採用とは攻めと守りの設計が成功の鍵
本記事では、SNS採用の基礎から応用までを網羅的に解説してきました。
SNS採用とは、単なる求人情報の掲載ツールではありません。
企業の文化や働く人の魅力を積極的に発信し、潜在層にまでアプローチする「攻めの採用」を実現する強力な手法です。
低コストでの母集団形成や採用ブランディング強化といった大きなメリットがある一方で、炎上リスクや運用工数といった課題も存在します。
成功の鍵は、明確な目的・ペルソナ設定と継続的な情報発信という「攻めの設計」と、炎上を防ぐガイドライン策定や効果測定に基づく改善といった「守りの設計」の両輪をしっかりと回していくことです。
本記事が、貴社の採用活動を新たなステージへと引き上げる一助となれば幸いです。