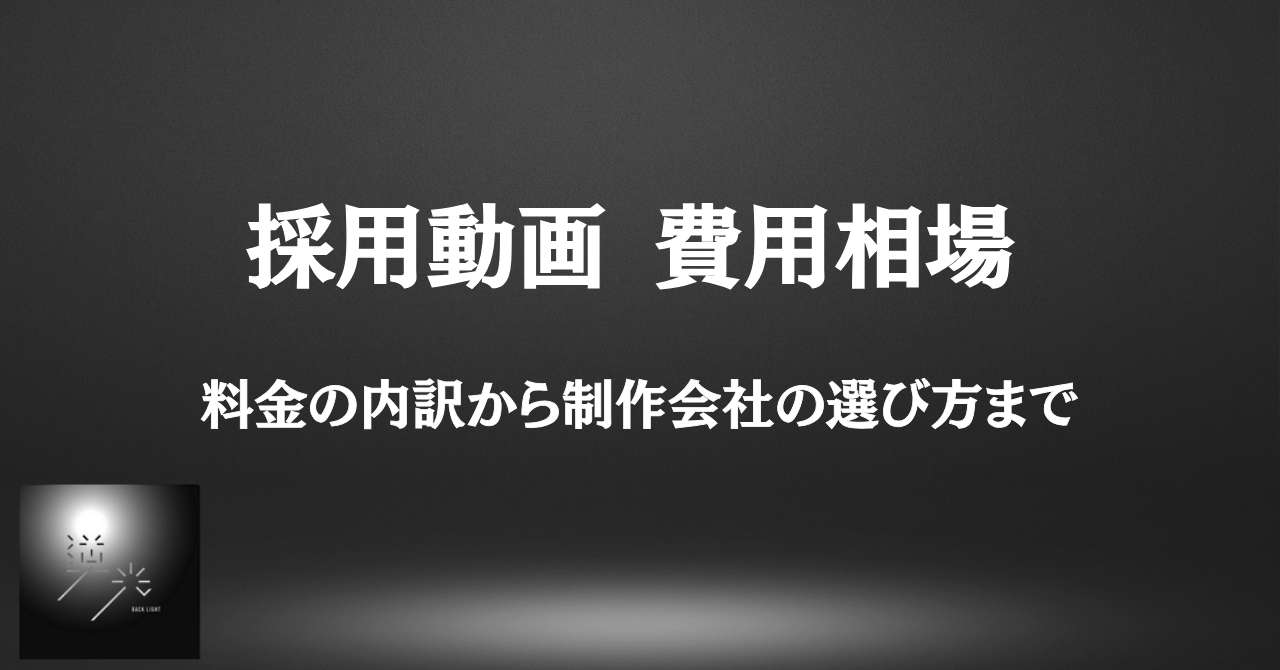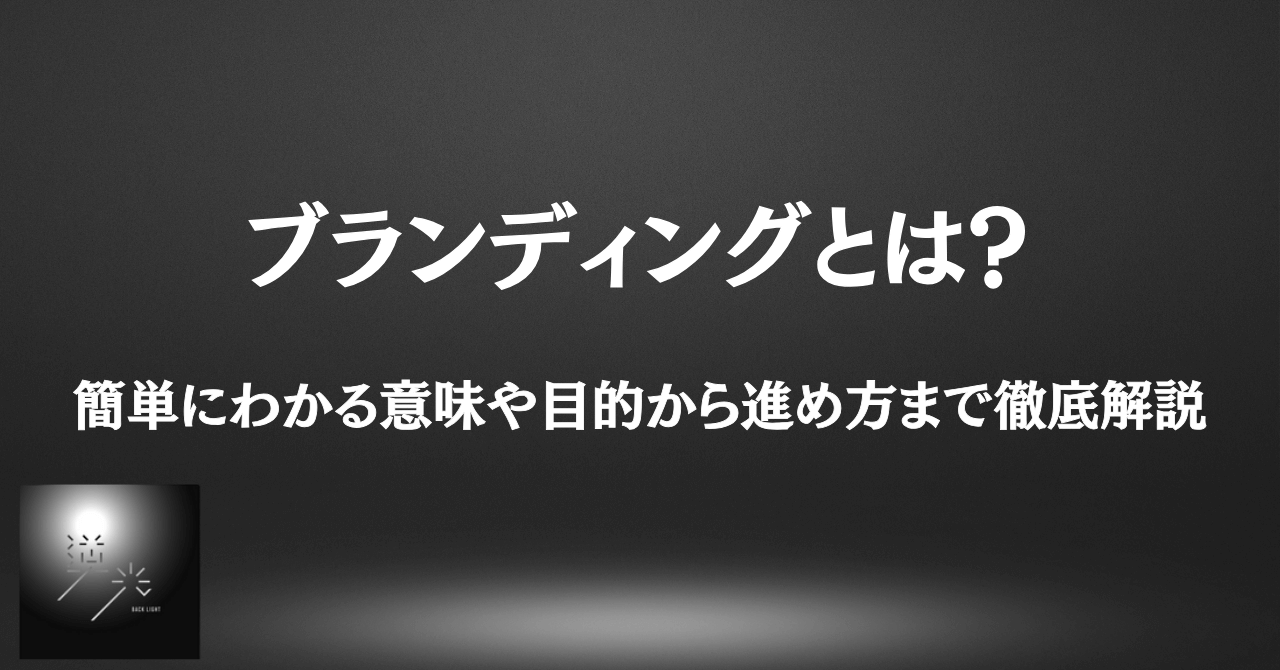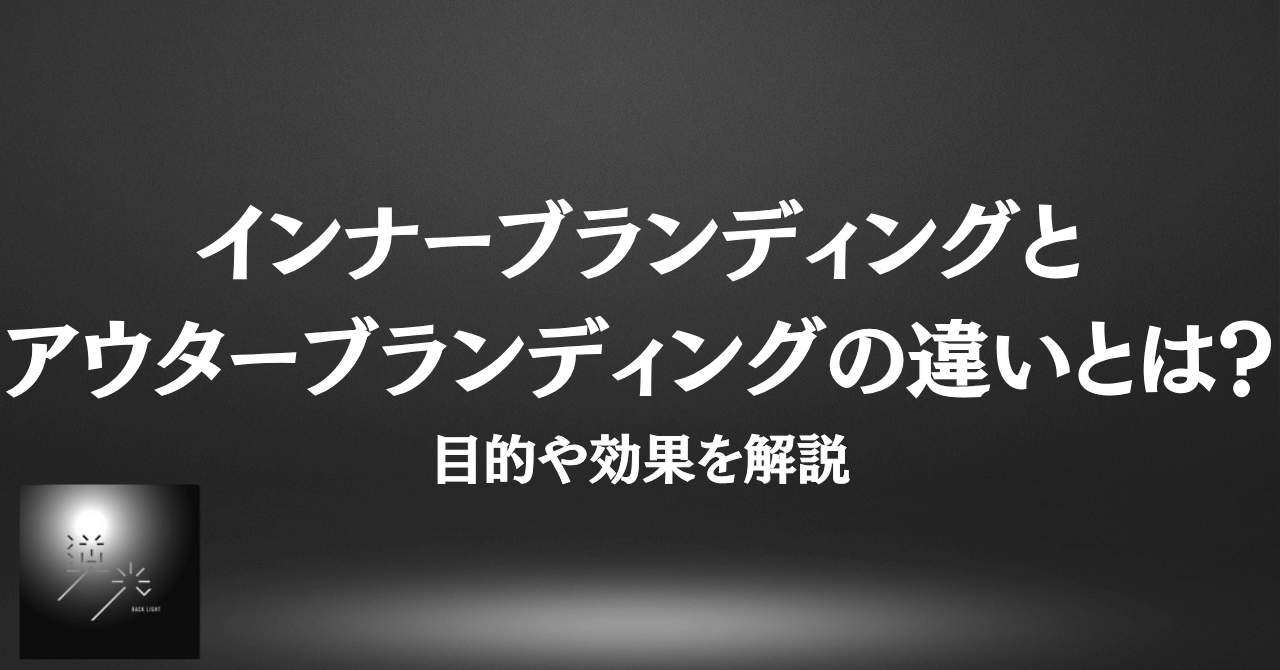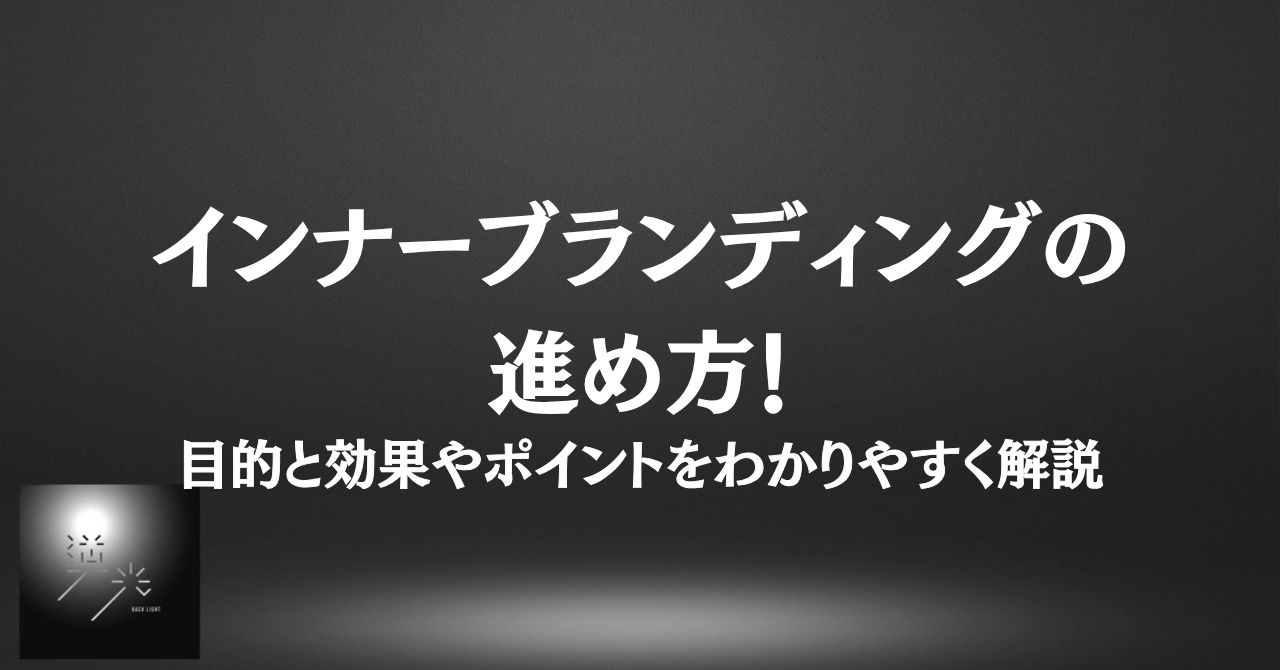「採用動画の制作には、一体いくらかかるのだろう?」 「料金の内訳はどうなっていて、何にどれくらいの費用が発生するのか知りたい」
このような疑問や悩みを抱えている採用担当者様は少なくありません。
採用動画の費用は、動画の種類やクオリティ、依頼する制作会社によって大きく変動するため、相場が分かりにくいのが実情です。
そこで本記事では、採用動画の費用相場や相場を左右する要素などを解説します。
ぜひ、貴社の採用活動を成功に導くために参考にしてください。
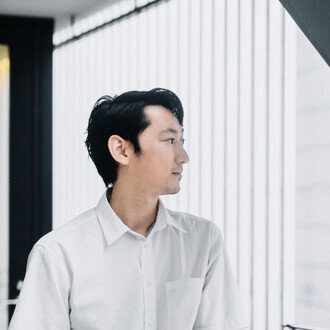
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
INDEX
採用動画の費用相場
採用動画の費用相場は、制作する動画の内容やクオリティによって大きく異なりますが、一般的には10万円から200万円以上と幅広い価格帯に分かれています。
ここでは、価格帯別にどのような採用動画が制作できるのか、その目安を具体的に解説します。
| 動画の種類 | 一般的な相場価格 |
|---|---|
| 商品・サービス紹介動画 | 50~100万円 |
| 会社・店舗・学校紹介動画マニュアル・HowTo・研修動画 | 50~100万円 |
| 新卒・中途採用動画 | 50~100万円 |
| 事例紹介・インタビュー動画 | 50~100万円 |
| セミナー・ウェビナー動画 | 30~80万円 |
| WebCM・動画広告 | 100~300万円 |
| マニュアル・HowTo・研修動画 | 30~80万円 |
| イベント動画 | 50~100万円 |
| 株主総会・IR動画 | 50~100万円 |
| 展示会動画 | 50~150万円 |
※引用:動画制作・映像制作の価格|東京の動画・映像制作会社フォーズン
採用動画の具体的な事例や制作のメリットについてはこちらをご参照ください。
→製造業の採用動画事例紹介!制作するメリットや動画制作会社の選び方を完全解説
10~30万円の相場
この価格帯では、主にシンプルな構成の採用動画が制作可能です。
例えば、社員1〜2名へのインタビュー動画や、スライドショー形式での会社紹介動画などが中心となります。
【制作できる動画の例】
- 社員インタビュー動画(1〜2名)
- 写真や既存の映像素材を組み合わせたスライドショー動画
- テンプレートを使用した簡易的なアニメーション動画
【制作のポイント】
- 撮影は1日以内で完了させることが多いです。
- ディレクターが撮影を兼任するなど、少人数のスタッフで対応します。
- 編集はカットやつなぎ、簡単なテロップやBGMの追加がメインとなります。
予算を最大限に抑えたい場合や、説明会用の補助的な映像コンテンツとして活用したい場合におすすめの価格帯です。
30~80万円の相場
この価格帯は、採用動画制作において最も一般的なボリュームゾーンと言えます。
オリジナリティのある企画を取り入れ、企業の魅力を多角的に伝えることが可能になります。
【制作できる動画の例】
- 複数の社員が登場するインタビュー動画
- オフィスや仕事風景を交えた会社紹介・事業紹介動画
- 1日の仕事の流れを追う密着風動画
- 簡単なドローン撮影を交えた映像
【制作のポイント】
- 企画・構成に時間をかけ、ターゲットに響くメッセージを設計します。
- ディレクター、カメラマン、音声など、専門スタッフによる撮影が可能です。
- オリジナルのグラフィックやアニメーションを取り入れた、凝った編集も実現できます。
企業の理念や社風、働く社員のリアルな声をしっかりと伝え、求職者の応募意欲を高めたい場合に最適な価格帯です。
80~200万円の相場
この価格帯では、企業のブランディング向上にも寄与する、より高品質で企画性の高い採用動画の制作が可能です。
テレビCMのようなクオリティや、求職者の感情に訴えかけるストーリー性のある動画を求める場合におすすめです。
【制作できる動画の例】
- ストーリー仕立てのドラマ風動画
- 社員の成長や挑戦を追うドキュメンタリー動画
- 高度なCGやアニメーションを駆使したコンセプトムービー
- プロの役者を起用した再現ドラマ
【制作のポイント】
- 著名なクリエイターや脚本家を起用した、戦略的な企画立案が行われます。
- 複数日にわたる撮影や、地方・海外でのロケーションにも対応可能です。
- 映画用機材を使用した撮影や、プロのナレーターによるナレーション、オリジナルの楽曲制作なども含まれます。
企業の認知度向上や、競合他社との明確な差別化を図りたい場合に適した価格帯です。
200万円以上の相場
この価格帯では、まさに「作品」と呼べるレベルの、最高品質の採用動画を制作できます。
企業のブランドイメージを決定づけるような、インパクトの大きい映像表現が求められる場合に選択されることが多いです。
【制作できる動画の例】
- 有名タレントや著名人を起用したブランディングムービー
- 大規模なセットや海外ロケを敢行するプロモーションビデオ
- 最先端のVFX(視覚効果)を駆使した映像作品
【制作のポイント】
- 広告代理店なども交えた、大規模なプロジェクトチームで制作に臨みます。
- Web広告やテレビCMなど、クロスメディアでの展開を前提とした映像戦略を立てます。
- 細部にまでこだわり抜いた、一切の妥協がないクリエイティブが追求されます。
採用活動の枠を超え、企業の存在価値を社会に広く伝えたいという、強いメッセージ性を持つ場合に検討される価格帯です。
採用動画の費用相場を左右する要素
採用動画の費用は、様々な要素が複雑に絡み合って決まります。
ここでは、相場を左右する主な要素を「動画タイプ」「制作工程」「制作体制」「追加オプション」の4つの観点から詳しく解説します。
動画タイプ別(会社紹介・インタビュー・ドキュメンタリー)
制作する動画のタイプによって、必要な撮影規模や編集工数が変わるため、費用も変動します。
インタビュー動画
比較的シンプルな構成のため、費用を抑えやすい傾向にあります。
しかし、インタビュアーのスキルや、撮影場所の雰囲気づくりが動画の質を大きく左右します。
会社紹介動画
オフィス風景、事業内容、社員の働く様子など、複数の要素を盛り込むため、インタビュー動画より費用は高くなるのが一般的です。
どこまでを映像化するかによって、撮影日数や編集工数が変わります。
ドキュメンタリー動画
特定のプロジェクトや社員に長期間密着するため、撮影期間が長くなり、費用も高額になる傾向があります。
膨大な撮影データからストーリーを紡ぎ出す、高度な編集技術が求められます。
アニメーション動画
実写撮影が不要なため、撮影費やロケーション費はかかりませんが、アニメーターの制作費が発生します。
アニメーションのクオリティや長さによって費用は大きく変動します。
かっこいい採用動画についてはこちらの記事で紹介しています。
→かっこいい採用動画の事例を紹介!作り方や制作するメリットなどを徹底解説!
制作工程別(企画・撮影・編集・ナレーション)
採用動画の制作費用は、主に以下の工程ごとの費用の積み上げで構成されています。
企画・構成費(ディレクション費)
動画の目的やターゲットをヒアリングし、どのようなストーリーや見せ方にするかを設計する費用です。
動画のクオリティを決定づける最も重要な工程であり、全体の費用の10%〜20%を占めるのが一般的です。
撮影費
カメラマンや音声、照明といった技術スタッフの人件費と、カメラやマイク、照明機材などの機材費で構成されます。
撮影日数やスタッフの人数、使用する機材のグレードによって費用が変動します。
編集費
撮影した映像素材をカットし、テロップやBGM、効果音などを加えて1本の動画に仕上げる費用です。
編集の複雑さ(アニメーションやCGの有無など)や、動画の尺によって費用が変わります。
ナレーション・MA(音響効果)費
プロのナレーターにナレーションを依頼する場合の費用や、BGM・効果音の選定・調整を行うMA(Multi Audio)スタジオの使用料などです。
ナレーターの知名度や拘束時間によって費用が変動します。
撮影日数・ロケ地・キャスト・CG/アニメーションの追加料金
基本的な制作費に加えて、以下の要素は追加料金として費用に上乗せされることが一般的です。
| 項目 | 内訳 |
| 撮影日数・ロケ地 | 撮影が複数日にわたる場合や、遠方のロケ地で撮影を行う場合は、スタッフの拘束時間や交通費・宿泊費が追加で発生します。 |
| キャスト(役者) | 社員ではなくプロの役者を起用する場合、キャスティング費用や出演料が必要になります。タレントの知名度によって費用は大きく異なります。 |
| CG/アニメーション | 動画内に高度なCGやオリジナルのアニメーションを取り入れる場合、専門のクリエイターによる制作費が別途かかります。表現の複雑さによって費用は大きく変動します。 |
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用動画の制作会社 vs 内製の費用差
採用動画は制作会社に外注するだけでなく、自社で制作(内製)することも可能です。
採用動画を制作する際の「外注」と「内製」の比較表を以下に示します。
| 項目 | 制作会社に外注する場合 | 自社で内製する場合 |
| メリット | ・企画から納品まで一貫して任せられ、高品質な動画を効率的に制作できる。・担当者の工数削減、プロのノウハウ活用。 | ・制作会社に支払う費用は発生しない。・長期的に多くの動画を制作する場合、コストメリットが出る可能性がある。 |
| デメリット | ・撮影機材や編集ソフトの購入費用、制作担当者の人件費(学習コスト含む)がかかる。・クオリティの担保や制作ノウハウの蓄積が課題。 | ・制作費がかかる。 |
採用動画の費用を安く抑えるポイント
「品質は落としたくない、でも費用はできるだけ抑えたい」というのが担当者様の本音ではないでしょうか。
ここでは、採用動画のクオリティを維持しつつ、費用を賢く抑えるための4つのポイントをご紹介します。
企画精度を高めてリテイクを防ぐ
制作途中の仕様変更や、完成間近での大幅な修正(リテイク)は、追加費用の最も大きな原因となります。
これを防ぐためには、制作開始前の「企画」段階が非常に重要です。
- 動画の目的を明確にする
- ターゲットを具体的に描く
- 伝えたいメッセージを絞る
これらの点を事前に社内で十分に議論し、制作会社と密に共有することで、認識のズレを防ぎ、手戻りのないスムーズな制作進行が可能になります。
採用戦略全体の構築についてはこちらをご参照ください。
→採用戦略の成功事例!フレームワークを活用した作り方や戦略の立て方を分かりやすく徹底解説!
撮影スケジュールを最適化する
撮影にかかる費用は、スタッフの拘束時間(日数)に大きく左右されます。
撮影スケジュールを効率化することで、コストを大幅に削減できる可能性があります。
- 撮影日を1日に集約する
- 撮影場所を社内に限定する
- 出演者のスケジュールを事前に確保する
助成金・補助金・支援施策の活用
国や地方自治体は、企業の採用活動やDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援するための様々な助成金・補助金制度を用意しています。
これらの制度を活用することで、採用動画の制作費用の一部が補助される場合があります。
制度の内容や対象条件は年度によって変更されるため、厚生労働省や中小企業庁、各自治体のウェブサイトで最新の情報を確認することをおすすめします。
既存素材の再利用とテンプレ活用
ゼロからすべてを制作するのではなく、今ある資産を有効活用することもコスト削減につながります。
- 既存素材の活用
- テンプレートの活用
などでコストの削減が可能です。
採用動画の費用で失敗しない制作会社の選び方と注意点
採用動画の成否は、パートナーとなる制作会社選びにかかっていると言っても過言ではありません。
ここでは、数ある制作会社の中から自社に最適な一社を見つけ出すためのポイントと、契約時の注意点を解説します。
制作会社の選び方についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
→採用動画の外注とは?費用相場から制作会社の選び方や成功のポイントまで解説
見積もり比較のチェックポイント10項目
複数の制作会社から見積もりを取る「相見積もり」は必須です。
その際、 総額の安さだけで判断するのではなく、以下の10項目を細かくチェックしましょう。
| 項目 | チェックポイント |
| 費用の内訳 | 「一式」ではなく、項目別に料金が記載されているか(企画費、撮影費、編集費など) |
| 単価の妥当性 | 各項目の単価(人件費、機材費など)が相場から大きく外れていないか |
| 制作体制 | スタッフの人数と役割(ディレクター、カメラマンなど)が明記されているか |
| 修正回数 | 編集の無料修正回数と、それ以降の追加料金が明記されているか |
| 音源費用 | BGMやナレーションの費用が含まれているか、別途必要か |
| 納品・納期 | 希望するファイル形式と納期が記載されているか |
| 諸経費 | 交通費や宿泊費などの諸経費が、見積もりに含まれているか、実費精算か |
| 著作権 | 著作権の帰属について明記されているか |
| 二次使用 | 二次使用の範囲と料金について明記されているか |
| 担当者の対応 | 見積もり依頼時のレスポンスの速さや、質問への回答が丁寧か |
契約時の注意点・条件(著作権・二次使用・追加費用)
見積もりの内容に納得し、発注する前には必ず契約書の内容を確認しましょう。
特に以下の3点は、後々のトラブルを防ぐために重要です。
著作権の帰属
制作した動画の著作権が、発注側(自社)に譲渡されるのか、それとも制作会社に帰属するのかを必ず確認しましょう。
一般的には「著作権譲渡」の契約を結ぶことが多いですが、追加料金が発生する場合もあります。
著作権が制作会社にある場合、動画の一部を切り出して別の用途で使うことなどが制限される可能性があります。
二次使用の範囲
制作した動画を、当初の目的(例:採用サイトへの掲載)以外で使用(二次使用)する場合の条件を確認します。
例えば、SNS広告や展示会、営業資料などで使用する場合に追加料金が発生するのか、そもそも使用が許可されているのかを明確にしておきましょう。
追加費用の発生条件
契約範囲を超える作業を依頼した場合、どのような条件で追加費用が発生するのかを事前に確認しておくことが重要です。
「急な撮影日の変更」「大幅な企画内容の変更」「規定回数以上の修正」などが該当します。
制作実績・サポート体制・アフターケアの比較
料金や契約条件だけでなく、制作会社の「実績」と「体制」も比較検討の重要な軸となります。
| 項目 | 確認事項 |
| 制作実績 | ・自社が作りたい動画のテイスト(かっこいい系、温かい系など)と合っているか? ・ 同業他社の採用動画を手がけた実績はあるか? ・動画のクオリティは、見積もり金額に見合っているか? |
| サポート体制 | ・企画段階から親身に相談に乗ってくれるか? ・専門用語を使わず、分かりやすく説明してくれるか? ・レスポンスは迅速で、柔軟な対応を期待できるか? |
| アフターケア | ・納品後の動画の活用方法についてアドバイスをくれるか? ・視聴データに基づいた効果測定や、改善提案をしてくれるか? ・動画のマイナーチェンジ(テロップ修正など)に安価で対応してくれるか? |
これらの点を総合的に比較し、長期的なパートナーとして信頼できる制作会社を選びましょう。
採用動画の外注時に押さえておくべき実務的なポイント
制作会社を選んだ後、実際に発注する際には以下の点にも注意しましょう。
ターゲット像の事前共有
誰に見てもらいたい動画なのかを制作会社と明確に共有することが重要です。
- 新卒採用向けか、中途採用向けか
- どの職種・部署をターゲットにするか
- 求める人物像やスキルレベル
ターゲットが曖昧なまま制作を進めると、伝えたいメッセージがぼやけ、効果的な動画になりません。
出演者の事前調整
社員に出演してもらう場合、以下の点を事前に調整しておきましょう。
- 出演者のスケジュール確保
- 出演承諾書の取得
- 退職後の動画使用に関する取り決め
- 出演者への事前説明(撮影の流れ、所要時間など)
特に「退職後も動画を使用できるか」は、後々トラブルになりやすいポイントです。
契約書で明確にしておきましょう。
撮影当日の準備事項
撮影をスムーズに進めるため、以下を事前に準備しておくことをおすすめします。
- 撮影場所の確保と整理整頓
- 社内への撮影告知(他の社員への配慮)
- 出演者の服装指定(ある場合)
- 会社ロゴデータなど必要素材の提供
準備不足により撮影が予定通り進まないと、追加費用が発生する可能性があります。
採用動画で起こりがりがちな失敗事例と改善策
ここでは、採用動画制作でよくある失敗事例とその改善策を3つのケースでご紹介します。
同じ失敗をしないようあらかじめリスクを想定しておきましょう。
予算オーバーで社内稟議が停滞したケース
当初の見積もりは安かったものの、制作を進めるうちにあれもこれもと要望を追加。
最終的に予算を大幅に超過してしまい、社内稟議が通らずプロジェクトが頓挫してしまうケース。
このような採用動画制作における失敗を避ける策として、まず要件定義の徹底が挙げられます。
このような対策方法としては制作開始前に、動画で「やること」と「やらないこと」を明確に線引きすることで、後の工程での手戻りや追加費用の発生を防ぐことです。
視聴者離脱率が高く効果が出なかったケース
社長のメッセージや企業の沿革など、企業側が伝えたい情報ばかりを詰め込んだ結果、求職者にとっては退屈な動画に。
視聴維持率が低く、誰にも最後まで見てもらえなかった。
このような視聴者離脱率が高く効果が出なかったケースへの改善策として、まずターゲット視点の徹底が不可欠です。
「求職者は何を知りたいか?」という視点で企画を立て、社員のリアルな声や入社後のキャリアパス、職場の雰囲気など、求職者が本当に求める情報を提供することが重要です。
採用動画の費用相場に関するよくある質問
最後に、採用動画の費用に関して多くの担当者様から寄せられる質問とその回答をまとめました。
採用動画の標準的な制作期間は?
制作する動画の内容によって大きく異なりますが、一般的には企画開始から納品まで1.5ヶ月〜3ヶ月程度を見ておくと良いでしょう。
- 企画・構成: 2〜4週間
- 撮影準備・撮影: 1〜2週間
- 編集・修正: 2〜4週間
- MA・納品: 1週間
特に、企画工程は動画の土台となるため、時間をかけて丁寧に進めることが重要です。
タイトなスケジュールで制作を依頼すると、その分費用が割高になる可能性もあります。
採用動画の効果測定とポイントについてはこちらで詳しく解説しています。
→採用動画の効果とは?最大化するポイントと成功事例3選を完全解説
採用動画と採用パンフレット、どちらが費用対効果が高い?
一概には言えませんが、長期的な視点で見ると採用動画の方が費用対効果は高いと言えるケースが多いです。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、目的やターゲットに応じて両者を使い分けるのが最も効果的です。
採用動画を内製化するメリット・デメリットは?
採用動画の内製化には、以下のようなメリットとデメリットがあります。
| 項目 | メリット | デメリット |
| コスト | 長期的に見れば、外注費を削減できます。 | 初期投資(機材・ソフト購入費、担当者の学習コスト含む)がかかります。 |
| 制作スピード | 社内の判断でスピーディーに制作・修正が可能です。 | 担当者の制作時間という工数が発生します。 |
| ノウハウ・知見 | 社内に動画制作の知見が溜まります。 | プロのクオリティに達するには専門的な知識と技術が必要です。 |
| 企画力・客観性 | – | 客観的な視点が欠け、独りよがりな内容になりがちです。 |
まずは簡単な社員インタビューなどから内製を始め、本格的なブランディング動画はプロに依頼するなど、ハイブリッドで進めるのも一つの手です。
見積もりが適正かどうかを判断する基準は?
見積もりの適正さを判断するには、以下の基準でチェックすることをおすすめします。
- 相見積もりを取る
- 内訳の具体性
- 制作実績とのバランス
- 担当者の説明
これらの基準を元に総合的に判断することで、不当に高い、あるいは安すぎて品質が不安な見積もりを避け、適正な価格で依頼することができます。
まとめ|採用動画の費用相場を知り最適な予算計画から始めよう
本記事では、採用動画の費用相場を中心に、料金の内訳、コストを抑えるポイント、そして失敗しない制作会社の選び方までを網羅的に解説しました。
採用動画の費用は10万円から200万円以上と非常に幅広く、その価格は「動画のタイプ」「制作工程」「クオリティ」によって決まります。
重要なのは、単に価格の安さだけで判断するのではなく、「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」という目的を明確にし、その目的を達成するために最適な予算と制作会社を選ぶことです。
この記事でご紹介した内容を参考に、まずは自社が採用動画にかけられる予算と、実現したい動画のイメージを具体的にしてみてください。
そして、信頼できるパートナーとなる制作会社を見つけ、共に採用活動を成功へと導く一本を創り上げましょう。