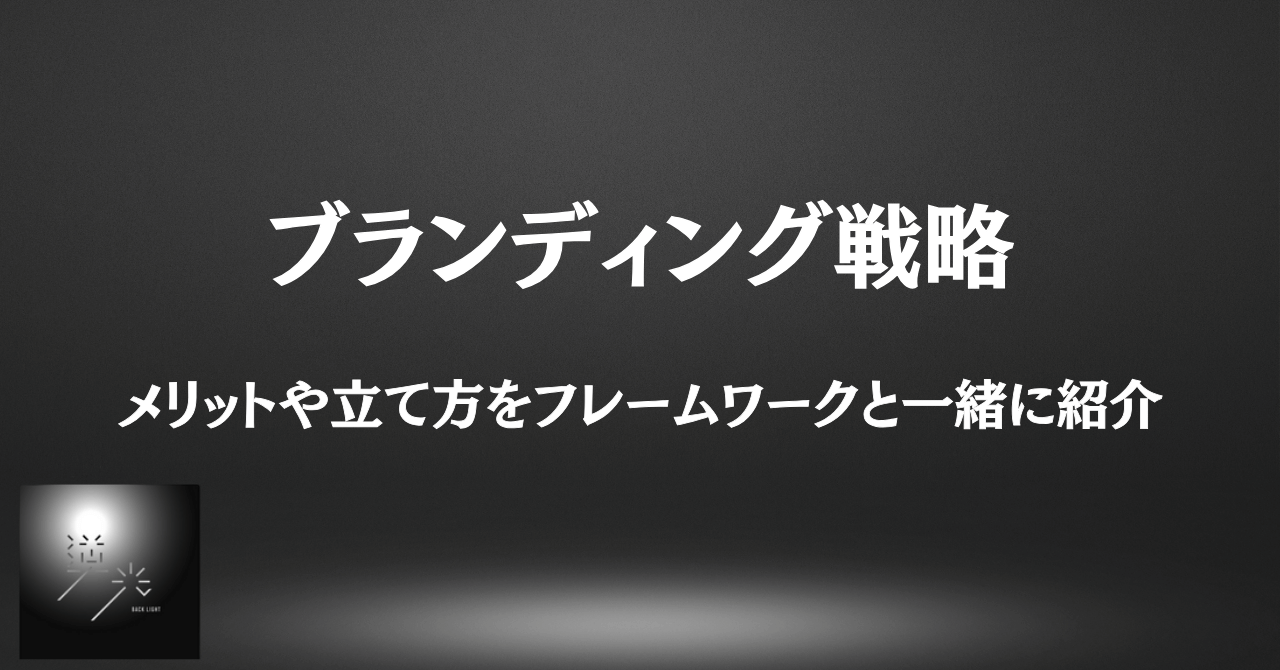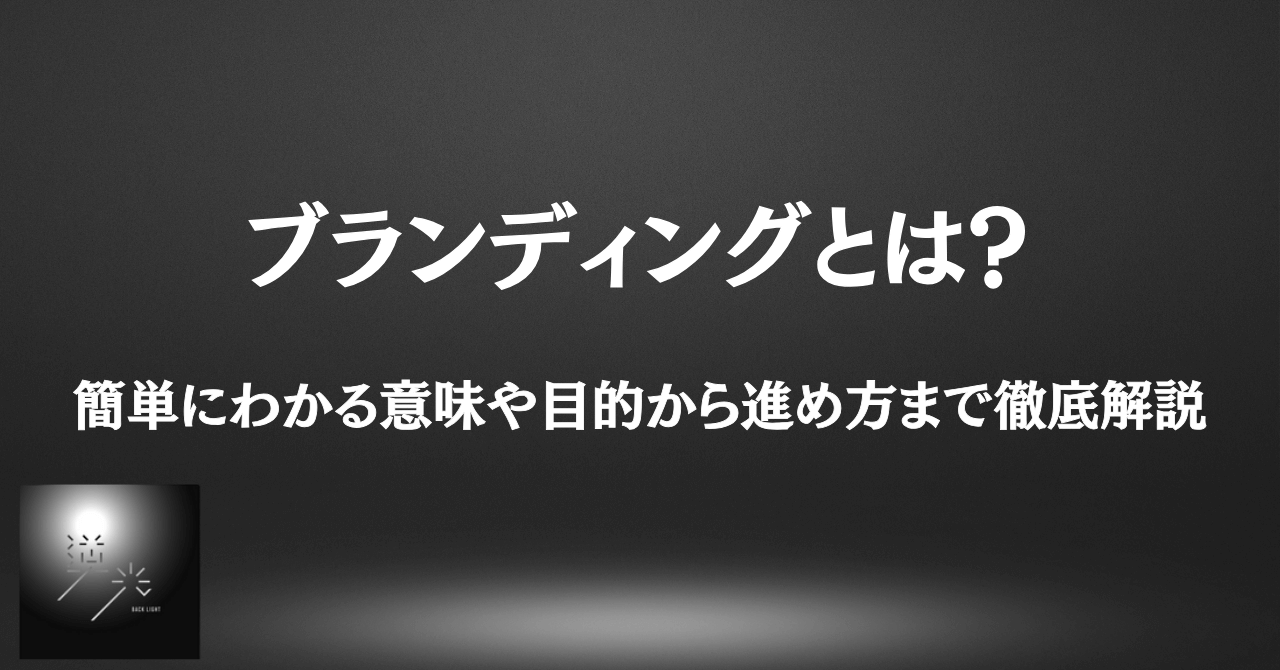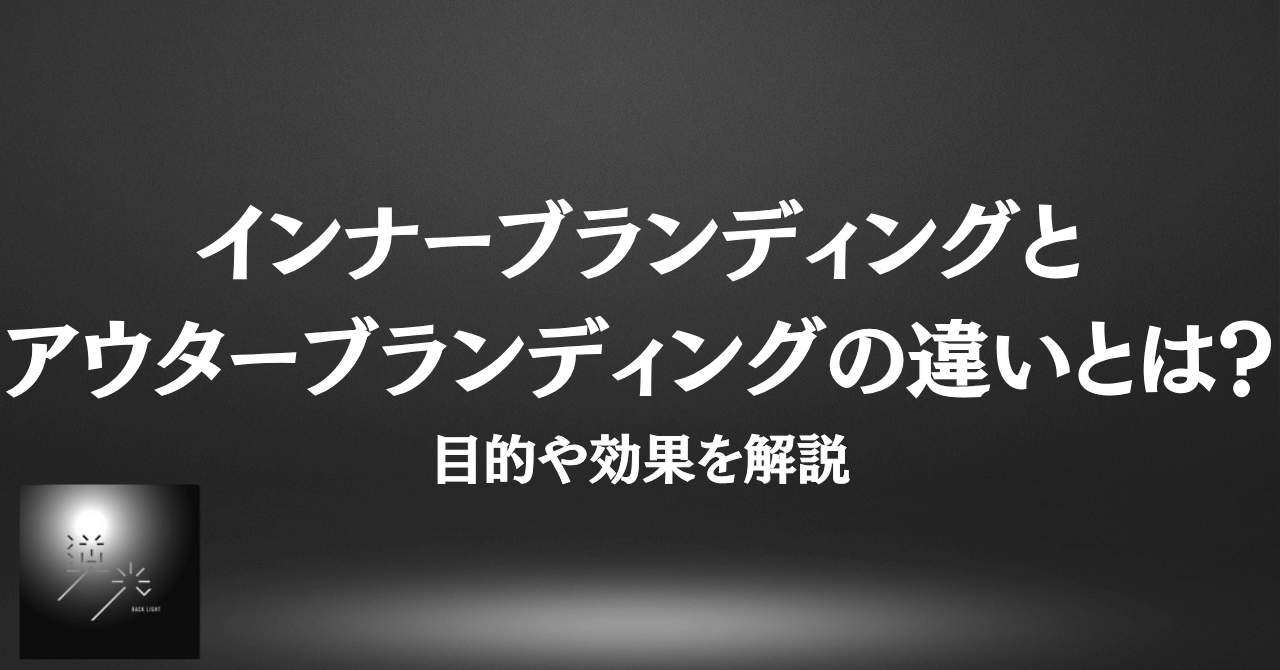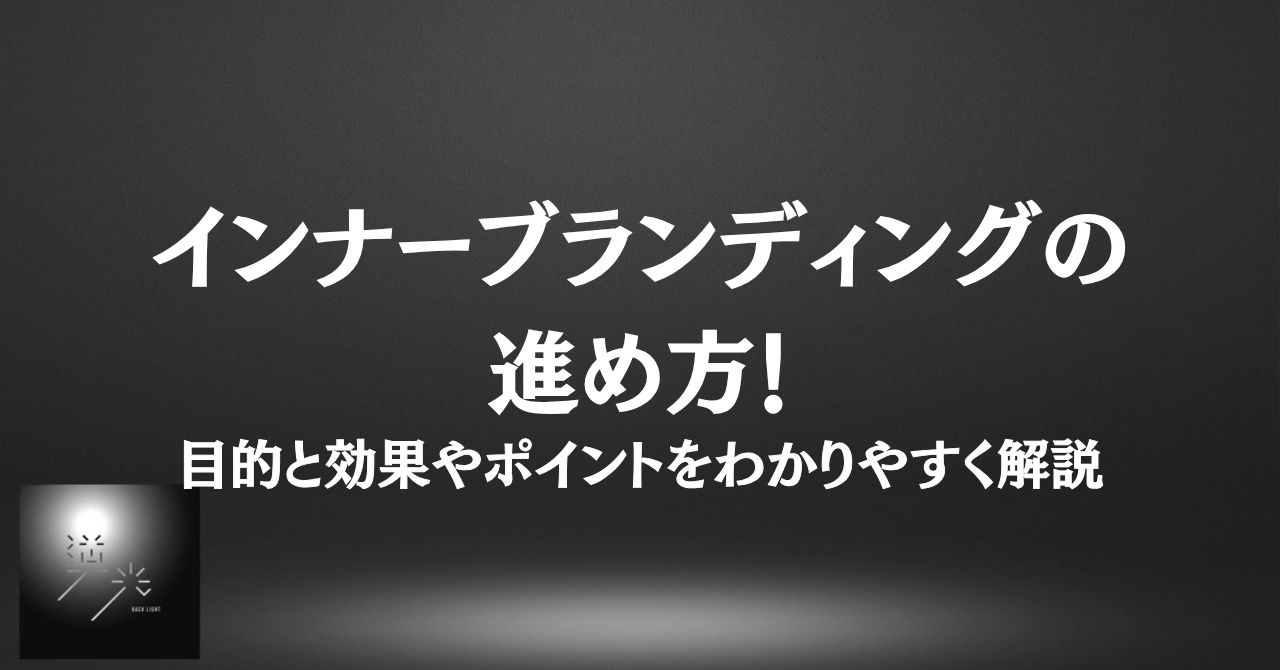「企業の知名度や待遇だけでは、求める人材からの応募が集まらない」と感じていませんか。
現代の採用市場は、労働人口の減少と働き方の多様化により、企業が求職者から「選ばれる」時代へと変化しています。
このような状況で重要性を増しているのが「採用ブランディング」です。
本記事では、採用ブランディングの基本的な意味や目的から、具体的な進め方、成功のポイント、そして先進企業の事例までを網羅的に解説します。
採用活動に課題を感じている担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
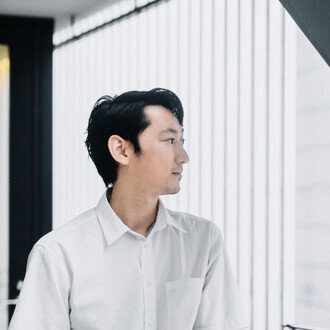
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
INDEX
採用ブランディングとは?
採用ブランディングとは、企業の理念や文化、働く環境といった魅力を定義し、それを求職者や社会に継続的に発信することで、自社を「理想の就職先」として認知してもらうための戦略的な活動全般を指します。
単に求人広告を出すといった短期的な採用活動とは異なり、長期的な視点で企業価値そのものを高め、ファンを増やしていくイメージです。
この活動が今重要視されている背景には、以下のような社会的な変化があります。
| 要因 | 説明 |
| 労働人口の減少 | 少子高齢化により、働き手の数が年々減少しており、人材獲得競争が激化しています。 |
| 働き方の多様化 | テレワークの普及や副業の解禁など、人々が仕事に求める価値観は多様化しています。給与や待遇だけでなく、「働きがい」や「企業文化への共感」が重視されるようになりました。 |
| 情報の透明化 | 口コミサイトやSNSの普及により、企業のリアルな情報が簡単に手に入るようになりました。求職者は多角的な情報から、自分に合った企業を慎重に選んでいます。 |
このような状況下で、企業は自社の魅力を明確に言語化し、積極的に発信していかなければ、求職者の目に留まることすら難しくなっています。
採用ブランディングは、この厳しい採用市場を勝ち抜くための不可欠な採用戦略なのです。
採用戦略の作り方についてはこちらをご参照ください。
→採用戦略の成功事例!フレームワークを活用した作り方や戦略の立て方を分かりやすく徹底解説!
採用ブランディングの目的
採用ブランディングは、単に応募者を集めることだけが目的ではありません。
その先にある、企業の持続的な成長を見据えた2つの大きな目的があります。
応募者数・質を向上させる狙い
採用ブランディングの第一の目的は、採用したいターゲット人材からの応募を、数と質の両面で向上させることです。
自社のビジョンや事業の社会性、独自のカルチャーといった魅力を発信し続けることで、これまで企業の存在を知らなかった潜在的な候補者層にもアプローチできます。
これにより、自然と応募者の母集団形成、つまり「数」の増加につながります。
さらに重要なのが「質」の向上です。
発信するメッセージに共感した人材、つまり企業の価値観や文化にフィットした人材が集まりやすくなります。
スキルや経験がマッチしているだけでなく、「この会社で働きたい」という強い動機を持った候補者が増えるため、選考の精度が高まり、結果的に入社後のミスマッチを大幅に減らすことができるのです。
社員エンゲージメントと定着率への影響
採用ブランディングは、社外へのアピールだけでなく、社内に向けてもポジティブな影響を与え、社員エンゲージメントと定着率の向上に貢献します。
自社の強みや社会的な存在価値を改めて言語化し、発信するプロセスを通じて、既存の社員は自分たちの働く会社に対する理解を深め、誇りや愛着を再認識します。
これが「エンゲージメント(仕事に対する熱意や貢献意欲)」の向上につながります。
エンゲージメントが高い社員は、仕事へのパフォーマンスが高いだけでなく、離職する可能性が低いことが分かっています。
また、自社の魅力を自らの言葉で語れるようになるため、リファラル採用(社員紹介)の活性化にもつながり、採用活動全体に好循環を生み出します。
採用ブランディングのメリット
採用ブランディングに取り組むことで、企業と求職者の双方に多くのメリットが生まれます。
ここでは、特に重要な3つの観点からその効果を解説します。
企業側に得られる5つの効果
採用ブランディングを推進することで、企業は主に以下の5つの効果を得ることができます。
ミスマッチの減少と定着率の向上
企業文化や働き方のリアルな情報を事前に伝えることで、求職者は入社後の姿を具体的にイメージできます。
これにより、「こんなはずではなかった」というミスマッチが減り、社員の定着率向上に直結します。
採用コストの削減
企業の魅力が浸透し、指名での応募が増えることで、高額な求人広告や人材紹介サービスへの依存度を下げることができます。詳細は後述します。
応募者数の増加
企業の認知度が向上し、働く場所としての魅力が伝わることで、これまでアプローチできていなかった層からも応募が集まるようになります。
求める人材からの応募増加
ターゲットとして設定したペルソナに響くメッセージを発信することで、スキルや価値観が自社にマッチした、質の高い候補者からの応募が増加します。
社員のエンゲージメント向上
社外への魅力発信は、インナーブランディングの効果も持ちます。社員が自社の価値を再認識し、誇りを持つことで、組織全体の活性化につながります。
応募者側に感じられる価値
採用ブランディングは、求職者にとっても企業選びの精度を高めるという大きな価値を提供します。
企業選びの判断軸が明確になる
給与や事業内容だけでなく、社風や価値観といった定性的な情報が得られるため、自分に合った企業かどうかを多角的に判断できます。
入社後の働き方を具体的にイメージできる
社員インタビューや一日の仕事を紹介する動画などを見ることで、自分がその企業で働く姿をリアルに想像できます。
情報の信頼性が高い
企業から直接発信されるリアルな情報に触れることで、口コミサイトだけでは分からない企業の本当の姿を知ることができます。
自身のキャリアと企業のマッチ度を判断できる
企業が求める人物像やキャリアパスが明確であるため、自身のキャリアプランと照らし合わせやすくなります。
採用コスト削減の仕組み
採用ブランディングが採用コストの削減につながる仕組みは、主に以下の3点です。
広告費への依存度低下
企業のファンが増え、公式サイトやSNSからの直接応募(ダイレクトリクルーティング)や、指名検索による応募が増加します。
これにより、多額の費用がかかる求人広告媒体への出稿を減らすことができます。
リファラル採用の活性化
社員エンゲージメントが高まることで、社員が自社の魅力を友人や知人に自信を持って伝え、紹介してくれるようになります。
リファラル採用は、他の採用手法に比べて一人あたりの採用単価(CPA)が低い傾向にあります。
採用プロセスの効率化
自社への理解度が高い候補者が増えるため、選考途中での辞退率が低下します。
これにより、面接官の工数や再募集にかかるコストを削減できます。
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
採用ブランディングの進め方4ステップ
採用ブランディングは、思いつきで始めても成功しません。戦略的に、段階を踏んで進めることが重要です。
ここでは、実践的な4つのステップに分けて、その進め方とポイントを解説します。
ステップ1:現状分析とペルソナ設定
最初のステップは、自社の立ち位置を正確に把握し、誰にメッセージを届けたいのかを定義することです。
まずは、自社を取り巻く環境を客観的に分析します。
フレームワークとしては「3C分析」が有効です。
- 自社(Company): 自社の強み・弱みは何か?
- 競合(Competitor): 競合他社はどのような採用メッセージを発信しているか?
- 求職者(Customer/Candidate): 求職者は企業に何を求めているか?
分析結果をもとに、自社の魅力を具体的に洗い出します。
経営層だけでなく、様々な部署や年次の社員にヒアリングやアンケートを行い、「自社らしさ」とは何かを多角的な視点から集めることが重要です。
次に、どのような人材に来てほしいのか、その人物像を具体的に描きます。
これを「採用ペルソナ」と呼びます。
年齢や性別、スキルといった基本情報だけでなく、価値観、キャリアへの考え方、情報収集の方法といった内面まで詳細に設定することで、メッセージがぶれなくなります。
ステップ2:EVP設計とメッセージ開発
次に、洗い出した自社の魅力を、ペルソナに響く「価値」として再定義し、伝わる言葉に変換していきます。
EVPとは「企業が従業員に提供できる価値」のことです。
ステップ1で洗い出した魅力を整理し、「自社で働くことで、従業員はどのような素晴らしい経験や報酬を得られるのか」を定義します。
EVPは一般的に以下の5つの要素で構成されます。
- 機会(Opportunity): キャリアアップ、成長の機会
- 人(People): 経営者や同僚の魅力、組織風土
- 組織(Organization): 企業のビジョン、社会貢献性
- 仕事(Work): 仕事のやりがい、面白さ
- 報酬(Reward): 金銭的報酬、福利厚生
設計したEVPを核として、採用活動全体で一貫して使用するコンセプトやタグライン(キャッチコピー)を開発します。
ペルソナの心に刺さり、覚えやすく、自社らしさが伝わる言葉を選ぶことがポイントです。
採用コンセプト開発の詳しい方法についてはこちらで解説しています。
→採用コンセプトの作り方5ステップ!失敗しないポイントまで徹底解説
ステップ3:サイト・SNS・動画など施策設計
コンセプトが決まったら、それを具体的にどのような手法で発信していくかを計画します。
ペルソナが普段どのようなメディアに接触しているかを考慮して、最適なチャネルを選びましょう。
Tiktok採用についてはこちらの記事をご覧下さい。
→Tiktok採用とは?成功事例やメリットデメリットを網羅的に解説
ステップ4:実行と改善サイクルの回し方
施策は実行して終わりではありません。
効果を測定し、改善を繰り返す「PDCAサイクル」を回すことが、採用ブランディングを成功させる上で最も重要です。
施策の効果を客観的に測るための指標(KPI)を設定します。
設定したKPIを定期的に観測し、どの施策が効果的で、どこに課題があるのかを分析します。
Google Analyticsや各SNSの分析ツールを活用しましょう。
分析結果に基づき、仮説を立てて改善策を実行します。
例えば、「ブログ記事からの応募が少ない」のであれば、「記事のテーマを変える」「CTA(行動喚起)ボタンの配置を見直す」といった対策を講じ、その結果をまた測定します。
このサイクルを粘り強く回し続けることが成功への鍵です。
採用ブランディングの成功事例
ここでは、採用ブランディングに成功している企業の具体的な事例を4社紹介します。
各社がどのように自社の魅力を発信しているのか、そのポイントを見ていきましょう。
株式会社エイチーム
多岐にわたる事業を展開する株式会社エイチームは、「経営理念への共感」を軸とした採用ブランディングを徹底しています。
「みんなで幸せになろうぜ」という経営理念のもと、社員一人ひとりが主体的に経営に参加する文化を発信。
独自の福利厚生やオープンな社風を伝えることで、理念に共感し、共に成長したいと考える熱意ある人材の獲得に成功しています。
参考:大切にしていること | 株式会社エイチームホールディングス(Ateam Holdings Co., Ltd.)
株式会社メルカリ
フリマアプリで知られる株式会社メルカリは、「Go Bold(大胆にやろう)」をはじめとする3つのバリュー(価値観)を採用の中心に据えています。
バリューを体現する社員の行動やカルチャーを、技術ブログやイベント登壇などを通じて積極的に発信。
特にエンジニア採用においては、高い技術力と挑戦的な文化をアピールすることで、世界中から優秀な人材を集めることに成功しています。
参考: Culture | 株式会社メルカリ – 採用情報
さらに多くの成功事例を見たい場合はこちらをご参照ください。
→採用ブランディングの成功事例10選!メリットと戦略を徹底解説
採用ブランディングに関してよくある質問
最後に、採用ブランディングに関して多く寄せられる質問にお答えします。
採用ブランディングを始めるには?
まずは「現状分析とペルソナ設定」から始めるのが第一歩です。
いきなり大規模な施策を打つ必要はありません。
まずは社内の数人でチームを組み、「自社の本当の魅力は何か?」「どんな人に仲間になってほしいか?」を話し合うことから始めてみましょう。
社員アンケートを実施して、自社の強みや改善点を洗い出すのも有効なスモールスタートです。
採用ブランディングと採用マーケティングの違いは?
この2つは密接に関連していますが、目的と時間軸に違いがあります。
| 採用ブランディング | 採用マーケティング | |
| 目的 | 企業の魅力を定義・発信し、共感を醸成することで、自社を「選ばれる存在」にする | 求職者の認知から応募・採用までの各プロセスを最適化する |
| 時間軸 | 長期的 | 短期的 |
| 位置づけ | 戦略(企業のファンを作る活動) | 戦術(見込み客を具体的な応募・採用につなげるための手法) |
採用ブランディングという強固な土台があってこそ、採用マーケティングの各施策が最大限の効果を発揮します。
ブランディング全般についてさらに詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
→ブランディングとは?簡単にわかる意味や目的から進め方まで徹底解説
中小企業でも取り組める?
はい、むしろ中小企業にこそ採用ブランディングは有効です。
知名度や資本力で大企業に劣る中小企業でも、独自の強みを打ち出すことで差別化が可能です。
- 経営層との距離の近さ
- 意思決定の速さ
- アットホームな社風
- ニッチな分野での高い技術力
地域社会との密接な関わり このような中小企業ならではの魅力を丁寧に発信することで、大企業にはない価値を求める優秀な人材に響きます。
SNSやブログなど、コストをかけずに始められる施策もたくさんあります。
中小企業の採用ブランディング戦略についてはこちらで詳しく解説しています。
→中小企業の採用ブランディングとは?成功事例と戦略で人材獲得を加速しよう
採用ブランディングの必要性は?
結論として、現代の採用市場において、採用ブランディングは「必要不可欠」です。
労働人口が減少し、求職者が優位な「売り手市場」が続く中で、企業は求職者から選ばれるための努力をしなければ、人材獲得はますます困難になります。
採用ブランディングは、目先の採用課題を解決するだけでなく、ミスマッチを防いで社員の定着率を高め、ひいては企業全体の価値を向上させる、持続的な成長のための投資なのです。
採用ブランディングのまとめ
本記事では、採用ブランディングの目的やメリット、具体的な進め方から成功事例までを詳しく解説しました。
採用ブランディングは、単なる採用テクニックではありません。
自社は社会にどのような価値を提供し、社員はそこで働くことにどのような誇りを持てるのか。
その本質的な問いに向き合い、自社の魅力を再発見し、一貫したメッセージとして発信し続ける、長期的で戦略的な活動です。
厳しい採用環境を勝ち抜き、企業の未来を担う人材と出会うために、まずは自社の魅力について、同僚と語り合うことから始めてみてはいかがでしょうか。