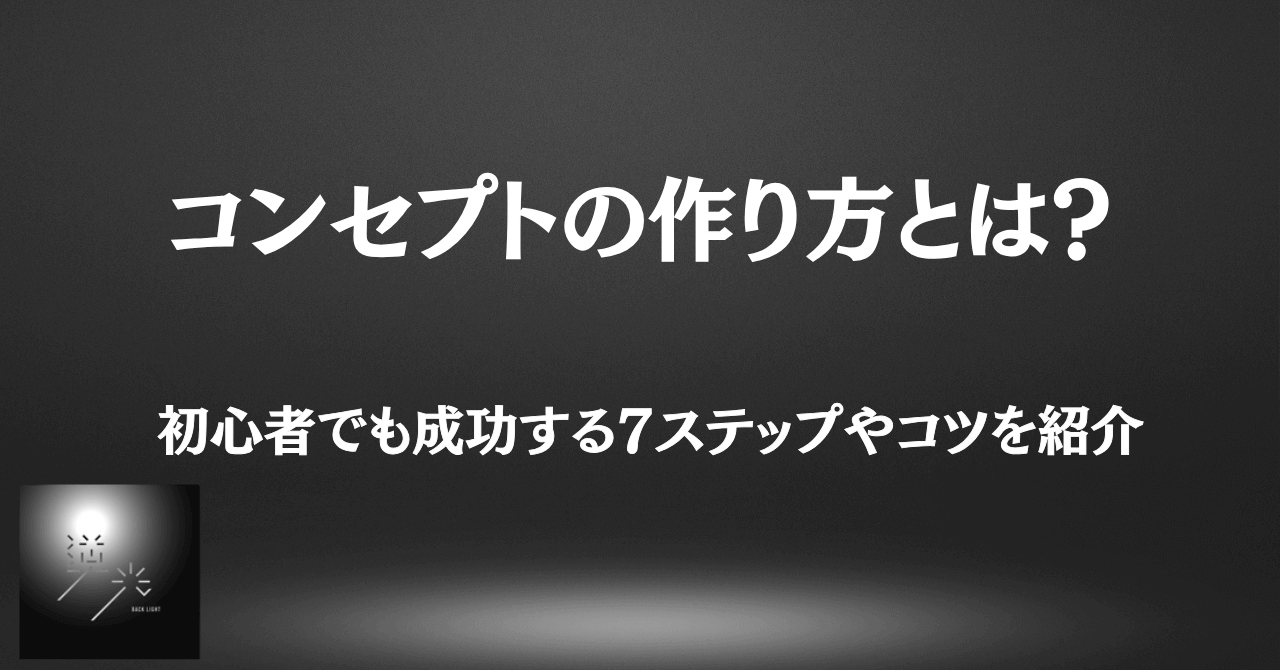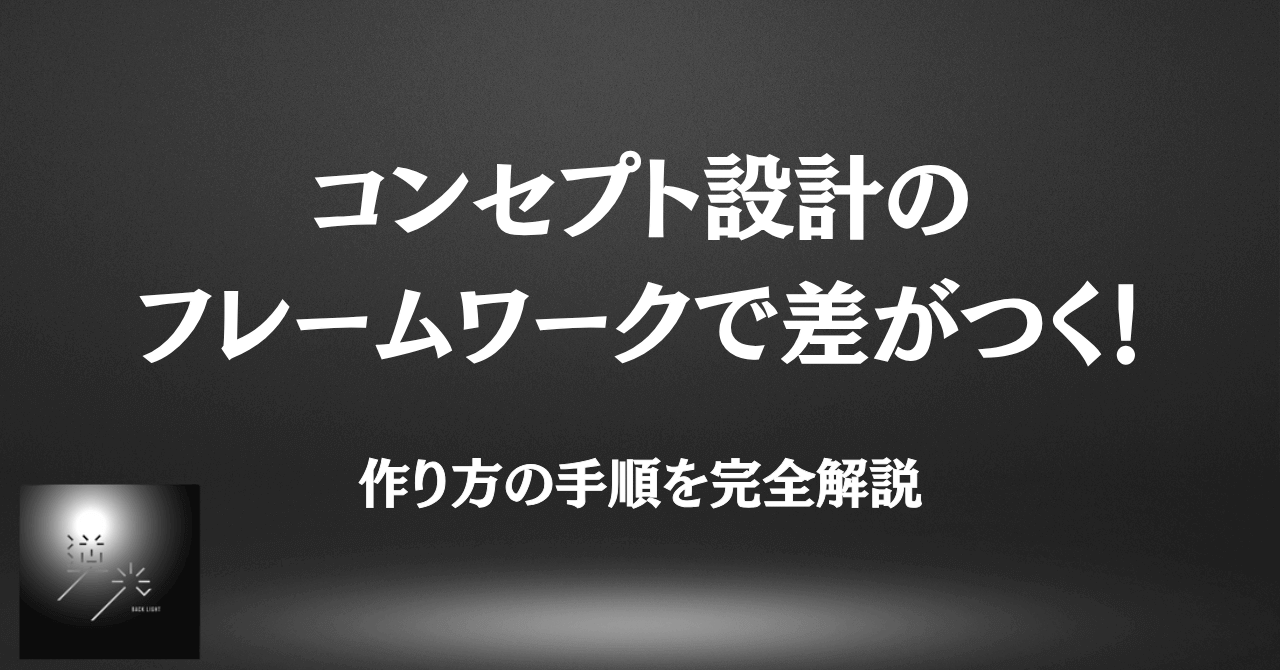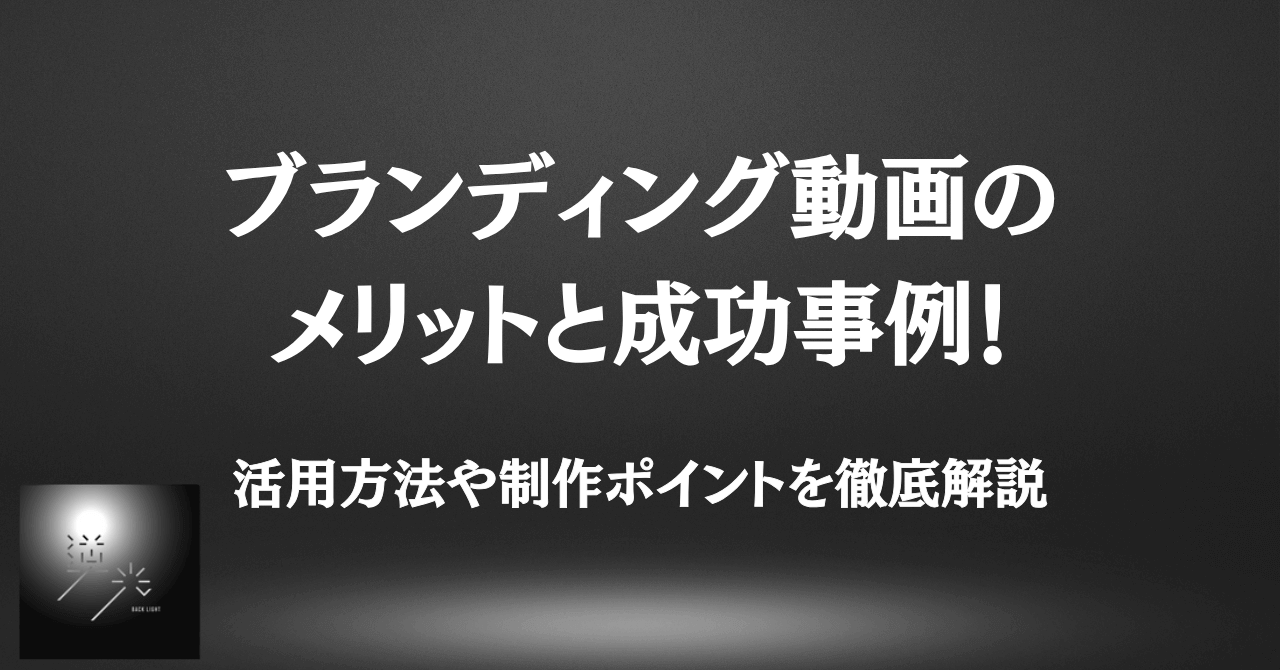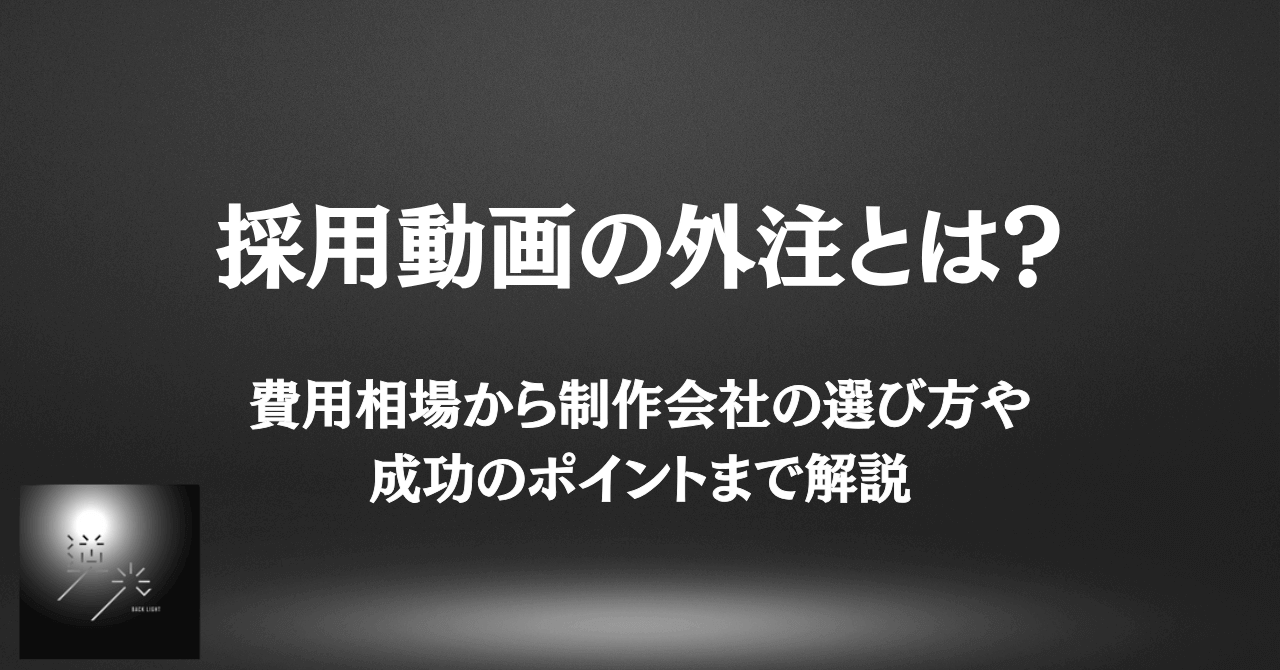「新商品のコンセプトが全く思いつかない」「企画のコンセプトが曖昧で、チーム内にうまく共有できない」そんな悩みを抱えていませんか。
コンセプトがしっかり定まっていないと、プロジェクトは方向性を見失い、時間やコストが無駄になってしまうことも少なくありません。
しかし、ご安心ください。
この記事では、初心者の方でも人を動かす魅力的なコンセプトを論理的に作り上げるための具体的なステップとコツを、分かりやすく解説します。
定番のフレームワークも紹介するので、読み終える頃には、あなたも自信を持ってコンセプト作りの第一歩を踏み出せるようになっているはずです。
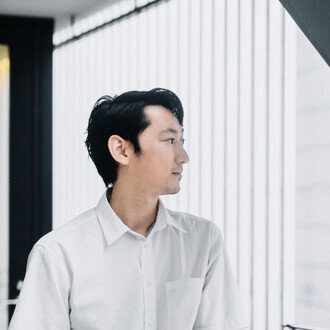
企業の“在り方(Being)”からブランドを再構築する独自の「在り方設計」を提供し、 文脈理解・共感設計を重視した支援で企業の本質的価値を言語化してきたブランディングの専門家。
毎週火曜日朝7時に Spotify【逆張りマーケラジオ】を発信中!>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
コンセプトの作り方とは?
コンセプトとは、日本語で「概念」「全体的な骨格」を意味し、商品やサービス、ブランドが「誰に」「何を」「どのように」提供するのかを簡潔に表現したものです。
良いコンセプトは、顧客に「これは自分のためのものだ!」と共感させ、行動を後押しする力を持っています。
ここでよく混同される言葉に「ビジョン」があります。
- ビジョン:目指すべき将来の理想像やあるべき姿。
- コンセプト:そのビジョンを実現するための具体的なアイデアや骨格。
例えるなら、ビジョンが「目指す山頂」だとすれば、コンセプトは「その山頂に到達するための登山ルート」と言えるでしょう。
つまり、ビジョンは長期的な指針であり、コンセプトは日々の活動を方向づける実践的な道しるべなのです。
ブランディングにおけるコンセプト設計の詳細についてはこちらをご参照ください。
→ブランディングにおけるコンセプトとは?作り方や成功のポイントを紹介
成功するコンセプト作りの前提
この章では、コンセプトを成功に導くために欠かせない、3つの重要な前提を解説します。
この章を読み終える頃には、なぜあなたのコンセプトが感情を揺さぶり、共感を生み出すのかを理解できるでしょう。
“6原則”に学ぶ共感設計
良いコンセプトは、人の心に深く響き、共感を生み出しますが、どのようなコンセプトが共感を生むのでしょうか?
ここでは、アイデアを形作るうえで役立つ6つの原則を紹介します。
【コンセプトを磨き上げる6原則】
- 単純性:誰にでも伝わるシンプルな言葉で表現する
- 意外性:人々の興味を引きつける斬新な視点を取り入れる
- 具体性:具体的なイメージが湧くように描写する
- 信頼性:根拠や権威性を示し、納得感を与える
- 感情性:人の心を揺さぶるストーリーやメッセージを盛り込む
- 物語性:共感や感動を呼ぶ背景やストーリーを語る
コンセプトを磨き上げる6原則を意識することで、あなたのコンセプトは単なる説明文ではなく、人々の心に深く刻まれるメッセージへと進化していくでしょう。
市場と顧客インサイトの読み解き
成功するコンセプトは、顧客の潜在的なニーズや、まだ気づいていない願望(インサイト)を見つけ出すことから始まります。
インサイトとは、顧客自身も気づいていない「心の奥底にある欲求」のことです。
表面的なニーズ「お腹が空いた」だけでなく、背景にあるインサイト「疲れたから、手軽に癒やされたい」まで深く掘り下げることが重要です。
顧客が何を求めているのか、何に不満を感じているのかを徹底的に分析することで、より響くコンセプトが生まれます。
目的やKGI/KPIの言語化
コンセプトづくりに着手する前に、事業の目的やゴール指標(KGI)、そして中間指標(KPI)を明確に言語化しておきましょう。
コンセプトはクリエイティブな作業ですが、最終的にはビジネスの目標達成に寄与するものです。
事前に「何をもって成功とするか(KGI)」を定め、それを達成するための重要な指標(KPI)を設定しておくことで、チーム全体で目指すべき方向性が明確になります。
例えば「年内に新規顧客を○○人獲得する」というKGIがあれば、それに直結するKPI(サイト訪問数や問い合わせ数など)が見えてきます。
KGI・KPIが曖昧なままだと、「売上を増やしたい」「顧客を増やしたい」といった漠然とした目標に留まり、何をすべきか判断しにくくなるのです。
目標を数値と言葉で具体化し共有することで、コンセプト設計のブレも防げますし、完成したコンセプトが社内外で評価・検証しやすくなるメリットもあります。
コンセプトの作り方4ステップ
ここでは、初心者でも実践できるコンセプト作成の具体的な4ステップを解説します。
この章を読めば、あなたのビジネスに最適なコンセプトを論理的に構築する方法が分かります。
採用領域でのコンセプト作成については、こちらでも詳しく解説しています。
→採用コンセプトの作り方5ステップ!失敗しないポイントまで徹底解説
現状分析:課題と強みを棚卸し
コンセプト作成の第一歩は、現状を客観的に把握することです。
まずは、あなたのビジネスや商品、サービスが現在どのような状況にあるのかを徹底的に洗い出しましょう。
- 自社の強み・弱み:他社にはない独自の技術やノウハウ、サービスの特徴は何か?逆に、改善すべき点はどこか?
- 顧客の課題:ターゲットとなる顧客がどんな悩みや不満を抱えているか?
- 市場の動向:競合はどんな商品やサービスを提供しているか?市場全体にどのようなトレンドがあるか?
以上の情報を詳細に分析することで、コンセプトの土台となる要素が見えてきます。
ペルソナ設定とジョブ理論の活用
コンセプトをより深く、魅力的にするために、ペルソナとジョブ理論を活用しましょう。
ペルソナとは、あなたのサービスを利用する架空の人物像を詳細に設定することです。
年齢、性別、職業、家族構成、趣味、ライフスタイル、そしてどんな悩みを抱えているかまで具体的に設定することで、曖昧だったターゲットが明確になるでしょう。
さらに、ジョブ理論は、顧客がなぜその商品やサービスを「雇用」するのかを考えるフレームワークです。
単に「コーヒーが飲みたい」というニーズだけでなく、「忙しい仕事の合間に一息つくために」というように、顧客が達成したい「仕事(ジョブ)」を掘り下げます。
このジョブを理解することで、顧客の潜在的な欲求に響くコンセプトが見つかります。
ベネフィット抽出→感情フックを設計
ペルソナとジョブが明確になったら、次はベネフィットを抽出します。
ベネフィットとは、その商品やサービスが顧客にもたらす「良いこと」や「価値」のことです。
商品の特徴(例:軽量でコンパクト)ではなく、ベネフィットによって顧客が得られる利益(例:持ち運びが楽になり、いつでもどこでも使える)を検討しましょう。
このベネフィットに「感情フック」を加えましょう。
感情フックとは、顧客の感情に訴えかけるキーワードやメッセージのことです。
例えば、「家事の負担を減らす」というベネフィットに対して、「家族と過ごす時間が増える幸せ」という感情フックを付け加えることで、コンセプトはより魅力的になります。
コアメッセージを一言に凝縮
最後に、今までの分析で得た要素を一つのコアメッセージに凝縮します。
要するに、あなたのコンセプトを端的に表す一言です。
コアメッセージ作成のポイント
- 簡潔さ:誰にでもわかる簡単な言葉で表現する
- 具体性:抽象的な表現を避け、具体的なイメージが伝わるようにする
- 独自性:他社にはない、あなただけの価値を際立たせる
このコアメッセージは、あなたのビジネスのすべての活動の軸となります。
>>コンセプトやブランディングの相談をしてみる
>>逆光のブランディング支援実績を見てみる
コンセプト立案に役立つ定番フレームワーク
ここでは、コンセプトを論理的に構築するために役立つ、3つの定番フレームワークを紹介します。
この章を読むことで、コンセプトの要素を整理し、客観的に分析できるようになるでしょう。
より詳しいフレームワークの活用方法についてはこちらをご参照ください。
→コンセプト設計のフレームワークで差がつく!作り方の手順を完全解説
ペルソナ作成でターゲット像を具体化
コンセプト設計では前述の通りペルソナ作成が有効です。
ペルソナは、サービスの典型的な利用者を表す架空の人物像でした。
年齢・性別・居住地・職業から、1日の行動パターン、抱える悩み、価値観、よく使うメディアまで可能な限り具体的に設定します。
このようにターゲット像を具体化することで、チーム内で「この人ならどう感じるか?」と議論しやすくなり、共通認識が生まれるのです。
ペルソナを作成する際は、実在の顧客データやインタビュー結果を反映させると信憑性が高まります。
可能であればマーケティングデータやユーザーアンケートを用いて、空想上の人物になり過ぎないよう注意しましょう。
ペルソナがしっかり機能すれば、コンセプト検討時にも「このペルソナに響く表現か?」と判断基準が明確になります。
ターゲットを思い描きながら言葉を選ぶことで、独りよがりではないユーザー視点のコンセプトに近づけることができるのです。
3C分析で市場と競合を俯瞰する
マーケティング戦略立案ではお馴染みの3C分析も、コンセプトづくりの下地として有用です。
3C分析とは、市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの観点から環境分析を行うフレームワークです。
市場(Customer)の分析では市場規模や成長性、顧客ニーズの傾向を洗い出します。
競合(Competitor)分析では主要な競合の動向や強み・弱み、自社との違いを比較します。
自社(Company)の分析では自社の強み・弱みやリソースを再確認しましょう。
こうした情報を整理すると、自社が市場でどんな立ち位置にあり、どこで差別化できるかが見えてきます。
コンセプト策定時に3C分析の結果を参照すれば、「市場のどのニーズに応えるコンセプトか」「競合にはないどんな独自価値を打ち出すか」が明確になるでしょう。
つまり3C分析は、コンセプトの戦略的な裏付けとして機能します。
全体像を俯瞰した上でコンセプトを考えることで、的外れなアピールを避け、競合に埋もれない独自のメッセージを作れるのです。
カスタマージャーニーマップで体験を設計する
カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスを認知してから購入に至るまでの一連の行動、思考、感情を可視化したものです。
【カスタマージャーニーマップの作成項目例】
- フェーズ:認知→情報収集→比較検討→購入→利用→再購入
- 顧客の行動:どんなウェブサイトを見るか、誰に相談するかなど
- 顧客の思考・感情:「こんな商品があるんだ」「本当に効果あるかな…」「買ってみて良かった!」など
- 課題・ニーズ:各フェーズで顧客が抱える不満や解決したいことは何か
このマップを作成することで、各段階で顧客が抱く感情や課題を深く理解し、適切なタイミングで響くメッセージやサービスを設計できるようになるでしょう。
動画でのコンセプト表現についてはこちらをご参照ください。
→コンセプトムービーとは?作り方5ステップと費用相場をわかりやすく解説
コンセプトの作り方に関してよくある質問
この章では、コンセプト作成においてよくある疑問に答えます。
疑問を解消することで、コンセプト作りへの不安が払拭されるでしょう。
良いコンセプトの条件は?
良いコンセプトとは、誰にでも一言で伝わり、聞く人に「自分ごと」として感じさせるものです。
具体的には以下の3つの要素を満たしていることが重要です。
- ターゲットが明確である:「誰のために」作られたものかがはっきりしている
- 提供価値が明確である:「どんな価値」を提供するかが明確である
- 独自性がある:他社にはない「なぜ自社が提供するのか」という理由がある
コンセプトとビジョンの違いは?
コンセプトとビジョンの違いは、コンセプトが商品・サービスの価値を伝える具体的メッセージなのに対し、ビジョンは企業や事業が描く長期的な理想像である点です。
コンセプトは目の前のプロダクトやブランドにフォーカスし、「何を・誰に・どう提供するか」という価値提案を端的に示します。
一方ビジョンは「将来こうありたい」「社会にこんな価値を提供したい」といった壮大な目標や世界観を語るものです。
言わばコンセプトは現在進行形の戦術的メッセージで、ビジョンは未来志向の戦略的指針とも言えます。
例えば、コンセプトが「忙しい人の時間を生み出す〇〇サービス」だとしたら、ビジョンは「テクノロジーで人々の生活を豊かにする」といった具合です。
ただし両者は無関係ではなく、ビジョンが明確だとコンセプトにも一貫したストーリーが生まれます。
企業の大きなビジョンの下で、その一端を具体化したものが各商品のコンセプトとも言えるでしょう。
初心者でも作れますか?
はい、もちろん作れます。
大切なのは、最初から完璧なものを作ろうとしないことです。
まずはこの記事で紹介したフレームワークを参考に、頭の中にあるアイデアを一つずつ書き出してみましょう。
段階的に見直し、改善を繰り返すことで、より良いコンセプトに仕上がっていきます。
コンセプト作りに必要なツールは?
以下のツールが役立ちます。
- マインドマップツール(MindMeisterなど):アイデアの発散や整理に便利です。
- 作図ツール(Canva、Miroなど):ペルソナやカスタマージャーニーマップを視覚的に作成できます。
- ノートや付箋:手書きで自由にアイデアを出すのに最適です。
コンセプトを考える3要素は?
コンセプトを考える上で根幹となる3つの要素は、「ターゲット(誰に)」「価値(何を)」「独自性(どのように)」です。
まず、「誰の」ための商品・サービスなのかを明確に定義します。次に、そのターゲットに対して「どのような」価値(ベネフィット)を提供するのかを具体化します。
そして最後に、その価値を競合他社とは違う「どのような」独自の方法で提供するのかを明らかにします。
この3つの要素が明確かつ一貫してつながっていることで、コンセプトは強固で説得力のあるものになるでしょう。
コンセプトの作り方まとめ
コンセプト設計は、単なる商品説明ではなく、顧客の心を動かす感情設計の作業です。
あなたのサービスや商品が持つ機能的な価値を、顧客の感情に響く情緒的な言葉に置き換えることが重要です。
そのためには、まず「なぜこの商品(サービス)を作ろうと思ったのか?」という原体験を掘り下げてみてください。
あなたのビジネスの「らしさ」の核となるヒントが隠されているかもしれません。
そして、この核を軸に、誰に、何を、どのように提供するのかを具体化していくのです。
コンセプトが固まれば、発信や営業活動に一貫性が生まれ、顧客の共感を呼びやすくなるでしょう。
この記事で紹介したステップとフレームワークを参考に、ぜひあなたのビジネスを成功に導く、強力なコンセプトを創り出してみてください。